日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
熱中症対策を毎年アップデートしている…というのは過去記事にも書いていますが…
<過去記事:熱中症対策を年々アップデートしています。>
ここの所、本当に「去年と同じ対策では間に合わない」と痛感しています…。
一応、今年はかなり「前倒し」で熱中症対策を始めていたのですが(6月くらいにはもう始めていたはず)…
ここに来て「気づくと体調不良」「無自覚のパフォーマンス低下」が出てきてしまっています…。
「暑くなってくると脳のパフォーマンスも低下してくる」というのは、去年あたりから既に気づいていたことなのですが…
(アイディアが浮かびづらくなったり、上手く思考がまとまらなかったり、集中力が落ちてしまったり…。)
「自覚のできる脳のパフォーマンス低下」は「まだマシな方」だったのだと、今年になって気づきました…。
本当に恐ろしい脳パフォーマンスの低下は「いつの間にか」「無自覚で」出て来るものなのです…。
皆さんも「普段はしないようなミスをしてしまう」「物忘れやド忘れが増えた」という時には、プチ熱中症を疑ってみた方が良いでしょう。
特に、睡眠の質が保てているかどうかは気をつけた方が良いです。
自分は今年から、一番の酷暑の時季にはエアコンにプラスして「凍らせるタイプの冷却シート」を頭に貼っています。
(おでこ等に貼るタイプのゲルシートです。冷凍庫で冷やしてもカチンコチンにならず、朝まで冷却効果が続きます。肌に直接貼ると最初の方が冷た過ぎるため、自分は髪の上から貼っていました。)
あと、日中の気温が40℃を超えた日には、両手首の内側に冷却シート(凍らせない普通のタイプ)を貼り、上からリストバンドで固定して仕事をしていました。
(家の中なら「おでこに冷却シート」も普通にできますが、オフィスの中では無理ですからね…。職場にもエアコンはあるのですが、外気温が40℃前後の時はさすがに効きが悪いです…。)
リストバンドは固定機能の他、冷却シートの「目隠し」にも有効です。
難点はリストバンドの色によっては逆に目立つことと、手を洗う時に外したりズラしたりが大変な所ですかね…。
(うちの会社はPC入力が多いので、手にリストバンドやサポーターをしていてもそんなに気にされない方です。)
それと、去年までは頑なに「真夏でもキンキンに冷えた飲み物は飲まない」を貫いていたのですが(胃腸のことを考えて)…
今年は初めて「冷えた飲み物」を解禁しました。
お腹が下らないかと心配していたのですが、身体が熱を持ち過ぎているせいか、逆に「ほど良い冷却効果」という感じで大丈夫でした。
(朝でも30℃超えの中、自転車で会社に通勤すると、去年まではだいぶ長い間「汗ダラダラ」状態だったのですが、出社後すぐに冷たい飲み物を飲んでいる今年は「汗をかいている時間」が短くなったように感じます。)
…ただ、一日に何回も冷たい飲み物を飲んでいたら、さすがにちょっと胃が弱ってきた感はあるのですが(バランスが難しいです)…。
なお、今年は観測史上最高気温41.8℃が出たと騒がれていますが…
観測所のない近隣の某市では、その日ウェザーニューズで44℃予想が出ていました…。
観測所って、全市町村にあるわけじゃないですからね…。
<過去記事:熱中症対策を年々アップデートしています。>
ここの所、本当に「去年と同じ対策では間に合わない」と痛感しています…。
一応、今年はかなり「前倒し」で熱中症対策を始めていたのですが(6月くらいにはもう始めていたはず)…
ここに来て「気づくと体調不良」「無自覚のパフォーマンス低下」が出てきてしまっています…。
「暑くなってくると脳のパフォーマンスも低下してくる」というのは、去年あたりから既に気づいていたことなのですが…
(アイディアが浮かびづらくなったり、上手く思考がまとまらなかったり、集中力が落ちてしまったり…。)
「自覚のできる脳のパフォーマンス低下」は「まだマシな方」だったのだと、今年になって気づきました…。
本当に恐ろしい脳パフォーマンスの低下は「いつの間にか」「無自覚で」出て来るものなのです…。
皆さんも「普段はしないようなミスをしてしまう」「物忘れやド忘れが増えた」という時には、プチ熱中症を疑ってみた方が良いでしょう。
特に、睡眠の質が保てているかどうかは気をつけた方が良いです。
自分は今年から、一番の酷暑の時季にはエアコンにプラスして「凍らせるタイプの冷却シート」を頭に貼っています。
(おでこ等に貼るタイプのゲルシートです。冷凍庫で冷やしてもカチンコチンにならず、朝まで冷却効果が続きます。肌に直接貼ると最初の方が冷た過ぎるため、自分は髪の上から貼っていました。)
あと、日中の気温が40℃を超えた日には、両手首の内側に冷却シート(凍らせない普通のタイプ)を貼り、上からリストバンドで固定して仕事をしていました。
(家の中なら「おでこに冷却シート」も普通にできますが、オフィスの中では無理ですからね…。職場にもエアコンはあるのですが、外気温が40℃前後の時はさすがに効きが悪いです…。)
リストバンドは固定機能の他、冷却シートの「目隠し」にも有効です。
難点はリストバンドの色によっては逆に目立つことと、手を洗う時に外したりズラしたりが大変な所ですかね…。
(うちの会社はPC入力が多いので、手にリストバンドやサポーターをしていてもそんなに気にされない方です。)
それと、去年までは頑なに「真夏でもキンキンに冷えた飲み物は飲まない」を貫いていたのですが(胃腸のことを考えて)…
今年は初めて「冷えた飲み物」を解禁しました。
お腹が下らないかと心配していたのですが、身体が熱を持ち過ぎているせいか、逆に「ほど良い冷却効果」という感じで大丈夫でした。
(朝でも30℃超えの中、自転車で会社に通勤すると、去年まではだいぶ長い間「汗ダラダラ」状態だったのですが、出社後すぐに冷たい飲み物を飲んでいる今年は「汗をかいている時間」が短くなったように感じます。)
…ただ、一日に何回も冷たい飲み物を飲んでいたら、さすがにちょっと胃が弱ってきた感はあるのですが(バランスが難しいです)…。
なお、今年は観測史上最高気温41.8℃が出たと騒がれていますが…
観測所のない近隣の某市では、その日ウェザーニューズで44℃予想が出ていました…。
観測所って、全市町村にあるわけじゃないですからね…。
PR
個人的に、最近のG○oleさんのAI活用の仕方に失望を覚えています。
なぜなら最近のGo○leさんは「サイトやブログや投稿記事を紹介する」のではなく「そこから拾った情報を要約して提示する」方へ舵を切っているからです。
無料版の方なら一応、勝手に最上部にAI要約は出るものの、元記事へのリンクがあるのでまだマシなのですが(そのリンクもひどく分かりづらいのでちょっとアレなのですが)…
AIモードの方ではリンクも出なくなるという話を聞いています。
(ネット記事を読む限り、ChatGPTのようなAIチャットサービスを目指している印象があるのですが…実際のところどうなんでしょう?正直最初に読んだ時は「自分にしか無い強みを棄てて、わざわざ二番煎じに甘んじようとする意味が分からない」「そこまで思い詰めるほど広告収入が減っているのだろうか」と邪推してしまったのですが…。)
Goo○eさんはソレを「新たな情報検索の形」のように語っていますが…
どうも根本的に、検索者のニーズを「分かっていない」気がしてなりません。
(あるいは検索者本人すら、そのニーズに無自覚なのかも知れませんが。)
だって「検索」って、べつに「情報」だけを求めてするわけではないじゃないですか。
暇な時に、ふらふらウィンドウショッピングをするのを楽しむように、たくさんの情報が並んでいるのをざっと読んで「こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだ」というのを楽しむ時って、ありませんか?
AIによる要約・回答は、検索者から「選ぶ楽しみ」「探す楽しみ」を奪ってしまうのです。
そもそもAI要約・回答が「その人」に合った答えを導き出してくれるとは限りません。
人間の性質や生きる環境は十人十色で、求めている情報も実は細かく違っています。
(IQの高い人ならAIに質問する時点でそのあたりを細かく「条件付け」するでしょうが、「それほどでもない人」はそもそも「万人に通じる答えが存在する」と勘違いしていて、条件設定などしないことでしょう。)
AIはおそらく一番「一般的」な答えを出してくるでしょうが…実はもっとその人に合った「答え」がネット上には他に存在するかも知れないのです。
AIの答えだけで「こんなものか」と諦めてしまう人は、その「答え」に一生気づけません。
検索で出てきたサイトや投稿を直感で選んで読み漁るのって、「時間の無駄」になるリスクもありますが、逆に「思いがけない情報との出逢い」を生んでくれるものでもあります。
「要約」は一見タイパが良いように見えて、「急がば回れ」の「逆」なのです。
(さらに言えば、その「時間の無駄」と「思わぬ掘り出し物」を行ったり来たりするのが面白かったりするのですが…たぶん人生の醍醐味って、そういう所にあるものなんじゃないでしょうか?)
そんなこともあり、自分はAI要約を「お出しされる」たびに「余計なお世話なんじゃい!」と思ってしまいます。
(せめて要約が欲しいかどうか訊いてから出してくれないものでしょうか?そもそも自分はAIの「答え」が合っているかどうか元記事と見比べてファクトチェックするタイプですので、逆に手間なんですよ…。なお、言及記事の少ない事柄については誤答を出すこともある、というのは既に確認済。)
<関連記事:ある猫種を検索してみたら、AIの弱点とその対策にうっすら気づいた。>
そしてそれより何より最悪なのが「AI要約・回答が“人と人との出逢い”を奪ってしまうこと」です。
サイトやブログや記事の紹介なら、検索者が「その知を持った人」と出逢えるのです。
ふと出逢った「鋭い意見」や「独自の視点」にハッとさせられて、その人の過去記事を遡って読んだり、SNSを辿ってみたことってありませんか?
AI要約・回答では、情報は「その場限りで終わり」です。
その「元となった人」に出逢うこともなければ、過去記事に「もっと感動できる言葉」があることも知らないままです。
AIで「元の記事」と切り離された情報は「いもづる式に情報をたどること」を阻害してしまうのです。
自分もそうなので言うのですが…人間って、ただ情報だけを求めているわけではなく、その背後にいる「人間」を求めていたりはしないでしょうか?
その人がその情報を語るに至った「事情」や「物語」を求めていたりはしないでしょうか?
自分は時々X(旧Twitter)や動画サイトで「見知らぬ他人の意見」を読むのが好きです。
時にひどい暴言に胸が痛んだり、無神経な言葉に苛立ったりすることもありますが、それを「要約」で読みたいとは思いません。
なぜなら、AIで加工されていない、その人の「生の言葉」が読みたいからです。
(まぁ、それはあくまで「他人事」に対する意見だから、というのもあるのでしょうが…。あるいは自分が創作活動の糧として、人間のグロテスクな部分をも見たがっているせいかも…。)
「情報検索はAIによる回答だけで良い」と思ってしまっている人は、きっとそういう「人を求める人の気持ち」「人を知りたいと思う人の気持ち」が理解できていないのでしょう。
そして、そういう人が「開発」をしてしまう限り、きっと「人とネットとのつき合い」はどんどん機械的で無味乾燥な「つまらない」ものになってしまうことでしょう。
自分は検索サイトにおけるAI活用の仕方は、むしろ「人と情報(その背後にいる人)とのマッチング」だと思っています。
正直、現時点でも検索サイトの検索性能って、まだまだ不充分だと思いませんか?
ある程度の「あいまい検索」には対応できるようになっても「キーワードも思いつかない」情報って、検索できないじゃないですか。
むしろAIが導入され始めてから「それは求めていない(余計なお世話)」という余分な情報が交ざるようになり、検索性能が劣化している印象すらあります。
情報要約だの何だのを考える前に、まず本分である「検索」を、もっと突き詰めて考えるべきなのではないでしょうか?
そして出来ることならば「検索」が「人から情報を切り離し、人と人との出逢いの機会を失わせるもの」ではなく「人と人とが出逢えるもの」になってくれることを願います。
「人と出逢う」「人を知る」ということは、きっと単に「情報を知る」ことの何十倍、何千倍も価値あるもののはずなので…。
なぜなら最近のGo○leさんは「サイトやブログや投稿記事を紹介する」のではなく「そこから拾った情報を要約して提示する」方へ舵を切っているからです。
無料版の方なら一応、勝手に最上部にAI要約は出るものの、元記事へのリンクがあるのでまだマシなのですが(そのリンクもひどく分かりづらいのでちょっとアレなのですが)…
AIモードの方ではリンクも出なくなるという話を聞いています。
(ネット記事を読む限り、ChatGPTのようなAIチャットサービスを目指している印象があるのですが…実際のところどうなんでしょう?正直最初に読んだ時は「自分にしか無い強みを棄てて、わざわざ二番煎じに甘んじようとする意味が分からない」「そこまで思い詰めるほど広告収入が減っているのだろうか」と邪推してしまったのですが…。)
Goo○eさんはソレを「新たな情報検索の形」のように語っていますが…
どうも根本的に、検索者のニーズを「分かっていない」気がしてなりません。
(あるいは検索者本人すら、そのニーズに無自覚なのかも知れませんが。)
だって「検索」って、べつに「情報」だけを求めてするわけではないじゃないですか。
暇な時に、ふらふらウィンドウショッピングをするのを楽しむように、たくさんの情報が並んでいるのをざっと読んで「こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだ」というのを楽しむ時って、ありませんか?
AIによる要約・回答は、検索者から「選ぶ楽しみ」「探す楽しみ」を奪ってしまうのです。
そもそもAI要約・回答が「その人」に合った答えを導き出してくれるとは限りません。
人間の性質や生きる環境は十人十色で、求めている情報も実は細かく違っています。
(IQの高い人ならAIに質問する時点でそのあたりを細かく「条件付け」するでしょうが、「それほどでもない人」はそもそも「万人に通じる答えが存在する」と勘違いしていて、条件設定などしないことでしょう。)
AIはおそらく一番「一般的」な答えを出してくるでしょうが…実はもっとその人に合った「答え」がネット上には他に存在するかも知れないのです。
AIの答えだけで「こんなものか」と諦めてしまう人は、その「答え」に一生気づけません。
検索で出てきたサイトや投稿を直感で選んで読み漁るのって、「時間の無駄」になるリスクもありますが、逆に「思いがけない情報との出逢い」を生んでくれるものでもあります。
「要約」は一見タイパが良いように見えて、「急がば回れ」の「逆」なのです。
(さらに言えば、その「時間の無駄」と「思わぬ掘り出し物」を行ったり来たりするのが面白かったりするのですが…たぶん人生の醍醐味って、そういう所にあるものなんじゃないでしょうか?)
そんなこともあり、自分はAI要約を「お出しされる」たびに「余計なお世話なんじゃい!」と思ってしまいます。
(せめて要約が欲しいかどうか訊いてから出してくれないものでしょうか?そもそも自分はAIの「答え」が合っているかどうか元記事と見比べてファクトチェックするタイプですので、逆に手間なんですよ…。なお、言及記事の少ない事柄については誤答を出すこともある、というのは既に確認済。)
<関連記事:ある猫種を検索してみたら、AIの弱点とその対策にうっすら気づいた。>
そしてそれより何より最悪なのが「AI要約・回答が“人と人との出逢い”を奪ってしまうこと」です。
サイトやブログや記事の紹介なら、検索者が「その知を持った人」と出逢えるのです。
ふと出逢った「鋭い意見」や「独自の視点」にハッとさせられて、その人の過去記事を遡って読んだり、SNSを辿ってみたことってありませんか?
AI要約・回答では、情報は「その場限りで終わり」です。
その「元となった人」に出逢うこともなければ、過去記事に「もっと感動できる言葉」があることも知らないままです。
AIで「元の記事」と切り離された情報は「いもづる式に情報をたどること」を阻害してしまうのです。
自分もそうなので言うのですが…人間って、ただ情報だけを求めているわけではなく、その背後にいる「人間」を求めていたりはしないでしょうか?
その人がその情報を語るに至った「事情」や「物語」を求めていたりはしないでしょうか?
自分は時々X(旧Twitter)や動画サイトで「見知らぬ他人の意見」を読むのが好きです。
時にひどい暴言に胸が痛んだり、無神経な言葉に苛立ったりすることもありますが、それを「要約」で読みたいとは思いません。
なぜなら、AIで加工されていない、その人の「生の言葉」が読みたいからです。
(まぁ、それはあくまで「他人事」に対する意見だから、というのもあるのでしょうが…。あるいは自分が創作活動の糧として、人間のグロテスクな部分をも見たがっているせいかも…。)
「情報検索はAIによる回答だけで良い」と思ってしまっている人は、きっとそういう「人を求める人の気持ち」「人を知りたいと思う人の気持ち」が理解できていないのでしょう。
そして、そういう人が「開発」をしてしまう限り、きっと「人とネットとのつき合い」はどんどん機械的で無味乾燥な「つまらない」ものになってしまうことでしょう。
自分は検索サイトにおけるAI活用の仕方は、むしろ「人と情報(その背後にいる人)とのマッチング」だと思っています。
正直、現時点でも検索サイトの検索性能って、まだまだ不充分だと思いませんか?
ある程度の「あいまい検索」には対応できるようになっても「キーワードも思いつかない」情報って、検索できないじゃないですか。
むしろAIが導入され始めてから「それは求めていない(余計なお世話)」という余分な情報が交ざるようになり、検索性能が劣化している印象すらあります。
情報要約だの何だのを考える前に、まず本分である「検索」を、もっと突き詰めて考えるべきなのではないでしょうか?
そして出来ることならば「検索」が「人から情報を切り離し、人と人との出逢いの機会を失わせるもの」ではなく「人と人とが出逢えるもの」になってくれることを願います。
「人と出逢う」「人を知る」ということは、きっと単に「情報を知る」ことの何十倍、何千倍も価値あるもののはずなので…。
昨今の政治はSNSの影響力が上がっていると言います。
選挙なども、SNSや動画投稿での「情報発信」が上手くできている候補が支持を集めやすいのだとか…。
そんな話を聞くたびに、いつも腑に落ちない思いを抱いているのですが…
世の中そんなに、本人や支持勢力の「自己アピール」を鵜呑みにする層が多いのでしょうか?
…いや、だって「自己アピール」って普通、自分をよく魅せようと盛りがちなモノじゃないですか。
就職活動などで経験のある人は多いと思いますが…
長所はなるべく「より良く見えるように」盛り、短所は「逆に長所に見えるように」上手く誤魔化す…そう書くよう教えられるじゃないですか。
「企業の採用担当者って、こんな“見せかけ”だらけの“自己”アピールをそんなに重視するものなんだろうか?」と逆に社会に不信を抱いたりしませんでしたか?(自分はしました)
自分は物事を判断する際、本人たちの「自己申告」だけを判断材料にしたりはしません。
判断する際に重視するのは「客観的な情報」です。
むしろ主観的で感情的な動画発信やSNSは「振り回されて判断が鈍る」可能性が高いので、なるべく目に入れたくありません。
なお、ここでの「客観的情報」は「反対勢力の意見」ということではありません。
反対勢力は反対勢力で、感情的に意見を吐露していることが多いので、やはり振り回されたくないのです。
(政治系のキリヌキ動画も、いろいろ誇張されていそうで惑わされそうなので目に入れたくありません。)
自分が見るのは、経歴――その人がそれまで何をやってきたのか、です。
既に国会議員としての経験がある候補者なら、オーソドックスですが『国会議員白書』などで「議員としてどんな活動をしてきたのか」見ます。
(スマホではビミョウに見づらい場合もあるサイトですが、国会議員のこれまでの役職や委員出席回数、「発言回数」さらには「発言文字数」やその内容まで調べることができます。議員にはなったけれど大した発言をしていない人などはこれで分かります。)
経験のない新人の場合は、経歴を「感情をなるべく削ぎ落として」見ます。
ポイントは「気に入った候補・気になった候補だけを見るのではなく、必ず全候補の経歴を見比べる」ことです。
「気になった候補」から見るのはアリですが、「気にいらない候補」を見ないのはナシということです。
選挙などの「判断」をする際に一番厄介な「毒」となるのが「感情」です。
「感情」は、好きなものは実物より良く見せ、気に入らないものは実物よりも悪く見せます。
つまりは判断が鈍るのです。
ナチスも当時は国民の選挙によって選ばれました。
ヒトラーは人の感情を煽るのがとても上手く、スピーチの仕方までよく研究していました(※褒めてはいません)。
人の感情を上手く捕えて好意を持たせた者が、善い政治を行ってくれるとは限りません。
だから自分は、大事なものを判断する際に、なるべく感情を削ぎ落とすのです。
「この候補が良い」と思っても、それが「感情に踊らされた結果」でないかどうか、慎重に自分の心に問います。
でも世の中、どうにも「感情のまま」に判断を下している人が多い印象なのですが…気のせいでしょうか?
「感情に溺れる人」って、何かと「愚か」だと馬鹿にされがちですよね?
なのに選挙の時には「感情」を判断の基準にするのでしょうか?
少なくとも「本人」や「支持者たち」の言うことを「本気」に取るのはどうなのか、と思います。
だって、実際には守る気のない公約だろうと、実現不可能な絵空事だろうと、口では何とでも言えるのです。
それを全面的に信じるなんて、悪い意味で素直過ぎやしませんか?(普通は「話半分」で聞くものではありませんか?)
わざと敵を作ったり、劇的にパフォーマンスしてみたり…「演出」で人心を惹きつけるのも「あるある」な戦略ですが…
そういうエンターテイメント性で感情を揺さぶられて、判断を鈍らされてはいませんか?
選挙とは、ある意味「騙し合い」です。
選ぶ側は“見せかけ”や“誇張”や“守る気の無い約束”に騙されず、真実を見抜かなければならないのです。
…ぶっちゃけ、主観的情報(自己発信)は溢れているのに、客観的データは少な過ぎて毎度判断に苦しむのですが…
事は自分たちの未来を決める、大事な判断。これからも慎重に見極めていこうと思うのです。
選挙なども、SNSや動画投稿での「情報発信」が上手くできている候補が支持を集めやすいのだとか…。
そんな話を聞くたびに、いつも腑に落ちない思いを抱いているのですが…
世の中そんなに、本人や支持勢力の「自己アピール」を鵜呑みにする層が多いのでしょうか?
…いや、だって「自己アピール」って普通、自分をよく魅せようと盛りがちなモノじゃないですか。
就職活動などで経験のある人は多いと思いますが…
長所はなるべく「より良く見えるように」盛り、短所は「逆に長所に見えるように」上手く誤魔化す…そう書くよう教えられるじゃないですか。
「企業の採用担当者って、こんな“見せかけ”だらけの“自己”アピールをそんなに重視するものなんだろうか?」と逆に社会に不信を抱いたりしませんでしたか?(自分はしました)
自分は物事を判断する際、本人たちの「自己申告」だけを判断材料にしたりはしません。
判断する際に重視するのは「客観的な情報」です。
むしろ主観的で感情的な動画発信やSNSは「振り回されて判断が鈍る」可能性が高いので、なるべく目に入れたくありません。
なお、ここでの「客観的情報」は「反対勢力の意見」ということではありません。
反対勢力は反対勢力で、感情的に意見を吐露していることが多いので、やはり振り回されたくないのです。
(政治系のキリヌキ動画も、いろいろ誇張されていそうで惑わされそうなので目に入れたくありません。)
自分が見るのは、経歴――その人がそれまで何をやってきたのか、です。
既に国会議員としての経験がある候補者なら、オーソドックスですが『国会議員白書』などで「議員としてどんな活動をしてきたのか」見ます。
(スマホではビミョウに見づらい場合もあるサイトですが、国会議員のこれまでの役職や委員出席回数、「発言回数」さらには「発言文字数」やその内容まで調べることができます。議員にはなったけれど大した発言をしていない人などはこれで分かります。)
経験のない新人の場合は、経歴を「感情をなるべく削ぎ落として」見ます。
ポイントは「気に入った候補・気になった候補だけを見るのではなく、必ず全候補の経歴を見比べる」ことです。
「気になった候補」から見るのはアリですが、「気にいらない候補」を見ないのはナシということです。
選挙などの「判断」をする際に一番厄介な「毒」となるのが「感情」です。
「感情」は、好きなものは実物より良く見せ、気に入らないものは実物よりも悪く見せます。
つまりは判断が鈍るのです。
ナチスも当時は国民の選挙によって選ばれました。
ヒトラーは人の感情を煽るのがとても上手く、スピーチの仕方までよく研究していました(※褒めてはいません)。
人の感情を上手く捕えて好意を持たせた者が、善い政治を行ってくれるとは限りません。
だから自分は、大事なものを判断する際に、なるべく感情を削ぎ落とすのです。
「この候補が良い」と思っても、それが「感情に踊らされた結果」でないかどうか、慎重に自分の心に問います。
でも世の中、どうにも「感情のまま」に判断を下している人が多い印象なのですが…気のせいでしょうか?
「感情に溺れる人」って、何かと「愚か」だと馬鹿にされがちですよね?
なのに選挙の時には「感情」を判断の基準にするのでしょうか?
少なくとも「本人」や「支持者たち」の言うことを「本気」に取るのはどうなのか、と思います。
だって、実際には守る気のない公約だろうと、実現不可能な絵空事だろうと、口では何とでも言えるのです。
それを全面的に信じるなんて、悪い意味で素直過ぎやしませんか?(普通は「話半分」で聞くものではありませんか?)
わざと敵を作ったり、劇的にパフォーマンスしてみたり…「演出」で人心を惹きつけるのも「あるある」な戦略ですが…
そういうエンターテイメント性で感情を揺さぶられて、判断を鈍らされてはいませんか?
選挙とは、ある意味「騙し合い」です。
選ぶ側は“見せかけ”や“誇張”や“守る気の無い約束”に騙されず、真実を見抜かなければならないのです。
…ぶっちゃけ、主観的情報(自己発信)は溢れているのに、客観的データは少な過ぎて毎度判断に苦しむのですが…
事は自分たちの未来を決める、大事な判断。これからも慎重に見極めていこうと思うのです。
小学生の頃、選挙カーを見つけると何人かで一緒に追いかけていって手を振るのがプチブームだったことがあります。
候補者は大概、子どもでもちゃんと手を振り返してくれるので、それが楽しかったのだと思います。
手を振り返してもらえると、それだけでその人に何となく好意を抱いたりして…我ながら「子どもって単純だなぁ」と思います。
子どもの頃は、わりとそんな単純な「好き嫌い」で選挙を見ていたのですが…
さすがに大人となった今は、好き嫌いの感情だけで投票先を選ぶつもりはありません。
だって、自分が好意を持った候補者が良い政治を行ってくれるとは限りませんし、その逆もまた然りだからです。
そもそも、どの党もどの候補も、選挙期間中は「自分を良く見せよう」と必死で、その「作られたイメージ」を見破れる自信もありません。
なので自分は「感情」や「好き嫌い」ではなく「理性」で判断することにしています。
その「理性」は、各党・各候補のマニフェストが「自分の得になることかどうか」という単純なことではありません。
それを「実現」する能力がありそうかどうか…
そもそも実現する「意思」はちゃんとあるのか(口で言うだけならいくらでも言えるため)…
一時的な「点数稼ぎ」で「今だけ良ければ後はどうなっても良い」という考え無しな政策を立ててはいないか(後の国民に借金や遺恨を作りはしないか)…
そこまで考えて選ぼうとはしている…のですが…
実際問題、まだ実績の無い新人さんだと判断のしようも無いですし、実力やマニフェストの真偽を見抜く“目”も自信は無いんですよね…。
ただひとつ心がけているのは「選んで、結果が出て、そこで“おわり”にはしない」ということです。
たとえば自分の投票した候補が当選したなら、その当選後の“その先の結果”までちゃんと見届ける、ということです。
自分の選んだ党や候補が政治をグダグダにしてしまったとしたら、それは自分の“見る目の無さ”にも原因の一端がある、ということです。
選挙も政治も“人を見る目”も、一朝一夕で身につくような簡単なものではありません。
自分の“見る目”が果たして合っていたのかどうか…
それは“結果”を見届けて判断し、間違っていたのなら磨き直していくしかないのです。
候補者は大概、子どもでもちゃんと手を振り返してくれるので、それが楽しかったのだと思います。
手を振り返してもらえると、それだけでその人に何となく好意を抱いたりして…我ながら「子どもって単純だなぁ」と思います。
子どもの頃は、わりとそんな単純な「好き嫌い」で選挙を見ていたのですが…
さすがに大人となった今は、好き嫌いの感情だけで投票先を選ぶつもりはありません。
だって、自分が好意を持った候補者が良い政治を行ってくれるとは限りませんし、その逆もまた然りだからです。
そもそも、どの党もどの候補も、選挙期間中は「自分を良く見せよう」と必死で、その「作られたイメージ」を見破れる自信もありません。
なので自分は「感情」や「好き嫌い」ではなく「理性」で判断することにしています。
その「理性」は、各党・各候補のマニフェストが「自分の得になることかどうか」という単純なことではありません。
それを「実現」する能力がありそうかどうか…
そもそも実現する「意思」はちゃんとあるのか(口で言うだけならいくらでも言えるため)…
一時的な「点数稼ぎ」で「今だけ良ければ後はどうなっても良い」という考え無しな政策を立ててはいないか(後の国民に借金や遺恨を作りはしないか)…
そこまで考えて選ぼうとはしている…のですが…
実際問題、まだ実績の無い新人さんだと判断のしようも無いですし、実力やマニフェストの真偽を見抜く“目”も自信は無いんですよね…。
ただひとつ心がけているのは「選んで、結果が出て、そこで“おわり”にはしない」ということです。
たとえば自分の投票した候補が当選したなら、その当選後の“その先の結果”までちゃんと見届ける、ということです。
自分の選んだ党や候補が政治をグダグダにしてしまったとしたら、それは自分の“見る目の無さ”にも原因の一端がある、ということです。
選挙も政治も“人を見る目”も、一朝一夕で身につくような簡単なものではありません。
自分の“見る目”が果たして合っていたのかどうか…
それは“結果”を見届けて判断し、間違っていたのなら磨き直していくしかないのです。
幼少期、祖父母と一緒に過ごす時間が多かった影響か、自分の中には知らず知らずのうちに身についていた「世渡りの知恵」のようなものがあります。
その1つが「物事の良い面しか言って来ない人を信用してはならない」だったのですが…
…これ、今の世の中を見渡すと、ビックリするくらい「身についていない人」が多くないですか??
むしろ、投資詐欺だの、ラクに稼げるバイトだの、「おいしい話」にホイホイ乗って破滅したなんて話がゴロゴロ転がっているのが恐ろしいところです…。
自分は「うまい話には裏がある」と用心し、行動・選択の前には必ずワンテンポ置いて「よく考える」タイプなのですが…
世の中そんなに「ポジティブな情報」ばかりに釣られて安易に物事を決めてしまう人が多いのでしょうか?
自分はむしろ「プラスの情報しか出ていない」ものは余計に用心します。
なぜなら、物事には必ずメリット・デメリットの両面があるものだからです。
それなのに利点の方しか書いていない・話して来ないということは、相手に「欠点を隠さず公表するだけの誠実性が無い」ということです。
あるいは、必ず存在するはずのウィークポイントをまだ見出せていない――つまり「弱点を把握するだけの能力が無い」ということになります。
いずれにせよ、その相手が「信頼性に欠ける」ということになるのです。
日本には商人の間で古くから伝わる「三方よし」の精神があります。
すなわち「売り手」「買い手」「世間」の三方全てに良い効果をもたらす商売の仕方です。
今でも「ちゃんとした企業」は自社の利益だけでなく、消費者の信頼や社会貢献を考えた企業運営をしています。
しかしながら昨今は「ズルをしてでもユーザーを釣ろう」「数値を誤魔化してでも利益を上げよう」「消費者を騙してでも儲けよう」という真逆な精神性もはびこっているように感じられます。
もはや見知らぬ相手をホイホイ信用してはいけない時代――用心して自衛しなければ簡単に騙され、破滅させられてしまう時代なのです。
今の時代でも、真っ当な企業は一応「商品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」等の法律で縛られています。
ざっくり説明すると「誇大広告や誤解を招く表現で消費者を騙してはいけない」ということです。
たとえば洗剤のCMひとつとっても「99.9%除菌」とは謳っても「100%」と宣伝している所はありませんよね?
あるいは消費者金融のCMの端っこ、あるいは最後の方に細かい字でビッシリ「注意書き」が書かれているのを見たことはありませんか?
(それでもコンプラ スレスレのグレーゾーンを攻める企業はあるのでしょうけど…。)
「まとも」な企業はその種の「法律」がある程度、消費者の「防御壁」になってくれています。
ですが問題は「まとも」でない人々、ハナからコンプライアンスを守る気のない企業や個人です。
そういう人々は誇大広告だろうが虚偽記載だろうが肖像権侵害だろうが何でもやります。
堂々と数字を偽り、堂々とウソを載せ、堂々と有名人の名を騙ります。
そうやって「つくられた」おいしい情報に、うっかり釣られてしまう人がいるのが今の時代なのです…。
「数字は嘘をつかない」で、「人間の言うこと」は疑っても「数字」にはホイホイ釣られてしまうという人も多いのでしょうが…
その「数字は嘘をつかない」には、実は「続き」があることをご存知でしょうか?
「数字は嘘をつかないが、人は数字で嘘をつく」です。
今の時代、魅力的なキャッチコピーだろうが、数字だろうがグラフだろうが、有名人のオススメだろうが、一旦は疑わなければいけない時代です。
ましてAIの進化によるデメリット(と言うより「規制」が無いことのデメリット?)で、その辺の個人でもいくらでも精巧なフェイクが作れてしまうような時代です。
(以前は「日本語があやしいサイトには注意」という「見分け方」もありましたが、それも通用しなくなりつつあります。)
こんな時代で真偽を見抜くひとつのポイントが「メリットだけを謳っていないか?」「デメリットにもちゃんと言及しているか?」なのではないでしょうか?
(騙す気満々の人は、わざわざ欠点なんて語りませんから…。)
その1つが「物事の良い面しか言って来ない人を信用してはならない」だったのですが…
…これ、今の世の中を見渡すと、ビックリするくらい「身についていない人」が多くないですか??
むしろ、投資詐欺だの、ラクに稼げるバイトだの、「おいしい話」にホイホイ乗って破滅したなんて話がゴロゴロ転がっているのが恐ろしいところです…。
自分は「うまい話には裏がある」と用心し、行動・選択の前には必ずワンテンポ置いて「よく考える」タイプなのですが…
世の中そんなに「ポジティブな情報」ばかりに釣られて安易に物事を決めてしまう人が多いのでしょうか?
自分はむしろ「プラスの情報しか出ていない」ものは余計に用心します。
なぜなら、物事には必ずメリット・デメリットの両面があるものだからです。
それなのに利点の方しか書いていない・話して来ないということは、相手に「欠点を隠さず公表するだけの誠実性が無い」ということです。
あるいは、必ず存在するはずのウィークポイントをまだ見出せていない――つまり「弱点を把握するだけの能力が無い」ということになります。
いずれにせよ、その相手が「信頼性に欠ける」ということになるのです。
日本には商人の間で古くから伝わる「三方よし」の精神があります。
すなわち「売り手」「買い手」「世間」の三方全てに良い効果をもたらす商売の仕方です。
今でも「ちゃんとした企業」は自社の利益だけでなく、消費者の信頼や社会貢献を考えた企業運営をしています。
しかしながら昨今は「ズルをしてでもユーザーを釣ろう」「数値を誤魔化してでも利益を上げよう」「消費者を騙してでも儲けよう」という真逆な精神性もはびこっているように感じられます。
もはや見知らぬ相手をホイホイ信用してはいけない時代――用心して自衛しなければ簡単に騙され、破滅させられてしまう時代なのです。
今の時代でも、真っ当な企業は一応「商品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)」等の法律で縛られています。
ざっくり説明すると「誇大広告や誤解を招く表現で消費者を騙してはいけない」ということです。
たとえば洗剤のCMひとつとっても「99.9%除菌」とは謳っても「100%」と宣伝している所はありませんよね?
あるいは消費者金融のCMの端っこ、あるいは最後の方に細かい字でビッシリ「注意書き」が書かれているのを見たことはありませんか?
(それでもコンプラ スレスレのグレーゾーンを攻める企業はあるのでしょうけど…。)
「まとも」な企業はその種の「法律」がある程度、消費者の「防御壁」になってくれています。
ですが問題は「まとも」でない人々、ハナからコンプライアンスを守る気のない企業や個人です。
そういう人々は誇大広告だろうが虚偽記載だろうが肖像権侵害だろうが何でもやります。
堂々と数字を偽り、堂々とウソを載せ、堂々と有名人の名を騙ります。
そうやって「つくられた」おいしい情報に、うっかり釣られてしまう人がいるのが今の時代なのです…。
「数字は嘘をつかない」で、「人間の言うこと」は疑っても「数字」にはホイホイ釣られてしまうという人も多いのでしょうが…
その「数字は嘘をつかない」には、実は「続き」があることをご存知でしょうか?
「数字は嘘をつかないが、人は数字で嘘をつく」です。
今の時代、魅力的なキャッチコピーだろうが、数字だろうがグラフだろうが、有名人のオススメだろうが、一旦は疑わなければいけない時代です。
ましてAIの進化によるデメリット(と言うより「規制」が無いことのデメリット?)で、その辺の個人でもいくらでも精巧なフェイクが作れてしまうような時代です。
(以前は「日本語があやしいサイトには注意」という「見分け方」もありましたが、それも通用しなくなりつつあります。)
こんな時代で真偽を見抜くひとつのポイントが「メリットだけを謳っていないか?」「デメリットにもちゃんと言及しているか?」なのではないでしょうか?
(騙す気満々の人は、わざわざ欠点なんて語りませんから…。)
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(12/06)
(11/29)
(11/23)
(11/08)
(10/26)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
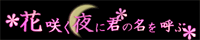
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
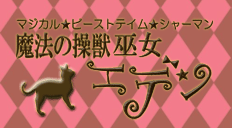
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
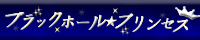
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
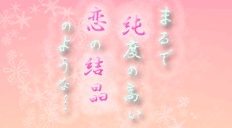
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
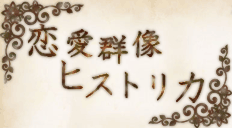
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
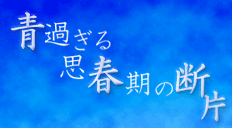
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
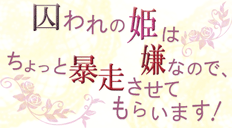
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
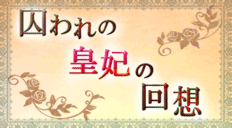
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
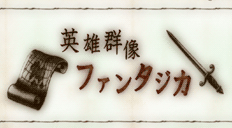
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
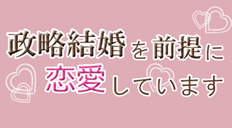
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
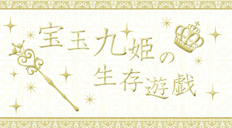
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

