日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
社会人になってから疑問を抱くようになったことがあります。
それは「数字でしか物事を判断できない(しない)人間が多過ぎないだろうか?」という疑問です。
会社の成績にしてもそうです。
何かと「数字」を出して、そのデータを比較しようとしてきますが…
その人の「会社への貢献度」とは、本当にそれだけなのでしょうか?
成績上位の人間の中には「とにかく数をこなせれば良い」という感じで「適当な仕事」をして、そのミスを他人に押しつけてくる人もいます。
後チェックをしなければならない人間は、そんなミスの修正に手間取って、自らは成績を上げている余裕もありません。
また、下手をするとそんなミスに対する「クレーム」が、たまたま電話を取った別の人間の時間を奪うこともあります。
たとえ1人の成績が良くても、それがチーム全体の効率を落としている場合もあるのです。
しかし、個人個人の数値を出してはいても、チーム全体での数値を出していないなら、そんな効率低下による「損失」が数値として表れることはありません。
(あるいはチーム全体で見たとしても、プラマイゼロで「見えにくい」場合もあるかも知れませんが…。)
「数字は嘘をつかない」と言いますが、それは「適切な数字を切り取れた場合」に限ります。
数値というものは、どの部分を切り取るか(どんなデータを出すか)により、全く意味を変えてしまうものなのです。
そしてザッと世の中を見渡す限り、現代人はそれを上手に切り取ることが「できていない」気がします。
そもそも、今の世の中には「間違った切り取り方をしている」「見る人に誤解を与えかねない」ことを「承知の上」で出されている数値もあります。
様々な広告に溢れる「1位」「No.1」という数字…。
それがどんな人によってどんな条件で出された「1位」なのか、ちゃんと見ている人は、どれくらいいるのでしょうか?
また「よくよく見れば『売れた数ではない』ことが分かる」…けれどパッと見には「何だかすごそう」に見える「発行部数〇〇万部突破」「出荷台数〇〇万台突破」という数字…。
(分からなかった方→「売上部数」や「販売台数」ではなく「発行部数」「出荷台数」ですからね。よく見ないとアブないですよ。)
出版社やメーカーでは「作った数」「出荷した数」はすぐに把握できても、その先の販売店で「売れた数」は把握しづらいから…という事情もあるようですが、「作った」「出荷した」と「売れた」では意味が全く違いますよね?
(作って出荷しても、それが全て売り切れるとは限らないでしょうし…。)
それと、最近何かと気にされがちな、レビューの星の数やポイント数…。
前に出した「1位」「No.1」でも言えることですが…あの手の数字は、だいたいが主観的で相対的なもので、客観的で絶対的なものではありません。
たとえば家電が「使えるかどうか」は、ユーザーの使用条件次第。
たとえば評価が低くても、それが「自分の家の間取りに合わなかった」という個人的な理由の場合には全くアテになりませんし…
逆に評価が高くても、その使用条件が自分と全く異なっていた場合には、やはりアテになりません。
レビューは星の数よりもコメントの内容の方(そしてそれが「自分」に当てはまるかどうか)が重要なのです。
また、たとえばエンタメ・コンテンツが「おもしろいかどうか」は、そのユーザーの趣味嗜好次第。
どんなにPVや再生回数が高かろうと、自分の好みに合わないものは結局のところ「おもしろくない」ですし…
逆に数字が少なくても、それは単に「まだ他の人に見出されていない」だけで、見てみれば「ものすごく面白い」可能性だってあるわけです。
そもそも、世の中に溢れる数値の全部が全部「正しい」ものではありません。中には当然、不正なものもあるでしょう。
(ときどき、ニュースでもその手の話題が出ますよね。最近では「No.1」広告の不正のニュースを目にしたばかりですし…。)
それが真っ当な数字なのか、それとも誤魔化され偽られた数字なのか…見極めるのは、容易なことではありません。
世の中、数値に振り回されて、真実を読み誤って、いろいろな意味で「損をしている」人(や団体・企業)が多い気がしてなりません。
特に、他人によって意図的に「作られた」数字に操られているような人たちは…。
(…まぁ、ニュースに出てくるレベルの「組織ぐるみの数値偽装」の場合には、騙されずにいることの方が難しいのかも知れませんが…。)
それは「数字でしか物事を判断できない(しない)人間が多過ぎないだろうか?」という疑問です。
会社の成績にしてもそうです。
何かと「数字」を出して、そのデータを比較しようとしてきますが…
その人の「会社への貢献度」とは、本当にそれだけなのでしょうか?
成績上位の人間の中には「とにかく数をこなせれば良い」という感じで「適当な仕事」をして、そのミスを他人に押しつけてくる人もいます。
後チェックをしなければならない人間は、そんなミスの修正に手間取って、自らは成績を上げている余裕もありません。
また、下手をするとそんなミスに対する「クレーム」が、たまたま電話を取った別の人間の時間を奪うこともあります。
たとえ1人の成績が良くても、それがチーム全体の効率を落としている場合もあるのです。
しかし、個人個人の数値を出してはいても、チーム全体での数値を出していないなら、そんな効率低下による「損失」が数値として表れることはありません。
(あるいはチーム全体で見たとしても、プラマイゼロで「見えにくい」場合もあるかも知れませんが…。)
「数字は嘘をつかない」と言いますが、それは「適切な数字を切り取れた場合」に限ります。
数値というものは、どの部分を切り取るか(どんなデータを出すか)により、全く意味を変えてしまうものなのです。
そしてザッと世の中を見渡す限り、現代人はそれを上手に切り取ることが「できていない」気がします。
そもそも、今の世の中には「間違った切り取り方をしている」「見る人に誤解を与えかねない」ことを「承知の上」で出されている数値もあります。
様々な広告に溢れる「1位」「No.1」という数字…。
それがどんな人によってどんな条件で出された「1位」なのか、ちゃんと見ている人は、どれくらいいるのでしょうか?
また「よくよく見れば『売れた数ではない』ことが分かる」…けれどパッと見には「何だかすごそう」に見える「発行部数〇〇万部突破」「出荷台数〇〇万台突破」という数字…。
(分からなかった方→「売上部数」や「販売台数」ではなく「発行部数」「出荷台数」ですからね。よく見ないとアブないですよ。)
出版社やメーカーでは「作った数」「出荷した数」はすぐに把握できても、その先の販売店で「売れた数」は把握しづらいから…という事情もあるようですが、「作った」「出荷した」と「売れた」では意味が全く違いますよね?
(作って出荷しても、それが全て売り切れるとは限らないでしょうし…。)
それと、最近何かと気にされがちな、レビューの星の数やポイント数…。
前に出した「1位」「No.1」でも言えることですが…あの手の数字は、だいたいが主観的で相対的なもので、客観的で絶対的なものではありません。
たとえば家電が「使えるかどうか」は、ユーザーの使用条件次第。
たとえば評価が低くても、それが「自分の家の間取りに合わなかった」という個人的な理由の場合には全くアテになりませんし…
逆に評価が高くても、その使用条件が自分と全く異なっていた場合には、やはりアテになりません。
レビューは星の数よりもコメントの内容の方(そしてそれが「自分」に当てはまるかどうか)が重要なのです。
また、たとえばエンタメ・コンテンツが「おもしろいかどうか」は、そのユーザーの趣味嗜好次第。
どんなにPVや再生回数が高かろうと、自分の好みに合わないものは結局のところ「おもしろくない」ですし…
逆に数字が少なくても、それは単に「まだ他の人に見出されていない」だけで、見てみれば「ものすごく面白い」可能性だってあるわけです。
そもそも、世の中に溢れる数値の全部が全部「正しい」ものではありません。中には当然、不正なものもあるでしょう。
(ときどき、ニュースでもその手の話題が出ますよね。最近では「No.1」広告の不正のニュースを目にしたばかりですし…。)
それが真っ当な数字なのか、それとも誤魔化され偽られた数字なのか…見極めるのは、容易なことではありません。
世の中、数値に振り回されて、真実を読み誤って、いろいろな意味で「損をしている」人(や団体・企業)が多い気がしてなりません。
特に、他人によって意図的に「作られた」数字に操られているような人たちは…。
(…まぁ、ニュースに出てくるレベルの「組織ぐるみの数値偽装」の場合には、騙されずにいることの方が難しいのかも知れませんが…。)
PR
「イメージ戦略」という言葉があります。
商品を売ったり、評価を高めたりするために「良いイメージ」を築き上げる戦略なわけですが…
これに疑問を持ったことのある方、どれくらいいらっしゃるでしょうか?
「良い『イメージ』さえ作れれば、『実際』は良くなくても良いのか?」「人間って、そんな『うわべ』に騙されて物を買ってしまうものなのか?」と考えたこと、ありませんか?
イメージは、あくまでイメージ。いわば「虚像」であって、「真実」とは限りません。
(「清純派」や「家庭的」「クリーンで誠実」など、特定のイメージを作って活動していた俳優に、そんなイメージとは真逆のスキャンダルが出る…というのも、結構「あるある」ですよね?)
しかしながら、大人になって社会に出てみると、人が意外と「イメージ」に振り回され、「イメージ」に左右されて生きているということが分かります。
おそらくそれは「イメージは目につきやすく、分かりやすい」けれど、「真実は目に見えづらく、理解しづらい」からなのでしょう。
「イメージ」は前述の「イメージ戦略」のように、戦略のために前面に押し出され、目立つようにアピールされていることも少なくありません。
また、「イメージ」は人の意識に浸透しやすいように「分かりやすく」作られていることが多いです。
しかし、その奥にある「真実」は、すぐ目につく所に出ているわけではありませんし、時には隠されていることすらあります。
(むしろ、それを隠すために「イメージ」が作られることすらあるでしょう。)
また、わざと「分かりやすく作られている」イメージとは違い、真実は複雑で、すぐには理解し難いものも多々あります。
だから、人は「分かりやすい」イメージにばかり飛びついて、「分かりづらい」真実を見ることを、おろそかにしてしまうのかも知れません。
しかし、どんなに分かりやすくても、イメージはあくまでイメージに過ぎないのです。
そこに騙されて、そこにばかり目が行ってしまっては、人生を損しかねません。
それは、「イメージは良いけれど、実際には悪い」ものを手に取らされて、「イメージはそれほどでもないけれど、実際はとても良い」ものをスルーしてしまうリスクがあるからです。
実際この世界は、そんな「イメージ」の功罪により、知らず知らずのうちに恐ろしく「何か」をロスしているのではないでしょうか?
イメージ作りに優れたものばかりが生き残り、技術や質は高くてもイメージ作りの下手なものは淘汰されてしまう…
それは結局、ひとりひとりの消費者にとっても、業界全体にとっても、恐ろしく「損」なことなのではないでしょうか?
「イメージ」ではなく「その商品の質」でモノが選ばれるならば、莫大な広告費も要りませんし、それにより開発費が削られて次の商品の質が落ちるということもありません。
質の高い商品なら、自然とリピーターがつくものですが、イメージだけで売る商品は、次々とインパクトのある宣伝を打ち出し続けなければ、消費者に飽きられてしまいます(結果、広告費がさらにかさむ悪循環に陥ります)。
この世界はそうやって、本来なら自然に得られていたはずの大きな利益を、いつの間にかロスして、それに気づかずにいるのではないでしょうか?
とは言え、ここまでイメージ戦略が「一般化」してしまっている現代…できることと言えば、1人1人の消費者が「イメージに騙されないように」意識していくしかないのかも知れません。
ちなみにこの「イメージの功罪」…経済界のみの話ではありません。
むしろ、政治など他の分野の方が、より深刻かも知れません。
イメージに騙されて「騙した方が悪いんだ」と文句を言っても、その時にはもう手遅れかも知れませんので、何とか真実を見極める目を磨いていきたいなぁ…と日々思っています。
商品を売ったり、評価を高めたりするために「良いイメージ」を築き上げる戦略なわけですが…
これに疑問を持ったことのある方、どれくらいいらっしゃるでしょうか?
「良い『イメージ』さえ作れれば、『実際』は良くなくても良いのか?」「人間って、そんな『うわべ』に騙されて物を買ってしまうものなのか?」と考えたこと、ありませんか?
イメージは、あくまでイメージ。いわば「虚像」であって、「真実」とは限りません。
(「清純派」や「家庭的」「クリーンで誠実」など、特定のイメージを作って活動していた俳優に、そんなイメージとは真逆のスキャンダルが出る…というのも、結構「あるある」ですよね?)
しかしながら、大人になって社会に出てみると、人が意外と「イメージ」に振り回され、「イメージ」に左右されて生きているということが分かります。
おそらくそれは「イメージは目につきやすく、分かりやすい」けれど、「真実は目に見えづらく、理解しづらい」からなのでしょう。
「イメージ」は前述の「イメージ戦略」のように、戦略のために前面に押し出され、目立つようにアピールされていることも少なくありません。
また、「イメージ」は人の意識に浸透しやすいように「分かりやすく」作られていることが多いです。
しかし、その奥にある「真実」は、すぐ目につく所に出ているわけではありませんし、時には隠されていることすらあります。
(むしろ、それを隠すために「イメージ」が作られることすらあるでしょう。)
また、わざと「分かりやすく作られている」イメージとは違い、真実は複雑で、すぐには理解し難いものも多々あります。
だから、人は「分かりやすい」イメージにばかり飛びついて、「分かりづらい」真実を見ることを、おろそかにしてしまうのかも知れません。
しかし、どんなに分かりやすくても、イメージはあくまでイメージに過ぎないのです。
そこに騙されて、そこにばかり目が行ってしまっては、人生を損しかねません。
それは、「イメージは良いけれど、実際には悪い」ものを手に取らされて、「イメージはそれほどでもないけれど、実際はとても良い」ものをスルーしてしまうリスクがあるからです。
実際この世界は、そんな「イメージ」の功罪により、知らず知らずのうちに恐ろしく「何か」をロスしているのではないでしょうか?
イメージ作りに優れたものばかりが生き残り、技術や質は高くてもイメージ作りの下手なものは淘汰されてしまう…
それは結局、ひとりひとりの消費者にとっても、業界全体にとっても、恐ろしく「損」なことなのではないでしょうか?
「イメージ」ではなく「その商品の質」でモノが選ばれるならば、莫大な広告費も要りませんし、それにより開発費が削られて次の商品の質が落ちるということもありません。
質の高い商品なら、自然とリピーターがつくものですが、イメージだけで売る商品は、次々とインパクトのある宣伝を打ち出し続けなければ、消費者に飽きられてしまいます(結果、広告費がさらにかさむ悪循環に陥ります)。
この世界はそうやって、本来なら自然に得られていたはずの大きな利益を、いつの間にかロスして、それに気づかずにいるのではないでしょうか?
とは言え、ここまでイメージ戦略が「一般化」してしまっている現代…できることと言えば、1人1人の消費者が「イメージに騙されないように」意識していくしかないのかも知れません。
ちなみにこの「イメージの功罪」…経済界のみの話ではありません。
むしろ、政治など他の分野の方が、より深刻かも知れません。
イメージに騙されて「騙した方が悪いんだ」と文句を言っても、その時にはもう手遅れかも知れませんので、何とか真実を見極める目を磨いていきたいなぁ…と日々思っています。
何がフェイクで、何がリアルなのか、情報の精査の難しい昨今でも、揺るぎなくハッキリ言えることがひとつあります。
「戦争は駄目」だということです。
以前の記事でも触れましたが…
<関連記事:どんな「理由」や「大義」があろうと「手段」は選ばなければならない>
「理由があれば何をしても良い」ではなく、「たとえ理由があろうと、手段は選ばなければならない」のです。
無数にある手段の中から、よりにもよって、多くの人の命を奪うという選択をしておきながら、その正当性を論じること自体が、狂気の沙汰だとは思いませんか?
そんなことが正当化されてしまうとしたら…人間の命の価値は、どこまで薄く軽くなってしまうのでしょう。
他の選択肢もあったはずなのに、他の手段を選んでいたなら奪われなかったはずの命が、奪われていく…
人間が、人間の命を軽視し、人間の命を冒涜し、その価値を、どんどん薄っぺらなものにしていく…
人の命の価値を左右するのは、結局はその時代に生きる人間なのだと思います。
何らかの「理由」があれば、理不尽に人命を奪っても良いという「悪しき前例」を、作るべきではありません。
既にそんな風に正当化されてしまった前例が、歴史上いくつもあるとしても…
これ以上、増やすべきではありません。
それは、今まさに危機に晒されている人々のためだけでなく、今は安全な場所で平穏に暮らしている人々、未来に生きる人々にも関わってくることです。
歴史は、良いものも、悪いものも、学ばれて繰り返されてしまうものですから…。
「戦争は駄目」だということです。
以前の記事でも触れましたが…
<関連記事:どんな「理由」や「大義」があろうと「手段」は選ばなければならない>
「理由があれば何をしても良い」ではなく、「たとえ理由があろうと、手段は選ばなければならない」のです。
無数にある手段の中から、よりにもよって、多くの人の命を奪うという選択をしておきながら、その正当性を論じること自体が、狂気の沙汰だとは思いませんか?
そんなことが正当化されてしまうとしたら…人間の命の価値は、どこまで薄く軽くなってしまうのでしょう。
他の選択肢もあったはずなのに、他の手段を選んでいたなら奪われなかったはずの命が、奪われていく…
人間が、人間の命を軽視し、人間の命を冒涜し、その価値を、どんどん薄っぺらなものにしていく…
人の命の価値を左右するのは、結局はその時代に生きる人間なのだと思います。
何らかの「理由」があれば、理不尽に人命を奪っても良いという「悪しき前例」を、作るべきではありません。
既にそんな風に正当化されてしまった前例が、歴史上いくつもあるとしても…
これ以上、増やすべきではありません。
それは、今まさに危機に晒されている人々のためだけでなく、今は安全な場所で平穏に暮らしている人々、未来に生きる人々にも関わってくることです。
歴史は、良いものも、悪いものも、学ばれて繰り返されてしまうものですから…。
昨今の炎上事案など見ていて、時々感じることなのですが…
ネットという「相手の表情の見えない」世界では、物事が「大袈裟にとらえられがち」「誤解されがち」な傾向がある気がします。
たとえば誰かが何か過ちを犯した時、見ず知らずの人が「そんなことしちゃ駄目じゃん」と言ったとします。
しかし、その言葉のニュアンスが「そんなことしちゃダメじゃん(笑)」なのか「そんなことするなんて許されないことだ(怒)」なのか、すぐには分からないと思いませんか?
(もちろん、「(笑)」や「WW」が付いていたりすれば、そのニュアンスは伝わるでしょうが…。)
言葉は、そうそう簡単に感情を伝えてはくれないのです。
そして、そんな相手の「感情」が「よく見えない」ネットの世界では、何かと相手の感情が誤解されがちなのではないかと…。
読み手の受け取り方ひとつで、ポジティブにもネガティブにも読める言葉は、世の中に星の数ほどあります。
時に、思いがけない言葉が誤解を生むこともあります。
相手に全く誤解を与えずに文章を書くというのは、国語の偏差値が高い人間でも至難の業なのです。
そして、これまでの傾向を見るに、意外と多くの人が「他人の言葉に悪意を読み取りがち」なのではないかと…。
以前このブログの記事にも書いた通り、言葉は書き手だけでなく、読み手にとっても「心の鏡」です。
書き手が思いもしなかった「悪意」がその言葉の中から読み取られたとしたら…それは書き手ではなく、読み手の心の中にあったものなのです。
(その場合、単純な「悪意」と言うより「悪意への疑念」なのかも知れませんが…。)
誰かの「軽いツッコミ」を、「激しい非難」と勘違いしていたりはしませんか?
ただ無遠慮で気遣いに欠けるだけの「(攻撃の意思の無い)率直過ぎる意見」を、「自分に対する攻撃」ととらえ、過剰に「反撃」していたりはしませんか?
もちろん、本当に「攻撃」の場合もあるのでしょうが…
攻撃でないものも攻撃ととらえ、いちいち戦っていたのでは、心が疲弊するばかりだと思いませんか?
まずはそれが本当に「攻撃」なのか、それとも「攻撃にもとらえられかねないツッコミ」あるいは「率直過ぎて失礼・無神経な意見」に過ぎないのか…
その「前提」から疑ってみれば、ネットはもっと寛容で、活動しやすい世界になるのではないでしょうか?
<関連記事:言葉は鏡だ。書き手にとっても、読み手にとっても。>
ネットという「相手の表情の見えない」世界では、物事が「大袈裟にとらえられがち」「誤解されがち」な傾向がある気がします。
たとえば誰かが何か過ちを犯した時、見ず知らずの人が「そんなことしちゃ駄目じゃん」と言ったとします。
しかし、その言葉のニュアンスが「そんなことしちゃダメじゃん(笑)」なのか「そんなことするなんて許されないことだ(怒)」なのか、すぐには分からないと思いませんか?
(もちろん、「(笑)」や「WW」が付いていたりすれば、そのニュアンスは伝わるでしょうが…。)
言葉は、そうそう簡単に感情を伝えてはくれないのです。
そして、そんな相手の「感情」が「よく見えない」ネットの世界では、何かと相手の感情が誤解されがちなのではないかと…。
読み手の受け取り方ひとつで、ポジティブにもネガティブにも読める言葉は、世の中に星の数ほどあります。
時に、思いがけない言葉が誤解を生むこともあります。
相手に全く誤解を与えずに文章を書くというのは、国語の偏差値が高い人間でも至難の業なのです。
そして、これまでの傾向を見るに、意外と多くの人が「他人の言葉に悪意を読み取りがち」なのではないかと…。
以前このブログの記事にも書いた通り、言葉は書き手だけでなく、読み手にとっても「心の鏡」です。
書き手が思いもしなかった「悪意」がその言葉の中から読み取られたとしたら…それは書き手ではなく、読み手の心の中にあったものなのです。
(その場合、単純な「悪意」と言うより「悪意への疑念」なのかも知れませんが…。)
誰かの「軽いツッコミ」を、「激しい非難」と勘違いしていたりはしませんか?
ただ無遠慮で気遣いに欠けるだけの「(攻撃の意思の無い)率直過ぎる意見」を、「自分に対する攻撃」ととらえ、過剰に「反撃」していたりはしませんか?
もちろん、本当に「攻撃」の場合もあるのでしょうが…
攻撃でないものも攻撃ととらえ、いちいち戦っていたのでは、心が疲弊するばかりだと思いませんか?
まずはそれが本当に「攻撃」なのか、それとも「攻撃にもとらえられかねないツッコミ」あるいは「率直過ぎて失礼・無神経な意見」に過ぎないのか…
その「前提」から疑ってみれば、ネットはもっと寛容で、活動しやすい世界になるのではないでしょうか?
<関連記事:言葉は鏡だ。書き手にとっても、読み手にとっても。>
世の中を見ていて、よく思うことの1つが「どうして“分けて考えなきゃいけないこと”を“一緒くたにしてしまう”人が多いのだろう」ということです。
「ソレとコレとは話が別でしょう」「何でソレとコレを全部ワンセットで考えるんだろう」「分けて考えれば簡単に解決法が探せるのに」――そうツッコミを入れたくなるようなことが、世の中、本当に多い気がするのです。
たとえば、一部の“社会的地位のある人間”に見られがちな、他人を見下して、横暴に振る舞ったり、自分の意を無理矢理に通したりする行為……
何となく「自分はこんなに偉いんだから・今までにこれだけの功績を上げてきたのだから、何をしても許される」とでも言うような意識が、透けて見える気がするのですが……
その人の「築き上げてきた地位」や「過去の功績」と、それで「他人を傷つけたり・ないがしろにして良いのかどうか」は、どう考えても別物ですよね?
(そもそも普通に考えて、人間を傷つけたり・ないがしろにする行為自体、許されるものではないですし。)
それから「自分の価値観に照らして“間違ったことをしている人間”に対して“容赦なく鉄槌を下す”行為」……
昨今のネットの炎上事案のみならず、これまでの人類の歴史においても“正義の名の下に行われた虐殺”“大義を掲げた戦争”など、しばしば繰り返されてきた事柄なわけですが……
いつも思うのです。
たとえ本当に相手が間違ったことをしていたにせよ、何かしらの“大義”があるにせよ、それが「どんな手段を選んでも良い」という“理由”にはならない、と。
過去の歴史を見ても、人間(特に大衆)が他人を私的に裁こうとする時、それはしばしば、その罪に見合わないほどに重く苛烈なものにエスカレートしがちです。
しかも、そうした私刑の多くの場合、裁き手は「本当にそこに罪があるのか」「裁きが罪に見合ったものかどうか」を吟味しようとしません。
だからしばしば、間違った情報を鵜呑みにして無関係な人間を巻き込んだり、感情だけで暴走して行き過ぎた行為に及んだりするのかも知れません。
そこには何となく「罪人相手になら何をしても良い」という意識――そして、そんな“何をしても良い相手”に、「“普通なら許されないようなこと”をして心の憂さを晴らそう」という、薄暗い欲望や嗜虐心があるように思えて、うすら寒くなるのです。
結局のところ、古今東西、人類というものは、常に誰かを叩くための“言い訳”を探していて、いざソレを見つければ、嬉々として相手を攻撃する生き物なのではないか……と、人間という生き物に軽く絶望したくなるほどです。
そうして自分が他人に振り下ろしてきた拳や刃が、いずれ自らにも振り下ろされる可能性を、果たしてどれだけの人間が考ているでしょうか。
意識しているにせよ無意識にせよ、「ちょっとした間違いを犯した相手にも過剰な罰を与える」という前例を積み上げれば、この社会はどんどん、そういう“不寛容”な方向に変わっていってしまいます。
そうして「その不寛容さは、いずれ自分自身の首をも絞める可能性が高い」のです。
……これ、少し考えれば分かることだと思うのですが……
世の中の多くの人は、よほど楽観的に「自分だけは大丈夫」と思い込んでいるのでしょうか?
よほどポジティブに「自分なら、どんな過ちも、うっかりも、誤解を招くような発言もするはずがない」と信じているのでしょうか?
それとも、それまでは散々他人を叩いておきながら、いざ自分が過ちを犯して他人に叩かれれば、過去の自分の言動など綺麗サッパリ忘れ去って悲劇の主人公になりきるタイプなのでしょうか。
フランス革命の時、王や王妃に振り下ろされたギロチンの刃は、後に革命を起こした側の指導者や市民の首にも振り下ろされました。
革命の熱に酔っていた市民たちは、果たしてその時、予想できていたでしょうか?
その後に始まる恐怖政治と粛清の嵐を……。
歴史上、人が何かに熱狂し、酔いしれると、知らず知らずのうちに地獄を呼び寄せてしまっていることが多い気がします。
どんな“理由”や“大義”があろうと、我を忘れて手段を選ばなくなっては駄目なのです。
それはこれまでの人類史上、何度も何度も繰り返されてきた過ちであり……それでも尚「きちんと学ばれていない」教訓なのです。
「ソレとコレとは話が別でしょう」「何でソレとコレを全部ワンセットで考えるんだろう」「分けて考えれば簡単に解決法が探せるのに」――そうツッコミを入れたくなるようなことが、世の中、本当に多い気がするのです。
たとえば、一部の“社会的地位のある人間”に見られがちな、他人を見下して、横暴に振る舞ったり、自分の意を無理矢理に通したりする行為……
何となく「自分はこんなに偉いんだから・今までにこれだけの功績を上げてきたのだから、何をしても許される」とでも言うような意識が、透けて見える気がするのですが……
その人の「築き上げてきた地位」や「過去の功績」と、それで「他人を傷つけたり・ないがしろにして良いのかどうか」は、どう考えても別物ですよね?
(そもそも普通に考えて、人間を傷つけたり・ないがしろにする行為自体、許されるものではないですし。)
それから「自分の価値観に照らして“間違ったことをしている人間”に対して“容赦なく鉄槌を下す”行為」……
昨今のネットの炎上事案のみならず、これまでの人類の歴史においても“正義の名の下に行われた虐殺”“大義を掲げた戦争”など、しばしば繰り返されてきた事柄なわけですが……
いつも思うのです。
たとえ本当に相手が間違ったことをしていたにせよ、何かしらの“大義”があるにせよ、それが「どんな手段を選んでも良い」という“理由”にはならない、と。
過去の歴史を見ても、人間(特に大衆)が他人を私的に裁こうとする時、それはしばしば、その罪に見合わないほどに重く苛烈なものにエスカレートしがちです。
しかも、そうした私刑の多くの場合、裁き手は「本当にそこに罪があるのか」「裁きが罪に見合ったものかどうか」を吟味しようとしません。
だからしばしば、間違った情報を鵜呑みにして無関係な人間を巻き込んだり、感情だけで暴走して行き過ぎた行為に及んだりするのかも知れません。
そこには何となく「罪人相手になら何をしても良い」という意識――そして、そんな“何をしても良い相手”に、「“普通なら許されないようなこと”をして心の憂さを晴らそう」という、薄暗い欲望や嗜虐心があるように思えて、うすら寒くなるのです。
結局のところ、古今東西、人類というものは、常に誰かを叩くための“言い訳”を探していて、いざソレを見つければ、嬉々として相手を攻撃する生き物なのではないか……と、人間という生き物に軽く絶望したくなるほどです。
そうして自分が他人に振り下ろしてきた拳や刃が、いずれ自らにも振り下ろされる可能性を、果たしてどれだけの人間が考ているでしょうか。
意識しているにせよ無意識にせよ、「ちょっとした間違いを犯した相手にも過剰な罰を与える」という前例を積み上げれば、この社会はどんどん、そういう“不寛容”な方向に変わっていってしまいます。
そうして「その不寛容さは、いずれ自分自身の首をも絞める可能性が高い」のです。
……これ、少し考えれば分かることだと思うのですが……
世の中の多くの人は、よほど楽観的に「自分だけは大丈夫」と思い込んでいるのでしょうか?
よほどポジティブに「自分なら、どんな過ちも、うっかりも、誤解を招くような発言もするはずがない」と信じているのでしょうか?
それとも、それまでは散々他人を叩いておきながら、いざ自分が過ちを犯して他人に叩かれれば、過去の自分の言動など綺麗サッパリ忘れ去って悲劇の主人公になりきるタイプなのでしょうか。
フランス革命の時、王や王妃に振り下ろされたギロチンの刃は、後に革命を起こした側の指導者や市民の首にも振り下ろされました。
革命の熱に酔っていた市民たちは、果たしてその時、予想できていたでしょうか?
その後に始まる恐怖政治と粛清の嵐を……。
歴史上、人が何かに熱狂し、酔いしれると、知らず知らずのうちに地獄を呼び寄せてしまっていることが多い気がします。
どんな“理由”や“大義”があろうと、我を忘れて手段を選ばなくなっては駄目なのです。
それはこれまでの人類史上、何度も何度も繰り返されてきた過ちであり……それでも尚「きちんと学ばれていない」教訓なのです。
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(11/08)
(10/26)
(10/19)
(10/13)
(10/05)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
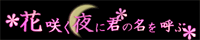
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
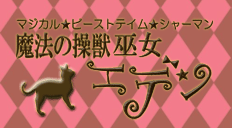
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
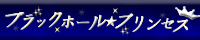
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
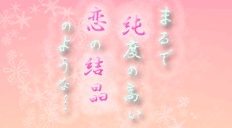
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
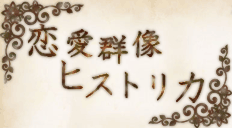
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
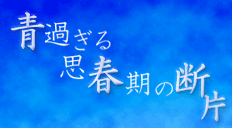
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
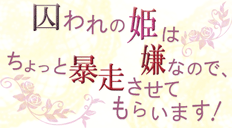
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
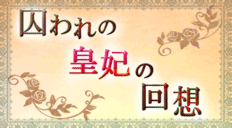
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
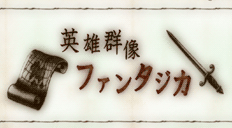
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
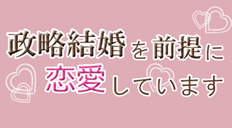
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
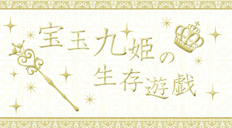
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

