日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
今の時代を見ていて不思議に思うのが「『意見の否定=その人の存在自体の否定』になっていないか?」ということです。
自分にとって「気に食わない意見」を持つ相手のことを、罵倒し、侮辱し、人格否定し、まるでこの世から葬り去ろうとでもするように徹底的に攻撃する…そんなことが、世の中に溢れている気がするのです。
でも「相手の意見を否定すること」と「相手の存在自体を否定すること」は決してイコールではありませんよね?
なぜ、そこを「一緒くた」にし、しかも、そのことに何の疑問も抱かずにいるのか…。
その「なぜ」の「答え」として、ひとつ推測しているのは、「感情に目がくらんで、『意見の否定』と『人格否定』を分けて考えることができなくなっているのではないか」ということです。
相手の意見に「怒り」や「不快」などの「負の感情」が刺激された結果、自分の言動が「意見の否定」という次元を遥かにオーバーし、「人格の否定」にまで至ってしまっていることに気づけない…
あるいは、気づいていても、無意識のうちにそれを「正当化」し、自分の感情を満足させることの方を優先させてしまう…
つまり「自分の言動を冷静に顧みることができない」「自分を律することができていない」ことが原因なのではないかと…。
あるいは、そもそも今の社会の中に「意見を戦わせる上で、相手の人格を攻撃しても構わない」という、誤った共通認識が育まれてしまっているのではないか、と…。
自分と対立する意見の相手は、存在自体を認めないと言うなら、そもそも「議論」そのものが成り立ちません。
それは「議論」ではなく、ただ自分の意見を周りに「押し付ける」ための場でしかありません。
たとえ自分とは反対の意見だったとしても、自分にとって「気に食わない」意見だったとしても、まずは「耳を傾ける」――それが、「議論」というものの「最低限」のルールのはずなのですが…その「最低限」ができていない人が多過ぎる、ということなのでしょうか?
そもそも、なぜそんなにも「自分の意見を通したがる」のか、自分の目からすると、そこからして不可解でなりません。
他人の存在を否定してまで自分の意見を通して――その意見が間違っていた場合、自分も他者も皆まとめて破滅するリスクがあるわけですが(そしてその場合、その破滅に対する「責任」が否応なく発生するわけですが)…そこの所は考えていない、ということなのでしょうか?
議論とはそもそも、多様性のある意見を集めることで、「ひとりの人間の視点」だけでは見出せない問題解決法を導き出すためのものだと思っていたのですが…そう思っていない(自分の意見を通す場とだけ考えている)人間が多いということなのでしょうか?
思えば我々は、義務教育の中できちんとした「議論の方法」を学んではいません。
「学級会」や「ホームルーム」で何かを決める際は、結局「多数決」で終わってしまい、「意見の調整」「意見のすり合わせ」「対立意見の妥協点を見出す」などは一切見られなかったように思います。
それゆえ、大人になってからも、そんな「多数決の勝ち負け」で全てを考えてしまうのでしょうか?
自分の意見が勝てばそれで良いと、そこで思考を止めてしまい、その結果、少数派がどうなるかについては一切思いをめぐらせないのでしょうか?
むしろ、勝者の権利とばかりに、敗者を徹底的に足蹴にしようとするのでしょうか?
推測はあくまで推測でしかありませんので、実際のところは分かりません。
しかし、もし「そう」なのだとしたら…今の世の中の様々な問題、そして「生きづらさ」の根本は、そこにあるのかも知れません。
自分にとって「気に食わない意見」を持つ相手のことを、罵倒し、侮辱し、人格否定し、まるでこの世から葬り去ろうとでもするように徹底的に攻撃する…そんなことが、世の中に溢れている気がするのです。
でも「相手の意見を否定すること」と「相手の存在自体を否定すること」は決してイコールではありませんよね?
なぜ、そこを「一緒くた」にし、しかも、そのことに何の疑問も抱かずにいるのか…。
その「なぜ」の「答え」として、ひとつ推測しているのは、「感情に目がくらんで、『意見の否定』と『人格否定』を分けて考えることができなくなっているのではないか」ということです。
相手の意見に「怒り」や「不快」などの「負の感情」が刺激された結果、自分の言動が「意見の否定」という次元を遥かにオーバーし、「人格の否定」にまで至ってしまっていることに気づけない…
あるいは、気づいていても、無意識のうちにそれを「正当化」し、自分の感情を満足させることの方を優先させてしまう…
つまり「自分の言動を冷静に顧みることができない」「自分を律することができていない」ことが原因なのではないかと…。
あるいは、そもそも今の社会の中に「意見を戦わせる上で、相手の人格を攻撃しても構わない」という、誤った共通認識が育まれてしまっているのではないか、と…。
自分と対立する意見の相手は、存在自体を認めないと言うなら、そもそも「議論」そのものが成り立ちません。
それは「議論」ではなく、ただ自分の意見を周りに「押し付ける」ための場でしかありません。
たとえ自分とは反対の意見だったとしても、自分にとって「気に食わない」意見だったとしても、まずは「耳を傾ける」――それが、「議論」というものの「最低限」のルールのはずなのですが…その「最低限」ができていない人が多過ぎる、ということなのでしょうか?
そもそも、なぜそんなにも「自分の意見を通したがる」のか、自分の目からすると、そこからして不可解でなりません。
他人の存在を否定してまで自分の意見を通して――その意見が間違っていた場合、自分も他者も皆まとめて破滅するリスクがあるわけですが(そしてその場合、その破滅に対する「責任」が否応なく発生するわけですが)…そこの所は考えていない、ということなのでしょうか?
議論とはそもそも、多様性のある意見を集めることで、「ひとりの人間の視点」だけでは見出せない問題解決法を導き出すためのものだと思っていたのですが…そう思っていない(自分の意見を通す場とだけ考えている)人間が多いということなのでしょうか?
思えば我々は、義務教育の中できちんとした「議論の方法」を学んではいません。
「学級会」や「ホームルーム」で何かを決める際は、結局「多数決」で終わってしまい、「意見の調整」「意見のすり合わせ」「対立意見の妥協点を見出す」などは一切見られなかったように思います。
それゆえ、大人になってからも、そんな「多数決の勝ち負け」で全てを考えてしまうのでしょうか?
自分の意見が勝てばそれで良いと、そこで思考を止めてしまい、その結果、少数派がどうなるかについては一切思いをめぐらせないのでしょうか?
むしろ、勝者の権利とばかりに、敗者を徹底的に足蹴にしようとするのでしょうか?
推測はあくまで推測でしかありませんので、実際のところは分かりません。
しかし、もし「そう」なのだとしたら…今の世の中の様々な問題、そして「生きづらさ」の根本は、そこにあるのかも知れません。
PR
就職活動で「自己分析」を経験した方、結構いらっしゃると思います。
自分の長所・短所を見つめ直し、面接で上手くPRできるように、自分自身について分析をするわけですが…
社会人になった今にして思うと、学生時代にやった「自己分析」は、まるで「なっていなかった」と感じます。
「自己分析」という字面からして、「自分自身」だけを分析すれば良いような気がしてしまいますが…
本当の意味で「自分自身を知る」には、「自分を知っている」だけでは駄目なのです。
知らなければならないのは「自分と他人との違い」です。
他人と比べて自分が勝っているものは何か、そして逆に劣っている部分は何なのか…。
そしてそんな「自分と他人との違い」を知るには、過小評価でも過大評価でもない「リアルで正確な他人の姿」を知らなければならないのです。
自己評価をする際、無意識のうちに他人の能力を低く見積もり、「自分はこんなにスゴいんだ」と偉ぶったりはしていませんか?
あるいは逆に、自分が周りと比べてひどく劣っているような気がして、委縮したりはしてしませんか?
他人の姿を色眼鏡無しに真っ直ぐ見つめるということは、そんなに簡単なことではないのです。
そもそも「自分から見える他人の姿」は、その人のほんの一部分――“氷山の一角”でしかありません。
実はとてつもない能力を隠し持っているかも知れませんし、逆に見栄を張って自分を大きく見せようとしているかも知れません。
そんな「目には見えない部分」も考慮した上で、他人と自分との「違い」を見つめていかなければなりません。
正直、非常に難しく、社会人になった今でも、ちゃんとできるかどうか、自信はありません。
しかし、他人を知り、自分を知るということは、就職活動のみならず、人生を生きる上でも非常に役立ちます。
就職活動のためだけのものと思わず、人生のふとした場面で、自己分析してみるのはいかがでしょうか。
自分の長所・短所を見つめ直し、面接で上手くPRできるように、自分自身について分析をするわけですが…
社会人になった今にして思うと、学生時代にやった「自己分析」は、まるで「なっていなかった」と感じます。
「自己分析」という字面からして、「自分自身」だけを分析すれば良いような気がしてしまいますが…
本当の意味で「自分自身を知る」には、「自分を知っている」だけでは駄目なのです。
知らなければならないのは「自分と他人との違い」です。
他人と比べて自分が勝っているものは何か、そして逆に劣っている部分は何なのか…。
そしてそんな「自分と他人との違い」を知るには、過小評価でも過大評価でもない「リアルで正確な他人の姿」を知らなければならないのです。
自己評価をする際、無意識のうちに他人の能力を低く見積もり、「自分はこんなにスゴいんだ」と偉ぶったりはしていませんか?
あるいは逆に、自分が周りと比べてひどく劣っているような気がして、委縮したりはしてしませんか?
他人の姿を色眼鏡無しに真っ直ぐ見つめるということは、そんなに簡単なことではないのです。
そもそも「自分から見える他人の姿」は、その人のほんの一部分――“氷山の一角”でしかありません。
実はとてつもない能力を隠し持っているかも知れませんし、逆に見栄を張って自分を大きく見せようとしているかも知れません。
そんな「目には見えない部分」も考慮した上で、他人と自分との「違い」を見つめていかなければなりません。
正直、非常に難しく、社会人になった今でも、ちゃんとできるかどうか、自信はありません。
しかし、他人を知り、自分を知るということは、就職活動のみならず、人生を生きる上でも非常に役立ちます。
就職活動のためだけのものと思わず、人生のふとした場面で、自己分析してみるのはいかがでしょうか。
社会人になってから気づいたことがあります。
それは、「分からない」には種類がある、ということです。
ひとつは「理解する能力が無い」から生じる「分からない」。
もうひとつは「理解する気が無い(理解する気が起きない)」から生じる「分からない」です。
どんな人でも分かるようにと、どんなに取扱説明書を分かりやすく工夫しようと、「分からない」人は「分からない」と言ってきます。
それなのに、こちらが取説をそのまま読み上げ、その通りに操作してもらうと、あっさり「出来て」しまったりするのです。
そんなことが何度かあり、思ったのが、「これは『理解できない』わけではなく、取説を取り出したり、その中から必要な操作を書いたページを探し出したり、そこに書いてある内容を理解するのが『面倒くさい』だけなのだろう」ということでした。
自分で説明書を読み込んで理解するより、他人に訊いてそのままやった方が「簡単」で「面倒くさくない」から、あえて「分からない」ままでいる…
世の中にはたぶん、そういう人々が存在するのです。
きっとこれは、機械の操作や業務の進め方に限らないことだと思われます。
世の中に溢れる様々な“問題”や“課題”――難しくて理解できない、という人のうち、「理解する能力が無い」から分からない人は、一体どれだけいるのでしょう。
きっと中には、理解する能力があっても、理解する気が無いから「分からない」、理解するのが面倒くさいから「分からない」という人間が相当数いるはずです。
人はそもそも、興味を持っていない分野のことは理解したがらないものです。
人生は有限で、処理しなければならない情報・問題は膨大にあります。
そんな中で、特に興味の無いことに頭を割いている余裕は無いのかも知れません。
しかし、そんな「本当は分かるはずなのに」あえて「分からない」ままにしていることが、時に誰かを苦しめたり、誰かに余計な負担を負わせたりしているのではないか…そんな風にも思うのです。
「愛の反対は、憎しみではなく無関心」という言葉があります。
本当は理解できるはずなのに、わざと理解しないでいる、そんな「分からない」も、「愛の反対」なのかも知れない――そんなことを、自戒も込めて考えてみる今日この頃です。
それは、「分からない」には種類がある、ということです。
ひとつは「理解する能力が無い」から生じる「分からない」。
もうひとつは「理解する気が無い(理解する気が起きない)」から生じる「分からない」です。
どんな人でも分かるようにと、どんなに取扱説明書を分かりやすく工夫しようと、「分からない」人は「分からない」と言ってきます。
それなのに、こちらが取説をそのまま読み上げ、その通りに操作してもらうと、あっさり「出来て」しまったりするのです。
そんなことが何度かあり、思ったのが、「これは『理解できない』わけではなく、取説を取り出したり、その中から必要な操作を書いたページを探し出したり、そこに書いてある内容を理解するのが『面倒くさい』だけなのだろう」ということでした。
自分で説明書を読み込んで理解するより、他人に訊いてそのままやった方が「簡単」で「面倒くさくない」から、あえて「分からない」ままでいる…
世の中にはたぶん、そういう人々が存在するのです。
きっとこれは、機械の操作や業務の進め方に限らないことだと思われます。
世の中に溢れる様々な“問題”や“課題”――難しくて理解できない、という人のうち、「理解する能力が無い」から分からない人は、一体どれだけいるのでしょう。
きっと中には、理解する能力があっても、理解する気が無いから「分からない」、理解するのが面倒くさいから「分からない」という人間が相当数いるはずです。
人はそもそも、興味を持っていない分野のことは理解したがらないものです。
人生は有限で、処理しなければならない情報・問題は膨大にあります。
そんな中で、特に興味の無いことに頭を割いている余裕は無いのかも知れません。
しかし、そんな「本当は分かるはずなのに」あえて「分からない」ままにしていることが、時に誰かを苦しめたり、誰かに余計な負担を負わせたりしているのではないか…そんな風にも思うのです。
「愛の反対は、憎しみではなく無関心」という言葉があります。
本当は理解できるはずなのに、わざと理解しないでいる、そんな「分からない」も、「愛の反対」なのかも知れない――そんなことを、自戒も込めて考えてみる今日この頃です。
皆さん、テストの点数を獲るのに必要なのは「学力」や「知識」だけだと思っていませんか?
しかし、テストに臨む人の何割かには、学力や知識以前の問題で点数を何点かロスしている、非常に「もったいない」人が多々いるのです。
以下は、その「もったいない」失点と、その対策のまとめです。
テストの点数が低くて悩んでいる方は「今すぐにできる対策」として、既にそれなりの実力者の方は「ケアレスミス防止策」として、参考までにご覧になってみてください。
(基本中の基本と思われてしまうようなものばかりかも知れませんが、実際これができていない方は相当数いらっしゃいますし、人生には「その1点が人生を分ける」という場面もありますので、とても大事なことなのです。)
しかし、テストに臨む人の何割かには、学力や知識以前の問題で点数を何点かロスしている、非常に「もったいない」人が多々いるのです。
以下は、その「もったいない」失点と、その対策のまとめです。
テストの点数が低くて悩んでいる方は「今すぐにできる対策」として、既にそれなりの実力者の方は「ケアレスミス防止策」として、参考までにご覧になってみてください。
(基本中の基本と思われてしまうようなものばかりかも知れませんが、実際これができていない方は相当数いらっしゃいますし、人生には「その1点が人生を分ける」という場面もありますので、とても大事なことなのです。)
- 漢字の間違いが無いかチェックしよう
- 頭の中で出した答えが合っていても、解答用紙に書いた答えの「漢字」が間違っていたら、とても「もったいない」ことになります。
「漢字のミスをどの程度見るか」は答案を採点する人によって違いますし、「ちょっと間違っている」くらいなら許されるミスも、「全く違う漢字を書いてしまっている」場合には×にされてしまうでしょう。
たとえば「菅原道真」と「管原道真」を間違える、「努力」と「怒力」を間違えるetc…
「そんなミスするわけない」と思う方もいるかも知れませんが、テストの時というものは、精神が何かとテンパりがちです。
いつもならしないような書き間違いも、うっかりしてしまうことがあります。
なので「解けた!」で安心してしまわずに、自分の書いた答えをチラッとだけでも見直すクセをつけておくと良いでしょう。
それと、こういった漢字間違いの中の何割かには「元々漢字を間違って覚えている」「うろ覚えなので、いざとなると正しいものが書けない」という方がいらっしゃいます。
テスト勉強の際には「ことば」を覚えるだけでなく、漢字もしっかり見て覚えておいた方が良いでしょう。
- クセ字や読みづらい字がないか、普段から気にしよう
- 数字や英字には、ちょっとした違いで別の字に見えてしまうものが多く存在します。
1と7、0と6、3と8、DとO、DとP、HとM、等々…
1と7は、上のチョンと曲がっている部分の長さひとつで、どちらにでも見えたりしますし、6は上のくるんとした部分が短過ぎれば0に見えます。
3と8は、字が小さすぎたり、濃く太い線で書かれてつぶれて見えたりすると、どちらなのか分かりません。
漢字も、由と田、夫と天など、突き抜けているか突き抜けていないかで全く別の字になってしまうものが結構あります。
正しい答えを書いても、それを採点者に正しく読んでもらえなかったら意味がありません。
こういう字のクセは、テストの時だからと言って急に直るようなものではありませんので、普段から「自分の字は他の人に別の字と読み間違えられたりしないだろうか」と気にして、別の字に読まれそうだったら直すように意識した方が良いでしょう。
こういう「読み間違えられやすいクセ字」は、テストのみならず、社会に出てからも問題になってくる可能性があります。
(数字の読み間違いなどで発注数を間違えられでもしたら、シャレになりません。)
なるべく早いうちに気づいて矯正しておく方が、後々必ず自分のためになります。
- 解答の仕方を間違えていないか気をつけよう
- テストの中には「設問Aと設問Bのうち、どちらか1つだけを選んで答えれば良い」という「選択問題」があったりします。
こういったテストの答え方を間違えて、やらなくても良いのに両方の問題を解いて、時間をロスしている「もったいない」方がたまにいます。
また、答えなくてはいけない問題を答えずに、その部分をまるまる失点してしまっている方もいます。
これは、落ち着いて問題文をよく読めば起こらないミスです。
なので、テストを解く際には焦らずに、問題文をちゃんと読むクセをつけた方が良いでしょう。
- 解答欄を間違えていないかチェックしよう
- 頭の中で考えた「答え」は合っているのに、解答欄が1つずつズレているため×にされる…
コメディではよくあるテンプレなミスですが、これ、実際やる人が必ず何人かいるのです。
上の方にも書きましたが、テストの最中は精神状態が普通でないことが多々あります。
普段なら絶対やらないようなミスもうっかりしてしまうのが、テストなのです。
そして、解答欄を全て埋められるような人ならともかく、間に空欄ができてしまうような方は、その辺りから解答がズレていってしまうことが、よくあります。
これも、一度自分の書いた答えをチェックするクセをつけておけば防げるミスですので、気をつけてみると良いでしょう。
学生時代、自分の成績には、かなりのムラがありました。
理数系はダメダメでしたが、得意な国語は学年1位の常連でした。
そしてその国語に関して言えば、塾などには一切通ったことがなく、特別な「勉強」をした記憶もありません。
それでも国語の成績が異常に良かったのは…自分にとって国語の知識を高めることが、「勉強」ではなく「日常の一部」だったせいかと思われます。
自分は物心ついた時から活字中毒で、小学生の頃から図書館の本を読み尽くす勢いで本を読み漁っていました。
さらには自分で物語を作るのも好きで、そんな物語の糧とすべく、せっせと語彙や知識を吸収しまくっていました。
高校の入学時に伯父にリクエストした入学祝いは「広辞苑」で、高校時代は暇があれば適当に開いたページを「読んで」遊んでいました。
国語の教科書は自分にとっては「教科書」ではなく、詩や短編など様々な文学を集めた「アンソロジー」でした。
授業が始まる前から教科書を読み込み、結局授業では習わずに終わった部分さえしっかり内容を把握していました。
(さらに言えば、自分の代の教科書だけでなく、兄弟の使っていた教科書にまで手を出していたので、他の世代の国語の教科書の内容も知っていたりします…。)
つまり…自分にとって国語を学ぶことは、苦痛な「勉強」ではなく、「楽しみ」や「趣味」だったのです。
「好きこそものの上手なれ」ということわざがあるように、人間誰しも、好きなことに関してはビックリするようなパフォーマンスを発揮するものです。
逆に、苦手意識を持ち「嫌だなぁ」と思っているものに対しては、思うように能力を発揮できないのではないでしょうか。
学校には、各教科を「嫌」で「苦手」なものに変えてしまう「罠」がたくさん存在します。
知識を暗記するばかりで、おもしろみの全く無いテスト対策…
周りの友達の「勉強なんてつまらないよな」という同調圧力…
学年が上がるにつれ増す難易度、教科書から減っていくイラストや図解…
その罠にはまらず、勉強を勉強と思わずに楽しむことができるなら、学力を上げることはそれほど難しくないと思います。
授業や受験対策、テスト勉強などはひとまず置いておいて、まずは各教科で自分が興味を持てそうな「要素」を見つけることです。
日本史の人物の中におかしな名前を見つけて喜ぶことから始めたって良いと思います。
和英辞典を使ってカッコイイ必殺技名を考え出すことから始めたって良いと思います。
大切なのは、まずは興味を持ち、知識を深める「きっかけ」を持つこと。
そして勉強を勉強と思わず、ちょっと変わった趣味のひとつにしてしまうことです。
…ただ、こういう“遊びから始める学力の深め方”は、それなりに長期戦となりますので、なるべく早い段階で始めておいた方が良いです。
あと、遊びから学んだ知識だと、受験と全く関係ない部分を異常に深く掘り下げてしまう場合もあります…。
(それはそれで、受験の役には立たなくても、後で人生の役に立つ場合があるので良いのですが…。)
理数系はダメダメでしたが、得意な国語は学年1位の常連でした。
そしてその国語に関して言えば、塾などには一切通ったことがなく、特別な「勉強」をした記憶もありません。
それでも国語の成績が異常に良かったのは…自分にとって国語の知識を高めることが、「勉強」ではなく「日常の一部」だったせいかと思われます。
自分は物心ついた時から活字中毒で、小学生の頃から図書館の本を読み尽くす勢いで本を読み漁っていました。
さらには自分で物語を作るのも好きで、そんな物語の糧とすべく、せっせと語彙や知識を吸収しまくっていました。
高校の入学時に伯父にリクエストした入学祝いは「広辞苑」で、高校時代は暇があれば適当に開いたページを「読んで」遊んでいました。
国語の教科書は自分にとっては「教科書」ではなく、詩や短編など様々な文学を集めた「アンソロジー」でした。
授業が始まる前から教科書を読み込み、結局授業では習わずに終わった部分さえしっかり内容を把握していました。
(さらに言えば、自分の代の教科書だけでなく、兄弟の使っていた教科書にまで手を出していたので、他の世代の国語の教科書の内容も知っていたりします…。)
つまり…自分にとって国語を学ぶことは、苦痛な「勉強」ではなく、「楽しみ」や「趣味」だったのです。
「好きこそものの上手なれ」ということわざがあるように、人間誰しも、好きなことに関してはビックリするようなパフォーマンスを発揮するものです。
逆に、苦手意識を持ち「嫌だなぁ」と思っているものに対しては、思うように能力を発揮できないのではないでしょうか。
学校には、各教科を「嫌」で「苦手」なものに変えてしまう「罠」がたくさん存在します。
知識を暗記するばかりで、おもしろみの全く無いテスト対策…
周りの友達の「勉強なんてつまらないよな」という同調圧力…
学年が上がるにつれ増す難易度、教科書から減っていくイラストや図解…
その罠にはまらず、勉強を勉強と思わずに楽しむことができるなら、学力を上げることはそれほど難しくないと思います。
授業や受験対策、テスト勉強などはひとまず置いておいて、まずは各教科で自分が興味を持てそうな「要素」を見つけることです。
日本史の人物の中におかしな名前を見つけて喜ぶことから始めたって良いと思います。
和英辞典を使ってカッコイイ必殺技名を考え出すことから始めたって良いと思います。
大切なのは、まずは興味を持ち、知識を深める「きっかけ」を持つこと。
そして勉強を勉強と思わず、ちょっと変わった趣味のひとつにしてしまうことです。
…ただ、こういう“遊びから始める学力の深め方”は、それなりに長期戦となりますので、なるべく早い段階で始めておいた方が良いです。
あと、遊びから学んだ知識だと、受験と全く関係ない部分を異常に深く掘り下げてしまう場合もあります…。
(それはそれで、受験の役には立たなくても、後で人生の役に立つ場合があるので良いのですが…。)
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(10/26)
(10/19)
(10/13)
(10/05)
(09/28)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
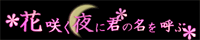
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
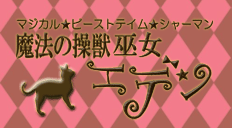
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
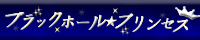
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
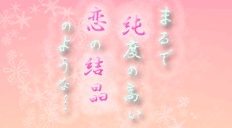
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
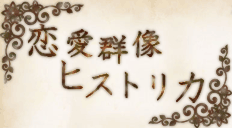
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
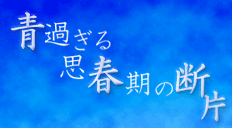
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
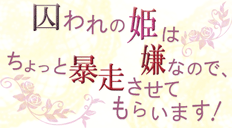
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
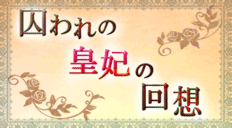
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
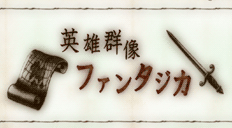
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
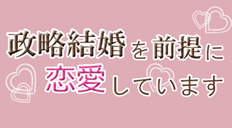
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
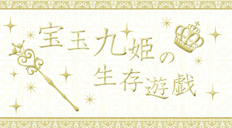
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

