日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
群馬県高崎市の於菊稲荷神社(おきくいなりじんじゃ)へ行って来ました。

以前、芸能人が中山道をリレー形式で歩いていく番組で取り上げられていて、ずっと気になっていたので。
小規模ながら朱色の鳥居がずらーっと並んでいるところも印象的だったのですが、御朱印が狐のスタンプの上に重なるように記された神社の名が狐の尾の形になっていて、とても珍しく素敵だったので。
(ネットで調べてみると、それ以外にも複数種類の御朱印があり、季節限定のものや、ひな祭り・端午の節句などイベント限定の御朱印もありました。限定の御朱印の時には結構人が並ぶようです。)
あと、夏休みがちょうどお盆時期と重なってしまい(ウチの会社の夏休みはローテーションなので、ちょうどお盆に当たるとは限りません。)、どこへ行っても混んでいそうなので穴場で、あまり人がいなさそうな所にちょろっと出掛けたい、というのがあって…。
あと、群馬は祖母の実家があって、小学生の頃は毎年お彼岸のたびに行っていたくらい馴染みのある場所なので。
(もっとも親戚の家メインだったので、あまり観光スポットには行っていないのですが。世界遺産の富岡製糸場にも行ったことがないくらいです。)
まぁ、それだけだと夏休みの目的地としては少し寂しいのですが、この神社の最寄駅である新町にはもう一つ目玉があります。
それは「ガトーフェスタ ハラダ」。
東京のデパ地下にも出店している、ラスクで有名な洋菓子店さんですが、新町には普通の販売店(於菊稲荷神社のそば)の他、まるで宮殿のような立派な工場(新町駅から徒歩15分)もあり、工場見学もできるのです。
(工場見学目当ての観光バスも来るらしいです。ちなみに工場見学は元日を除く平日のみで、10~17時。料金は無料。10名以上は要予約だそうです。工場見学するとラスクが1枚タダでいただけます。)
自分は群馬に親戚がいるので、よくここのラスクをお土産にもらっていましたが、実はラスクだけでなく、ケーキなどの生菓子や期間限定のゼリー(コーヒーゼリーとティーゼリー)、サブレ等の他の焼菓子も売っています。
ラスクも定番のプレーン(バターの風味のラスクに砂糖がまぶしてあるもの)だけでなく、間にラムレーズン入りホワイト・チョコクリームをはさんだものや、チョコレートでコーティングしてあるものなど、様々な種類があります。
…と言うわけで、於菊稲荷神社とガトーフェスタハラダ目当てで新町駅に降り立ったのですが…
親戚の家のイメージから何となく田舎なイメージがしていた新町でしたが、意外と建物や建造物が立派です。
と言うか、昭和レトロだったりオシャレだったり面白いセンスの建造物が多い気がします。
駅前ロータリーもライオンの噴水があったりなどして立派なのですが、自分が心惹かれたのは歩道橋です。
新町駅は改札が1つしかないのですが、駅の反対側へ渡るための歩道橋は、踊り場の真下にあたる部分に時計がついていたり、歩道の真ん中や突き当りに花壇があって、緑の歩道と花壇のカラフルな花との対比がとても綺麗で癒されました。


あと、改札から真っ直ぐ行った交差点にある歩道橋も、何だか未来的でカッコイイです。

自分は特に歩道橋マニアでも何でもないのですが、無駄に写真を撮りまくってしまいました。
於菊稲荷神社へは駅から徒歩で約10分ほどです。
(行き方はサイトの方に「於菊稲荷神社への行き方(アクセスマップ)」としてまとめてあります。)
この神社には珍しいペット用のお守りがあることは事前にネットで調べて知っていたのですが、絵馬もペットの形(犬の顔の形)をしたものがありました。
垂れ耳の耳の部分にだけ色がついていて、目や鼻、口などは自分で描き込むようになっているのですが、様々な顔のワンコの絵馬がずらっと並んでいて微笑ましく、ほっこりします。
境内には本殿の他、雷電神社の小さな祠があったり、小さなお狐様の人形がずらっと並ぶ白狐社があります。
御朱印は、自分が行った時には5種類ほどあって悩みましたが、結局テレビで最初に見た御朱印をいただきました。
それと我が家の愛猫用にペット守(交通安全・健康長寿)を購入。
青と赤の2種類あって、首輪に取り付けられるようになっています。

以前、芸能人が中山道をリレー形式で歩いていく番組で取り上げられていて、ずっと気になっていたので。
小規模ながら朱色の鳥居がずらーっと並んでいるところも印象的だったのですが、御朱印が狐のスタンプの上に重なるように記された神社の名が狐の尾の形になっていて、とても珍しく素敵だったので。
(ネットで調べてみると、それ以外にも複数種類の御朱印があり、季節限定のものや、ひな祭り・端午の節句などイベント限定の御朱印もありました。限定の御朱印の時には結構人が並ぶようです。)
あと、夏休みがちょうどお盆時期と重なってしまい(ウチの会社の夏休みはローテーションなので、ちょうどお盆に当たるとは限りません。)、どこへ行っても混んでいそうなので穴場で、あまり人がいなさそうな所にちょろっと出掛けたい、というのがあって…。
あと、群馬は祖母の実家があって、小学生の頃は毎年お彼岸のたびに行っていたくらい馴染みのある場所なので。
(もっとも親戚の家メインだったので、あまり観光スポットには行っていないのですが。世界遺産の富岡製糸場にも行ったことがないくらいです。)
まぁ、それだけだと夏休みの目的地としては少し寂しいのですが、この神社の最寄駅である新町にはもう一つ目玉があります。
それは「ガトーフェスタ ハラダ」。
東京のデパ地下にも出店している、ラスクで有名な洋菓子店さんですが、新町には普通の販売店(於菊稲荷神社のそば)の他、まるで宮殿のような立派な工場(新町駅から徒歩15分)もあり、工場見学もできるのです。
(工場見学目当ての観光バスも来るらしいです。ちなみに工場見学は元日を除く平日のみで、10~17時。料金は無料。10名以上は要予約だそうです。工場見学するとラスクが1枚タダでいただけます。)
自分は群馬に親戚がいるので、よくここのラスクをお土産にもらっていましたが、実はラスクだけでなく、ケーキなどの生菓子や期間限定のゼリー(コーヒーゼリーとティーゼリー)、サブレ等の他の焼菓子も売っています。
ラスクも定番のプレーン(バターの風味のラスクに砂糖がまぶしてあるもの)だけでなく、間にラムレーズン入りホワイト・チョコクリームをはさんだものや、チョコレートでコーティングしてあるものなど、様々な種類があります。
…と言うわけで、於菊稲荷神社とガトーフェスタハラダ目当てで新町駅に降り立ったのですが…
親戚の家のイメージから何となく田舎なイメージがしていた新町でしたが、意外と建物や建造物が立派です。
と言うか、昭和レトロだったりオシャレだったり面白いセンスの建造物が多い気がします。
駅前ロータリーもライオンの噴水があったりなどして立派なのですが、自分が心惹かれたのは歩道橋です。
新町駅は改札が1つしかないのですが、駅の反対側へ渡るための歩道橋は、踊り場の真下にあたる部分に時計がついていたり、歩道の真ん中や突き当りに花壇があって、緑の歩道と花壇のカラフルな花との対比がとても綺麗で癒されました。
あと、改札から真っ直ぐ行った交差点にある歩道橋も、何だか未来的でカッコイイです。
自分は特に歩道橋マニアでも何でもないのですが、無駄に写真を撮りまくってしまいました。
於菊稲荷神社へは駅から徒歩で約10分ほどです。
(行き方はサイトの方に「於菊稲荷神社への行き方(アクセスマップ)」としてまとめてあります。)
この神社には珍しいペット用のお守りがあることは事前にネットで調べて知っていたのですが、絵馬もペットの形(犬の顔の形)をしたものがありました。
垂れ耳の耳の部分にだけ色がついていて、目や鼻、口などは自分で描き込むようになっているのですが、様々な顔のワンコの絵馬がずらっと並んでいて微笑ましく、ほっこりします。
境内には本殿の他、雷電神社の小さな祠があったり、小さなお狐様の人形がずらっと並ぶ白狐社があります。
御朱印は、自分が行った時には5種類ほどあって悩みましたが、結局テレビで最初に見た御朱印をいただきました。
それと我が家の愛猫用にペット守(交通安全・健康長寿)を購入。
青と赤の2種類あって、首輪に取り付けられるようになっています。
VOICEROIDナレーション付の「於菊稲荷神社へ行って来ました」動画です。
↓
PR
まだ小学校にも上がらないくらいの幼児時代、流れるプールに沈みかけたことがあります。
それは町内会の「こども会」で連れて行ってもらったプールでのことでした。
たぶん、大勢の子どもに対し、引率する大人の人数が少なかったか何かで、自分と、もう一人の幼なじみの男の子だけ、他の皆と離れてふたりきりになった時間帯がありました。
経緯はさすがに忘れましたが、最初は子ども用の浅いプールにいたはずが、いつの間にか自分たちは流れるプールのそばにいて、しかも自分はそのうちに一人で、浮き輪も無しに流れるプールの中に入って行ってしまったのです。
当然足がつくわけもなく、自分はすぐに危険に気づき、必死にプールの縁にしがみついていました。
幼心にも「今、手を離したら死ぬ」という思いが頭を過りました。
その後のことは正直あまり記憶に無いのですが、自分が今こうして生きていることを考えれば、たぶん誰か大人の人が気づいて引き上げてくれたのでしょう。
自分にとっては強烈に脳に刻みつけられた記憶なのですが、親たちに聞いても知らないと言われます。
でも、その命の危機に関する部分だけでなく、初めてのコインロッカーの使い方が分からず(←たぶん誰も教えてくれなかったか、その時も近くに引率の大人がいなかった)、周りの人の見よう見まねでコインを入れたまでは良かったものの、カギを引き抜かずにそのままにしてしまったため、後でロッカーの場所が分からなくなって、ちょっとした騒動になったという細かいエピソードまで覚えていますので、少なくとも夢や妄想ということではなかったと思います。
(ひょっとすると、自分が溺れかけたということ自体、自分も含め誰も親に話さなかったのかも知れません。)
この時のことを思い出すたびに思うことが「子どもの判断力・思考力は大人のソレとは全く違う」という事実です。
大人からすると「何で足がつくはずもない大人用のプールに入って行くんだ?」と思うことでしょう。
でも、まだ保育園児で、今まで保育園の浅いプールか家庭用のビニールプールにしか入ったことがなく、大人用の深いプールですら初めて見る自分に、プールの深さに対する警戒心はありませんでした。
その時の自分に見えていたのは、流れるプールの中で楽しそうにはしゃぐ人たちの姿だけ。
何の危機感も抱かず楽しそうに笑う彼らの姿から「このプールには何の危険も無い」「このプールは楽しいところだ」「自分が入っても大丈夫だ」という、間違った推論を導いてしまったのです。
中には「頭のデキの悪い子だったから、そんなことしたんだろう」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、後に(高校生時点で)塾にも通わず特別な勉強もせず通常運行で国語の偏差値80を叩きだすことになる自分でさえ、この体たらくなのです。
子どもの判断力・思考力を甘く見てはいけません。
(まぁ、自分の場合は“天然”という要素が、多少の頭の良さ程度は台無しにしてしまっている可能性がなきにしもあらずではあるのですが……。)
そもそも判断力や思考力というものは、その元となる知識や記憶があって初めて真っ当な答えを導き出せるものです。
子どもは生きてきた年数が少ない分、その知識や記憶が大人に比べて圧倒的に足りていません。
そんな子どもに対し「大人と同じ判断をせよ」ということ自体、実はとてつもなく無茶で無謀なことなのです。
たとえば、火にかかったヤカンに無防備に触れてヤケドをする子どもがいます。
大人は「なんでそんな熱いものに素手で触るの!」「ヤケドをするに決まってるでしょ!」と怒るかも知れません。
でも、ひょっとするとその子には「火にかかったヤカンは熱いものだ」「熱いものに触るとヤケドをするのだ」という知識自体が、まだ無いのかも知れません。
そして、沸騰してピーピー音を鳴らすヤカンや、そこから噴き出す白い湯気が不思議で、面白くて、つい触ってみたくなってしまったのかも知れません。
多くの大人は忘れてしまっているのかも知れませんが、人間誰しも、最初は知らないことだらけです。
大人なら当然知っている危険なアレコレについても、子どもは知りません。
中には本能的に察知して危険を回避できるタイプの子もいるのかも分かりませんが、そんな子どもが全体の何%くらいを占めているのかなど、たぶん誰も知りませんので、そこはあまり期待しない方が良いでしょう。
今の世の中、周囲を見渡すと「子どもは知識が少ないから、判断力も低い」というその事実を把握できていないまま、子どもに無理な「正解」を求め、無闇に叱る大人が多いように見受けられます。
叱るだけでは子どもの判断力は伸びません。
たぶん、判断力の元となる“知識”を、ちゃんと、子どもにも分かりやすい言葉で教えてあげなければいけないのです。
子どもだけでなく、大人についても言えることですが、人間の判断力・思考力の源となる知識・記憶は個人個人で違っています。
だからどんなに自分が「ここではこういう風に判断するに決まってる」と思っていても、別の誰かはその場面で、思いもよらない判断をすることがあります。
それは持っている知識・記憶が一人一人違っている以上、ある意味仕方のないことなのです。
なので、世の中、自分の判断力・思考力だけを基準にして他人の行動――特に子どもの行動を予測するものではありません。
「他人(子ども)は時に思いもよらない行動を起こすものだ」ということを、常に頭の隅に置いておけば、ある程度のリスクは回避できるのではないでしょうか。
遊んでいる時の事故で死ぬ子どものことを、一部の特殊な事例、滅多に起こらないこと、あるいは単に運が悪かった、などと捉えている大人の方はまだまだ多いかも知れません。
でも、たぶんそれは、知識が無いがゆえのちょっとした判断ミス、経験が無いがゆえに危険を甘く見てしまうことなどにより、簡単に起きてしまう、どんな子にも起こり得る事例なのです。
そのことをちゃんと踏まえて、あらかじめ子どもたちに、ちゃんとそういった危険についての知識を分かりやすく教えることができるなら、もっと事故は減らせるのかも知れません。
ただ、その“分かりやすく”“子どもの頭にしっかりと刻まれるような形で”教えるということ自体、なかなかに難易度の高いことなのかも知れませんが……。
それは町内会の「こども会」で連れて行ってもらったプールでのことでした。
たぶん、大勢の子どもに対し、引率する大人の人数が少なかったか何かで、自分と、もう一人の幼なじみの男の子だけ、他の皆と離れてふたりきりになった時間帯がありました。
経緯はさすがに忘れましたが、最初は子ども用の浅いプールにいたはずが、いつの間にか自分たちは流れるプールのそばにいて、しかも自分はそのうちに一人で、浮き輪も無しに流れるプールの中に入って行ってしまったのです。
当然足がつくわけもなく、自分はすぐに危険に気づき、必死にプールの縁にしがみついていました。
幼心にも「今、手を離したら死ぬ」という思いが頭を過りました。
その後のことは正直あまり記憶に無いのですが、自分が今こうして生きていることを考えれば、たぶん誰か大人の人が気づいて引き上げてくれたのでしょう。
自分にとっては強烈に脳に刻みつけられた記憶なのですが、親たちに聞いても知らないと言われます。
でも、その命の危機に関する部分だけでなく、初めてのコインロッカーの使い方が分からず(←たぶん誰も教えてくれなかったか、その時も近くに引率の大人がいなかった)、周りの人の見よう見まねでコインを入れたまでは良かったものの、カギを引き抜かずにそのままにしてしまったため、後でロッカーの場所が分からなくなって、ちょっとした騒動になったという細かいエピソードまで覚えていますので、少なくとも夢や妄想ということではなかったと思います。
(ひょっとすると、自分が溺れかけたということ自体、自分も含め誰も親に話さなかったのかも知れません。)
この時のことを思い出すたびに思うことが「子どもの判断力・思考力は大人のソレとは全く違う」という事実です。
大人からすると「何で足がつくはずもない大人用のプールに入って行くんだ?」と思うことでしょう。
でも、まだ保育園児で、今まで保育園の浅いプールか家庭用のビニールプールにしか入ったことがなく、大人用の深いプールですら初めて見る自分に、プールの深さに対する警戒心はありませんでした。
その時の自分に見えていたのは、流れるプールの中で楽しそうにはしゃぐ人たちの姿だけ。
何の危機感も抱かず楽しそうに笑う彼らの姿から「このプールには何の危険も無い」「このプールは楽しいところだ」「自分が入っても大丈夫だ」という、間違った推論を導いてしまったのです。
中には「頭のデキの悪い子だったから、そんなことしたんだろう」と思われる方もいらっしゃるかも知れませんが、後に(高校生時点で)塾にも通わず特別な勉強もせず通常運行で国語の偏差値80を叩きだすことになる自分でさえ、この体たらくなのです。
子どもの判断力・思考力を甘く見てはいけません。
(まぁ、自分の場合は“天然”という要素が、多少の頭の良さ程度は台無しにしてしまっている可能性がなきにしもあらずではあるのですが……。)
そもそも判断力や思考力というものは、その元となる知識や記憶があって初めて真っ当な答えを導き出せるものです。
子どもは生きてきた年数が少ない分、その知識や記憶が大人に比べて圧倒的に足りていません。
そんな子どもに対し「大人と同じ判断をせよ」ということ自体、実はとてつもなく無茶で無謀なことなのです。
たとえば、火にかかったヤカンに無防備に触れてヤケドをする子どもがいます。
大人は「なんでそんな熱いものに素手で触るの!」「ヤケドをするに決まってるでしょ!」と怒るかも知れません。
でも、ひょっとするとその子には「火にかかったヤカンは熱いものだ」「熱いものに触るとヤケドをするのだ」という知識自体が、まだ無いのかも知れません。
そして、沸騰してピーピー音を鳴らすヤカンや、そこから噴き出す白い湯気が不思議で、面白くて、つい触ってみたくなってしまったのかも知れません。
多くの大人は忘れてしまっているのかも知れませんが、人間誰しも、最初は知らないことだらけです。
大人なら当然知っている危険なアレコレについても、子どもは知りません。
中には本能的に察知して危険を回避できるタイプの子もいるのかも分かりませんが、そんな子どもが全体の何%くらいを占めているのかなど、たぶん誰も知りませんので、そこはあまり期待しない方が良いでしょう。
今の世の中、周囲を見渡すと「子どもは知識が少ないから、判断力も低い」というその事実を把握できていないまま、子どもに無理な「正解」を求め、無闇に叱る大人が多いように見受けられます。
叱るだけでは子どもの判断力は伸びません。
たぶん、判断力の元となる“知識”を、ちゃんと、子どもにも分かりやすい言葉で教えてあげなければいけないのです。
子どもだけでなく、大人についても言えることですが、人間の判断力・思考力の源となる知識・記憶は個人個人で違っています。
だからどんなに自分が「ここではこういう風に判断するに決まってる」と思っていても、別の誰かはその場面で、思いもよらない判断をすることがあります。
それは持っている知識・記憶が一人一人違っている以上、ある意味仕方のないことなのです。
なので、世の中、自分の判断力・思考力だけを基準にして他人の行動――特に子どもの行動を予測するものではありません。
「他人(子ども)は時に思いもよらない行動を起こすものだ」ということを、常に頭の隅に置いておけば、ある程度のリスクは回避できるのではないでしょうか。
遊んでいる時の事故で死ぬ子どものことを、一部の特殊な事例、滅多に起こらないこと、あるいは単に運が悪かった、などと捉えている大人の方はまだまだ多いかも知れません。
でも、たぶんそれは、知識が無いがゆえのちょっとした判断ミス、経験が無いがゆえに危険を甘く見てしまうことなどにより、簡単に起きてしまう、どんな子にも起こり得る事例なのです。
そのことをちゃんと踏まえて、あらかじめ子どもたちに、ちゃんとそういった危険についての知識を分かりやすく教えることができるなら、もっと事故は減らせるのかも知れません。
ただ、その“分かりやすく”“子どもの頭にしっかりと刻まれるような形で”教えるということ自体、なかなかに難易度の高いことなのかも知れませんが……。
小学生の頃、自転車に乗っていて、踏切の中に取り残されたことがあります。
「踏切を横断する時は直前で一時停止し、向こう側に車1台分の空きスペースができてから横断する」という、自動車教習でなら必ず習う交通ルールを、当時知るべくもなかった小学生の自分は、空きスペースも何も考えず、前の自転車に続いてすぐ踏切に進入してしまったため、踏切の信号音が鳴りだしても、混雑していた道で前にも後ろにも進むことができず、遮断機の間に閉じ込められてしまったのでした。
自分はその時、まずは後ろ側に下がろうとしました。
(たぶん、後ろ側の遮断機の方が近かったのだと思います。)
しかし、そこには小学生くらいの知らない子たちが、自転車で集団になって固まっていて、こちらが明らかに踏切に閉じ込められかけて必死に後ろに下がろうとしているのに、道を開けたり下がろうとしてくれるどころか、一切動いてくれませんでした。
そうこうしているうちにも遮断機はどんどん降りていき…
自分は後ろの自転車集団の子たちの態度から「これは行けそうもない」と判断すると、前の遮断機へ目を向けました。
遮断機の“向こう側”は普通に車が流れていますので、さっきまでは前方を塞いでいた自転車も、いつの間にかいなくなってスペースが空いていました。
なので自分はとっさに自分の自転車をナナメに倒し、遮断機の下を潜り抜けて踏切の向こう側へ脱出しました。
忘れもしない、自分が幼少期に生命の危険をほんのり感じた幾つかの出来事のうちの一つです。
この経験を経て、身に染みて感じたことが一つあります。
それは「自分が生命の危機に瀕して助けを求めても、その時その場にいる人間に“人を助ける能力と意思”があるとは限らない」という事実です。
実際、自分が踏切に閉じ込められたあの時、助けてくれようとする人も、声をかけてくれる人もいませんでした。
遮断機の後ろにいた小学生の集団は、こちらが必死に下がろうとしているにも関わらず、動いてすらくれませんでした。
もっとも、あの時、自分もパニックになっていて、ただ無言で必死に自転車を後ろに下げようとしていただけなので、「どいて!」の一言でも言えていれば何かが違ったのかも知れません。
ただ、その言葉を発していたとしても、あの時のあの小学生集団に、あの混雑した道で、“声をかけあって一人一人が少しずつ後ろに下がっていき、自転車1台分のスペースを何とか空ける”ということが可能だったかどうか…それは正直、分かりません。
結局あの時、自分を助けたのは自分自身のとっさの判断力だけでした。
もしもあの時、それすら働かなかったとしたら…そして、それでも誰一人助けてくれていなかったとしたら…ひょっとして自分は、今こうして生きていられなかったかも知れません。
事故にしろ災害にしろ、生命の危機を伴うようなピンチに陥る可能性は、誰にでもあります。
そんな時、無意識に「周りに助けを求めればいい」「誰かが助けてくれる」と思っていないでしょうか?
でも、考えてみてください。
“誰かを助ける”ためには、それなりの思考力・判断力・行動力・体力・その他諸々の能力(そして「助けよう」という意思)が必要で、その時偶然その場に居合わせた人に、それが備わっているとは限らないのです。
(あるいは、あまりにひどい事故や災害の時には、皆が皆、自分自身が助かるのに必死で、他人を助けている余裕がない可能性もあります。)
誰かに助けを求めること自体は、きっと間違ってはいません。
どんなに頑張っても自分の能力だけではどうにもならないことはありますし、そんな時に他人の力を借りるのは仕方のないことだと思います。
ただ「ピンチになっても誰かに助けてもらえばいいや」と何も考えずボンヤリと生きていて、いざピンチになった時、たまたま周りにいるのが、そんな”助ける力の無い”人たちだったら…。あるいは、そもそも周りに誰もいなかったとしたら…。
そう考えると“いざと言う時”最後の最後に本当に頼りになるのは、結局は自分自身の力なのかも知れません。
ですから、いつか来るかも知れない、そんな“いざという時”のために、常日頃から知識を蓄え、判断力を養っておくに越したことはありません。
現代社会では「いざという時のサバイバル術」を普通にテレビで特集してくれることもありますし、インターネットという便利なものもあります。
何より、その手の「いざという時のための知識」に出会った時、「自分には関係ないからいいや」とスルーするのでなく、頭の隅の方にでも何となく記憶しておくことが重要だと思うのです。
「あの時のあの知識、ちゃんと覚えておけば良かった」と、“いざという時”になってから後悔したところで、どうにもならないのですから…。
ちなみに、小学生だった当時の自分は知らなかった、踏切内に閉じ込められて出られない場合の対処法ですが…
まずは、踏切脇にある緊急用のボタン(非常ボタン?…正式名称はよく分かりません…。)を探して押してください。
(と言うか、よく使う踏切なら、緊急ボタンの位置(や有無)を予めチェックしておいた方が良いと思います。)
緊急ボタンが無い場合は、なるべく安全な場所に移動し、上着などの大きめの布(無ければ手)を大きく振るなど、できる限り運転士の方に気付かれやすいように行動してください。
ちなみにこの種の緊急用ボタンは、踏切だけでなく、駅のホームにも設置してあることがあります。
(駅のホームから人や物が落下して、近くに駅員さんがいない時用かと思われます。)
あと念のため書いておきますが、もちろんこれらの緊急ボタンは非常時以外には決して押してはいけません。
電車の運行に支障が出ますし、威力業務妨害で逮捕される例もあるらしいですから。
「踏切を横断する時は直前で一時停止し、向こう側に車1台分の空きスペースができてから横断する」という、自動車教習でなら必ず習う交通ルールを、当時知るべくもなかった小学生の自分は、空きスペースも何も考えず、前の自転車に続いてすぐ踏切に進入してしまったため、踏切の信号音が鳴りだしても、混雑していた道で前にも後ろにも進むことができず、遮断機の間に閉じ込められてしまったのでした。
自分はその時、まずは後ろ側に下がろうとしました。
(たぶん、後ろ側の遮断機の方が近かったのだと思います。)
しかし、そこには小学生くらいの知らない子たちが、自転車で集団になって固まっていて、こちらが明らかに踏切に閉じ込められかけて必死に後ろに下がろうとしているのに、道を開けたり下がろうとしてくれるどころか、一切動いてくれませんでした。
そうこうしているうちにも遮断機はどんどん降りていき…
自分は後ろの自転車集団の子たちの態度から「これは行けそうもない」と判断すると、前の遮断機へ目を向けました。
遮断機の“向こう側”は普通に車が流れていますので、さっきまでは前方を塞いでいた自転車も、いつの間にかいなくなってスペースが空いていました。
なので自分はとっさに自分の自転車をナナメに倒し、遮断機の下を潜り抜けて踏切の向こう側へ脱出しました。
忘れもしない、自分が幼少期に生命の危険をほんのり感じた幾つかの出来事のうちの一つです。
この経験を経て、身に染みて感じたことが一つあります。
それは「自分が生命の危機に瀕して助けを求めても、その時その場にいる人間に“人を助ける能力と意思”があるとは限らない」という事実です。
実際、自分が踏切に閉じ込められたあの時、助けてくれようとする人も、声をかけてくれる人もいませんでした。
遮断機の後ろにいた小学生の集団は、こちらが必死に下がろうとしているにも関わらず、動いてすらくれませんでした。
もっとも、あの時、自分もパニックになっていて、ただ無言で必死に自転車を後ろに下げようとしていただけなので、「どいて!」の一言でも言えていれば何かが違ったのかも知れません。
ただ、その言葉を発していたとしても、あの時のあの小学生集団に、あの混雑した道で、“声をかけあって一人一人が少しずつ後ろに下がっていき、自転車1台分のスペースを何とか空ける”ということが可能だったかどうか…それは正直、分かりません。
結局あの時、自分を助けたのは自分自身のとっさの判断力だけでした。
もしもあの時、それすら働かなかったとしたら…そして、それでも誰一人助けてくれていなかったとしたら…ひょっとして自分は、今こうして生きていられなかったかも知れません。
事故にしろ災害にしろ、生命の危機を伴うようなピンチに陥る可能性は、誰にでもあります。
そんな時、無意識に「周りに助けを求めればいい」「誰かが助けてくれる」と思っていないでしょうか?
でも、考えてみてください。
“誰かを助ける”ためには、それなりの思考力・判断力・行動力・体力・その他諸々の能力(そして「助けよう」という意思)が必要で、その時偶然その場に居合わせた人に、それが備わっているとは限らないのです。
(あるいは、あまりにひどい事故や災害の時には、皆が皆、自分自身が助かるのに必死で、他人を助けている余裕がない可能性もあります。)
誰かに助けを求めること自体は、きっと間違ってはいません。
どんなに頑張っても自分の能力だけではどうにもならないことはありますし、そんな時に他人の力を借りるのは仕方のないことだと思います。
ただ「ピンチになっても誰かに助けてもらえばいいや」と何も考えずボンヤリと生きていて、いざピンチになった時、たまたま周りにいるのが、そんな”助ける力の無い”人たちだったら…。あるいは、そもそも周りに誰もいなかったとしたら…。
そう考えると“いざと言う時”最後の最後に本当に頼りになるのは、結局は自分自身の力なのかも知れません。
ですから、いつか来るかも知れない、そんな“いざという時”のために、常日頃から知識を蓄え、判断力を養っておくに越したことはありません。
現代社会では「いざという時のサバイバル術」を普通にテレビで特集してくれることもありますし、インターネットという便利なものもあります。
何より、その手の「いざという時のための知識」に出会った時、「自分には関係ないからいいや」とスルーするのでなく、頭の隅の方にでも何となく記憶しておくことが重要だと思うのです。
「あの時のあの知識、ちゃんと覚えておけば良かった」と、“いざという時”になってから後悔したところで、どうにもならないのですから…。
ちなみに、小学生だった当時の自分は知らなかった、踏切内に閉じ込められて出られない場合の対処法ですが…
まずは、踏切脇にある緊急用のボタン(非常ボタン?…正式名称はよく分かりません…。)を探して押してください。
(と言うか、よく使う踏切なら、緊急ボタンの位置(や有無)を予めチェックしておいた方が良いと思います。)
緊急ボタンが無い場合は、なるべく安全な場所に移動し、上着などの大きめの布(無ければ手)を大きく振るなど、できる限り運転士の方に気付かれやすいように行動してください。
ちなみにこの種の緊急用ボタンは、踏切だけでなく、駅のホームにも設置してあることがあります。
(駅のホームから人や物が落下して、近くに駅員さんがいない時用かと思われます。)
あと念のため書いておきますが、もちろんこれらの緊急ボタンは非常時以外には決して押してはいけません。
電車の運行に支障が出ますし、威力業務妨害で逮捕される例もあるらしいですから。
前の記事(→「虐め対処の実例~小学生の時~」)に書いたように、一応は自分で虐めを解決してきた自分ですが…
自分の場合、元々“自立心がある”子どもで、「一人でもわりと平気」な性格だったことも、冷静に虐めに対処できた要因の一つではありと思います。
小学生くらいの子どもの場合、まず「一人で行動を起こす」ということ自体が怖い子もいるでしょうし、「虐められていることを周りに知られたくない」「下手に抵抗すると教室での居場所がなくなってしまうのではないか」といった考えから、あえて何の行動も起こさずに虐めを耐え続ける子もいるでしょう。
そもそも大人は簡単に「悩んだら相談して」と言いますが、子どもが大人に何かを相談するという、そのこと自体、まず心理的ハードルが高かったりするものです。
しかも「悩んでいるなら、すぐに言って」「何でそこまで思いつめる前に言ってくれなかったの?」などと言いながらも、そんな相談を聞く大人の側に“子どもの話を親身に聞く”姿勢が備わっていないことも多々あるように思うのです。
子どもの頃「どうせ大人は何も分かってくれない」と思ったこと、ありませんか?
相談に乗るフリをしながら、結局は説教をされて終わりで、身になるアドバイスも解決策も、何ひとつもらえなかったことって、ありませんか?
大人同士での“相談”でも割と見られるケースですが、ヒトは「相談に乗る」と言いながら、相手の話はロクに聞きもせず、自分の言いたいことだけを一方的に押し付け、それで「相談に乗った気になっている」ことがよくあります。
しかもさらに悪いことに、相手が愚痴り始めると「そんなこと言っちゃ駄目だ」「それは悪い考え方だ」などと否定し、その愚痴に対する反論を延々とし続けるというケースもあります。
確かに「しにたい」だとか「自分はダメな人間だ」などという言葉に「そんなこと言うな」と言いたくなる気持ちは分かります。
でも、否定から入ってしまえば、相手は「この人は話を聞いてくれない人だ」「気持ちを分かってくれない人だ」と判断して、心を閉ざし、本音を語らなくなってしまいます。
表面上は素直に“説教”もとい“諭し”の言葉を聞いているように見えても、心の中では「この人に相談するんじゃなかった」と後悔し、ますます絶望を深めるばかりになってしまいます。
ならば、どうすれば良いのか……その一つのヒントが“傾聴”というものなのではないかと思います。
――相手の話に、ただ耳を傾けること。
虐めに傷ついている子どもは、まず癒しや救い、心の支えとなるもの、あるいは“自分を受け入れてくれる何か”を求めているのではないでしょうか。
虐め加害者から否定の言葉を投げつけられ続け、自分に価値がないように思えてしまっている――そんな、自分自身ですらダメで無価値に思える人間でも、否定せずにありのままを受け止めてくれて、話を聞いてくれる――そんな相手を無意識に求めているのではないでしょうか。
そんな子どもに必要なのは、マイナス発言・思考に対する否定の言葉ではなく、まずは赤子に接する母親のような優しさで「どうしたの?」と話を聞いてあげること、そして「つらかったね」と共感してあげること、「がんばってきたんだね」とそれまでの苦しみを労り慰めてあげること――そういうことなのではないかと、自分は思うのです。
もちろん、現実に起きている虐めを解決することも必要ですが。
それと、上記のような傾聴スキルを持った相談相手が現実にはそうそう存在しないかも知れないことを考えると「自分で自分を無価値な人間と思わないようにする」「誰かに何か否定的なことを言われようと、自分だけは自分の価値を肯定する」精神力を、予め身につけておけると便利なのかなと思います。
(できれば、ですが…。)
と言うか、虐めの加害者は何かと簡単に他人の価値を否定したがりますが……否定するも何も、そもそも一人の普通の人間に“誰かの価値を見抜く能力”なんてありませんからね。
たとえビジネス・スキルや絵の才能など、ある一つの分野で他人を”評価”することはできたとしても、それは一人の人間のうちのほんの一部でしかありませんからね。
エスパーでも賢者でもないのに、人の外側や言動に表れた部分だけを見て、その人の全てを判断するなんて、不可能ですからね。
それに、たとえ今現在は周りに比べて能力が劣っていたとしても、未来もそうだとは限りませんからね。
幼少期に虐められていた人物が、将来とてつもない成功者になる実例なんて、きっと探せば山のように出てくると思うのです。
それと、虐めって、モノによっては普通に犯罪行為ですからね。
その辺の知識を身につけておいても対抗策としては便利かも知れません。
…と言うか、“倫理的・道徳的に「虐めはダメ」と訴えるだけでは効果がない”というのは、いい加減実証済みな気がするので、「虐め行為は犯罪行為」だとか「虐め加害者にはこんな末路が待っている」といった風に“リスク”の面から「虐めをすると良くない」ということを教えてみるのも、手段の一つとしてアリなのではないかと思うのですが…。
<関連記事>
・ハブられ状態脱出の実例~中学生の時~
・虐め(いじめ)対処の実例~小学生の時~
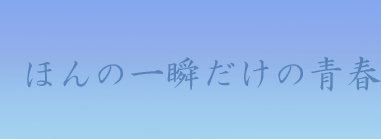
自分の場合、元々“自立心がある”子どもで、「一人でもわりと平気」な性格だったことも、冷静に虐めに対処できた要因の一つではありと思います。
小学生くらいの子どもの場合、まず「一人で行動を起こす」ということ自体が怖い子もいるでしょうし、「虐められていることを周りに知られたくない」「下手に抵抗すると教室での居場所がなくなってしまうのではないか」といった考えから、あえて何の行動も起こさずに虐めを耐え続ける子もいるでしょう。
そもそも大人は簡単に「悩んだら相談して」と言いますが、子どもが大人に何かを相談するという、そのこと自体、まず心理的ハードルが高かったりするものです。
しかも「悩んでいるなら、すぐに言って」「何でそこまで思いつめる前に言ってくれなかったの?」などと言いながらも、そんな相談を聞く大人の側に“子どもの話を親身に聞く”姿勢が備わっていないことも多々あるように思うのです。
子どもの頃「どうせ大人は何も分かってくれない」と思ったこと、ありませんか?
相談に乗るフリをしながら、結局は説教をされて終わりで、身になるアドバイスも解決策も、何ひとつもらえなかったことって、ありませんか?
大人同士での“相談”でも割と見られるケースですが、ヒトは「相談に乗る」と言いながら、相手の話はロクに聞きもせず、自分の言いたいことだけを一方的に押し付け、それで「相談に乗った気になっている」ことがよくあります。
しかもさらに悪いことに、相手が愚痴り始めると「そんなこと言っちゃ駄目だ」「それは悪い考え方だ」などと否定し、その愚痴に対する反論を延々とし続けるというケースもあります。
確かに「しにたい」だとか「自分はダメな人間だ」などという言葉に「そんなこと言うな」と言いたくなる気持ちは分かります。
でも、否定から入ってしまえば、相手は「この人は話を聞いてくれない人だ」「気持ちを分かってくれない人だ」と判断して、心を閉ざし、本音を語らなくなってしまいます。
表面上は素直に“説教”もとい“諭し”の言葉を聞いているように見えても、心の中では「この人に相談するんじゃなかった」と後悔し、ますます絶望を深めるばかりになってしまいます。
ならば、どうすれば良いのか……その一つのヒントが“傾聴”というものなのではないかと思います。
――相手の話に、ただ耳を傾けること。
虐めに傷ついている子どもは、まず癒しや救い、心の支えとなるもの、あるいは“自分を受け入れてくれる何か”を求めているのではないでしょうか。
虐め加害者から否定の言葉を投げつけられ続け、自分に価値がないように思えてしまっている――そんな、自分自身ですらダメで無価値に思える人間でも、否定せずにありのままを受け止めてくれて、話を聞いてくれる――そんな相手を無意識に求めているのではないでしょうか。
そんな子どもに必要なのは、マイナス発言・思考に対する否定の言葉ではなく、まずは赤子に接する母親のような優しさで「どうしたの?」と話を聞いてあげること、そして「つらかったね」と共感してあげること、「がんばってきたんだね」とそれまでの苦しみを労り慰めてあげること――そういうことなのではないかと、自分は思うのです。
もちろん、現実に起きている虐めを解決することも必要ですが。
それと、上記のような傾聴スキルを持った相談相手が現実にはそうそう存在しないかも知れないことを考えると「自分で自分を無価値な人間と思わないようにする」「誰かに何か否定的なことを言われようと、自分だけは自分の価値を肯定する」精神力を、予め身につけておけると便利なのかなと思います。
(できれば、ですが…。)
と言うか、虐めの加害者は何かと簡単に他人の価値を否定したがりますが……否定するも何も、そもそも一人の普通の人間に“誰かの価値を見抜く能力”なんてありませんからね。
たとえビジネス・スキルや絵の才能など、ある一つの分野で他人を”評価”することはできたとしても、それは一人の人間のうちのほんの一部でしかありませんからね。
エスパーでも賢者でもないのに、人の外側や言動に表れた部分だけを見て、その人の全てを判断するなんて、不可能ですからね。
それに、たとえ今現在は周りに比べて能力が劣っていたとしても、未来もそうだとは限りませんからね。
幼少期に虐められていた人物が、将来とてつもない成功者になる実例なんて、きっと探せば山のように出てくると思うのです。
それと、虐めって、モノによっては普通に犯罪行為ですからね。
その辺の知識を身につけておいても対抗策としては便利かも知れません。
…と言うか、“倫理的・道徳的に「虐めはダメ」と訴えるだけでは効果がない”というのは、いい加減実証済みな気がするので、「虐め行為は犯罪行為」だとか「虐め加害者にはこんな末路が待っている」といった風に“リスク”の面から「虐めをすると良くない」ということを教えてみるのも、手段の一つとしてアリなのではないかと思うのですが…。
<関連記事>
・ハブられ状態脱出の実例~中学生の時~
・虐め(いじめ)対処の実例~小学生の時~
自分は元々早生まれな上、丸1ヶ月近い早産で生まれた未熟児で、同じ学年の子どもたちより常に体格で劣っていました。
(「前へならえ」では、ほぼ毎年「腰に手をあてる」役だったくらいに…。)
おまけに運動音痴で体力も無く、ぱっと見“ひ弱”そうで“おとなしい”性格に見られていたため、虐め(いじめ)のターゲットにされやすいタイプではありました。
もっとも自分の場合、物心ついた時から妙に“知恵の回る”子どもだったため、己の立ち位置をよく把握しており、その小さな体格を逆に利用して“グループの中のマスコット・キャラ”“(数か月だけ)年下キャラ”を演じることで、「イジられはしても虐められはしない」という地位を確保している……つもりでした。
“つもり”というのは、自分も何分まだ小学生で、“知恵が回る”と言っても“ツメが甘かった”ため、気づいていない思考の死角があったということです。
――それはすなわち「イジりもエスカレートすれば簡単に虐めに変わる」という事実でした。
そんなこんなで、小学生時代の自分は何度か虐めを受けてきました。
最初のうちは家族にそのことを訴えたりもしましたが、考え方がまるで“旧時代”で「やられたらやり返すんだよ」という何の解決にもならないアドバイスしかくれない家族に、「この人たちに言っても無駄だ」とすぐに見切りをつけました。
(うちの家族の場合はそんな風でしたが、世の中には真剣に話を聞いてくれる頼りがいのある家族もいると思いますので、相談する前からあきらめる必要は無いと思います。重要なのは相談する相手の性格と知識と能力です。)
かと言って絶望の淵に沈むかと思えば全くそうではなく、自分は「家族に頼らずにこの状況を何とかする方法」を一人で考え始めました。
それこそ、虐められている真っ最中も、一人だんまりを決め込みながら、頭の中ではコツコツ冷静に解決法を練っていました。
結局その解決法は、担任の先生に自分の置かれている状況を訴えるというものだったのですが…
虐め加害者もいる教室内で先生に言うのは、リスクが高過ぎますし、職員室へ行って…というのも、なかなかハードルの高い行為でした。
それに口で説明する方法だと、緊張して上手く伝えられない可能性や、肝心なことを言い漏らしてしまう可能性もあります。
なので、小学4年生当時の自分がとった方法は「学習ノートを使う」というものでした。
自分の通っていた小学校では、児童それぞれが家で好きな教科を選んで勉強し、その内容をノートにまとめて先生に提出する“自習用”のノートがありました。
(後で赤ペンで担任の先生のコメントが付いて返ってくるのです。)
そのノートに自分は、自分がされている虐めの内容を客観的事実(いつ・どこで・誰に・何をされたのか)と主観的感想(その時、自分がどう感じたか)を交えて図解入りで詳細にまとめ、普段学習ノートを提出するのと全く同じように、しれっと提出したのです。
その直後、学級会でこのノートの内容が、被害者の名前と加害者の名前を匿名(黒塗り)にした上で取り上げられ、それが功を奏したのか、その後、その子たちからの虐めはなくなりました。
(相手がそれで反省していたのかどうかは分かりませんが、「こいつ、虐めるとリベンジしてくるぞ」ということを相手の頭にインプットするだけでも、ある程度の虐め抑制効果があったのではないかと思います。)
もっとも、コレは“たまたま上手くいったケース”というだけで、全ての虐めに通用する方法だとは思っていません。
こういった方法で虐めが止まるかどうかは、虐めの程度や内容、虐め加害者の性格にもよるでしょうし、担任の先生の力量や性格も関係してくるかも知れません。
それに、今にして思うと、さすがに小学4年生だけあって、自分のやり方もツメが甘かったと思います。
今の自分がやるなら、ノート1冊だけではなく、万が一担任の先生に握りつぶされた場合に備えて、予備のノートをもっと作っておきますし、できるなら文章だけではなく、物的証拠や写真(画像データ)も(虐め加害者にバレないように慎重に)収集・確保しておきます。
何げに最近はそういう“証拠集め”を、お年玉などを使ってプロ(興信所など)に依頼するケースもあるようですね。
(数年前にTV番組でそういう話を聞きました。うろ覚え情報ではありますが。)
<関連記事>
・ハブられ状態脱出の実例~中学生の時~
・小学校時代の虐め(いじめ)を経て思うこと
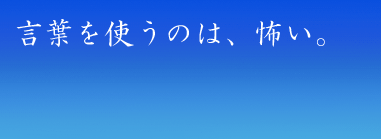
(「前へならえ」では、ほぼ毎年「腰に手をあてる」役だったくらいに…。)
おまけに運動音痴で体力も無く、ぱっと見“ひ弱”そうで“おとなしい”性格に見られていたため、虐め(いじめ)のターゲットにされやすいタイプではありました。
もっとも自分の場合、物心ついた時から妙に“知恵の回る”子どもだったため、己の立ち位置をよく把握しており、その小さな体格を逆に利用して“グループの中のマスコット・キャラ”“(数か月だけ)年下キャラ”を演じることで、「イジられはしても虐められはしない」という地位を確保している……つもりでした。
“つもり”というのは、自分も何分まだ小学生で、“知恵が回る”と言っても“ツメが甘かった”ため、気づいていない思考の死角があったということです。
――それはすなわち「イジりもエスカレートすれば簡単に虐めに変わる」という事実でした。
そんなこんなで、小学生時代の自分は何度か虐めを受けてきました。
最初のうちは家族にそのことを訴えたりもしましたが、考え方がまるで“旧時代”で「やられたらやり返すんだよ」という何の解決にもならないアドバイスしかくれない家族に、「この人たちに言っても無駄だ」とすぐに見切りをつけました。
(うちの家族の場合はそんな風でしたが、世の中には真剣に話を聞いてくれる頼りがいのある家族もいると思いますので、相談する前からあきらめる必要は無いと思います。重要なのは相談する相手の性格と知識と能力です。)
かと言って絶望の淵に沈むかと思えば全くそうではなく、自分は「家族に頼らずにこの状況を何とかする方法」を一人で考え始めました。
それこそ、虐められている真っ最中も、一人だんまりを決め込みながら、頭の中ではコツコツ冷静に解決法を練っていました。
結局その解決法は、担任の先生に自分の置かれている状況を訴えるというものだったのですが…
虐め加害者もいる教室内で先生に言うのは、リスクが高過ぎますし、職員室へ行って…というのも、なかなかハードルの高い行為でした。
それに口で説明する方法だと、緊張して上手く伝えられない可能性や、肝心なことを言い漏らしてしまう可能性もあります。
なので、小学4年生当時の自分がとった方法は「学習ノートを使う」というものでした。
自分の通っていた小学校では、児童それぞれが家で好きな教科を選んで勉強し、その内容をノートにまとめて先生に提出する“自習用”のノートがありました。
(後で赤ペンで担任の先生のコメントが付いて返ってくるのです。)
そのノートに自分は、自分がされている虐めの内容を客観的事実(いつ・どこで・誰に・何をされたのか)と主観的感想(その時、自分がどう感じたか)を交えて図解入りで詳細にまとめ、普段学習ノートを提出するのと全く同じように、しれっと提出したのです。
その直後、学級会でこのノートの内容が、被害者の名前と加害者の名前を匿名(黒塗り)にした上で取り上げられ、それが功を奏したのか、その後、その子たちからの虐めはなくなりました。
(相手がそれで反省していたのかどうかは分かりませんが、「こいつ、虐めるとリベンジしてくるぞ」ということを相手の頭にインプットするだけでも、ある程度の虐め抑制効果があったのではないかと思います。)
もっとも、コレは“たまたま上手くいったケース”というだけで、全ての虐めに通用する方法だとは思っていません。
こういった方法で虐めが止まるかどうかは、虐めの程度や内容、虐め加害者の性格にもよるでしょうし、担任の先生の力量や性格も関係してくるかも知れません。
それに、今にして思うと、さすがに小学4年生だけあって、自分のやり方もツメが甘かったと思います。
今の自分がやるなら、ノート1冊だけではなく、万が一担任の先生に握りつぶされた場合に備えて、予備のノートをもっと作っておきますし、できるなら文章だけではなく、物的証拠や写真(画像データ)も(虐め加害者にバレないように慎重に)収集・確保しておきます。
何げに最近はそういう“証拠集め”を、お年玉などを使ってプロ(興信所など)に依頼するケースもあるようですね。
(数年前にTV番組でそういう話を聞きました。うろ覚え情報ではありますが。)
<関連記事>
・ハブられ状態脱出の実例~中学生の時~
・小学校時代の虐め(いじめ)を経て思うこと
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(01/03)
(11/17)
(10/27)
(08/11)
(04/07)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
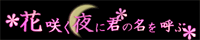
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
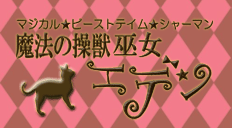
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
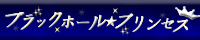
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
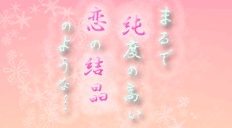
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
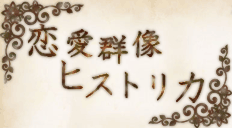
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
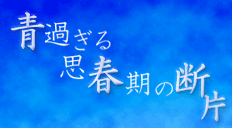
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
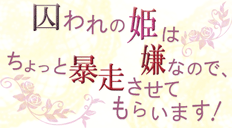
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
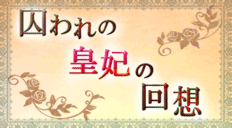
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
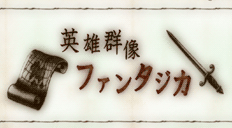
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
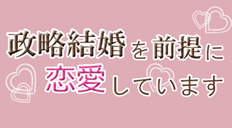
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
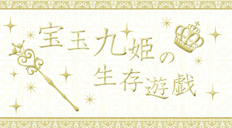
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

