日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
今の時代を見ていて不思議に思うのが「『意見の否定=その人の存在自体の否定』になっていないか?」ということです。
自分にとって「気に食わない意見」を持つ相手のことを、罵倒し、侮辱し、人格否定し、まるでこの世から葬り去ろうとでもするように徹底的に攻撃する…そんなことが、世の中に溢れている気がするのです。
でも「相手の意見を否定すること」と「相手の存在自体を否定すること」は決してイコールではありませんよね?
なぜ、そこを「一緒くた」にし、しかも、そのことに何の疑問も抱かずにいるのか…。
その「なぜ」の「答え」として、ひとつ推測しているのは、「感情に目がくらんで、『意見の否定』と『人格否定』を分けて考えることができなくなっているのではないか」ということです。
相手の意見に「怒り」や「不快」などの「負の感情」が刺激された結果、自分の言動が「意見の否定」という次元を遥かにオーバーし、「人格の否定」にまで至ってしまっていることに気づけない…
あるいは、気づいていても、無意識のうちにそれを「正当化」し、自分の感情を満足させることの方を優先させてしまう…
つまり「自分の言動を冷静に顧みることができない」「自分を律することができていない」ことが原因なのではないかと…。
あるいは、そもそも今の社会の中に「意見を戦わせる上で、相手の人格を攻撃しても構わない」という、誤った共通認識が育まれてしまっているのではないか、と…。
自分と対立する意見の相手は、存在自体を認めないと言うなら、そもそも「議論」そのものが成り立ちません。
それは「議論」ではなく、ただ自分の意見を周りに「押し付ける」ための場でしかありません。
たとえ自分とは反対の意見だったとしても、自分にとって「気に食わない」意見だったとしても、まずは「耳を傾ける」――それが、「議論」というものの「最低限」のルールのはずなのですが…その「最低限」ができていない人が多過ぎる、ということなのでしょうか?
そもそも、なぜそんなにも「自分の意見を通したがる」のか、自分の目からすると、そこからして不可解でなりません。
他人の存在を否定してまで自分の意見を通して――その意見が間違っていた場合、自分も他者も皆まとめて破滅するリスクがあるわけですが(そしてその場合、その破滅に対する「責任」が否応なく発生するわけですが)…そこの所は考えていない、ということなのでしょうか?
議論とはそもそも、多様性のある意見を集めることで、「ひとりの人間の視点」だけでは見出せない問題解決法を導き出すためのものだと思っていたのですが…そう思っていない(自分の意見を通す場とだけ考えている)人間が多いということなのでしょうか?
思えば我々は、義務教育の中できちんとした「議論の方法」を学んではいません。
「学級会」や「ホームルーム」で何かを決める際は、結局「多数決」で終わってしまい、「意見の調整」「意見のすり合わせ」「対立意見の妥協点を見出す」などは一切見られなかったように思います。
それゆえ、大人になってからも、そんな「多数決の勝ち負け」で全てを考えてしまうのでしょうか?
自分の意見が勝てばそれで良いと、そこで思考を止めてしまい、その結果、少数派がどうなるかについては一切思いをめぐらせないのでしょうか?
むしろ、勝者の権利とばかりに、敗者を徹底的に足蹴にしようとするのでしょうか?
推測はあくまで推測でしかありませんので、実際のところは分かりません。
しかし、もし「そう」なのだとしたら…今の世の中の様々な問題、そして「生きづらさ」の根本は、そこにあるのかも知れません。
自分にとって「気に食わない意見」を持つ相手のことを、罵倒し、侮辱し、人格否定し、まるでこの世から葬り去ろうとでもするように徹底的に攻撃する…そんなことが、世の中に溢れている気がするのです。
でも「相手の意見を否定すること」と「相手の存在自体を否定すること」は決してイコールではありませんよね?
なぜ、そこを「一緒くた」にし、しかも、そのことに何の疑問も抱かずにいるのか…。
その「なぜ」の「答え」として、ひとつ推測しているのは、「感情に目がくらんで、『意見の否定』と『人格否定』を分けて考えることができなくなっているのではないか」ということです。
相手の意見に「怒り」や「不快」などの「負の感情」が刺激された結果、自分の言動が「意見の否定」という次元を遥かにオーバーし、「人格の否定」にまで至ってしまっていることに気づけない…
あるいは、気づいていても、無意識のうちにそれを「正当化」し、自分の感情を満足させることの方を優先させてしまう…
つまり「自分の言動を冷静に顧みることができない」「自分を律することができていない」ことが原因なのではないかと…。
あるいは、そもそも今の社会の中に「意見を戦わせる上で、相手の人格を攻撃しても構わない」という、誤った共通認識が育まれてしまっているのではないか、と…。
自分と対立する意見の相手は、存在自体を認めないと言うなら、そもそも「議論」そのものが成り立ちません。
それは「議論」ではなく、ただ自分の意見を周りに「押し付ける」ための場でしかありません。
たとえ自分とは反対の意見だったとしても、自分にとって「気に食わない」意見だったとしても、まずは「耳を傾ける」――それが、「議論」というものの「最低限」のルールのはずなのですが…その「最低限」ができていない人が多過ぎる、ということなのでしょうか?
そもそも、なぜそんなにも「自分の意見を通したがる」のか、自分の目からすると、そこからして不可解でなりません。
他人の存在を否定してまで自分の意見を通して――その意見が間違っていた場合、自分も他者も皆まとめて破滅するリスクがあるわけですが(そしてその場合、その破滅に対する「責任」が否応なく発生するわけですが)…そこの所は考えていない、ということなのでしょうか?
議論とはそもそも、多様性のある意見を集めることで、「ひとりの人間の視点」だけでは見出せない問題解決法を導き出すためのものだと思っていたのですが…そう思っていない(自分の意見を通す場とだけ考えている)人間が多いということなのでしょうか?
思えば我々は、義務教育の中できちんとした「議論の方法」を学んではいません。
「学級会」や「ホームルーム」で何かを決める際は、結局「多数決」で終わってしまい、「意見の調整」「意見のすり合わせ」「対立意見の妥協点を見出す」などは一切見られなかったように思います。
それゆえ、大人になってからも、そんな「多数決の勝ち負け」で全てを考えてしまうのでしょうか?
自分の意見が勝てばそれで良いと、そこで思考を止めてしまい、その結果、少数派がどうなるかについては一切思いをめぐらせないのでしょうか?
むしろ、勝者の権利とばかりに、敗者を徹底的に足蹴にしようとするのでしょうか?
推測はあくまで推測でしかありませんので、実際のところは分かりません。
しかし、もし「そう」なのだとしたら…今の世の中の様々な問題、そして「生きづらさ」の根本は、そこにあるのかも知れません。
PR
社会人になってから気づいたことがあります。
それは、「分からない」には種類がある、ということです。
ひとつは「理解する能力が無い」から生じる「分からない」。
もうひとつは「理解する気が無い(理解する気が起きない)」から生じる「分からない」です。
どんな人でも分かるようにと、どんなに取扱説明書を分かりやすく工夫しようと、「分からない」人は「分からない」と言ってきます。
それなのに、こちらが取説をそのまま読み上げ、その通りに操作してもらうと、あっさり「出来て」しまったりするのです。
そんなことが何度かあり、思ったのが、「これは『理解できない』わけではなく、取説を取り出したり、その中から必要な操作を書いたページを探し出したり、そこに書いてある内容を理解するのが『面倒くさい』だけなのだろう」ということでした。
自分で説明書を読み込んで理解するより、他人に訊いてそのままやった方が「簡単」で「面倒くさくない」から、あえて「分からない」ままでいる…
世の中にはたぶん、そういう人々が存在するのです。
きっとこれは、機械の操作や業務の進め方に限らないことだと思われます。
世の中に溢れる様々な“問題”や“課題”――難しくて理解できない、という人のうち、「理解する能力が無い」から分からない人は、一体どれだけいるのでしょう。
きっと中には、理解する能力があっても、理解する気が無いから「分からない」、理解するのが面倒くさいから「分からない」という人間が相当数いるはずです。
人はそもそも、興味を持っていない分野のことは理解したがらないものです。
人生は有限で、処理しなければならない情報・問題は膨大にあります。
そんな中で、特に興味の無いことに頭を割いている余裕は無いのかも知れません。
しかし、そんな「本当は分かるはずなのに」あえて「分からない」ままにしていることが、時に誰かを苦しめたり、誰かに余計な負担を負わせたりしているのではないか…そんな風にも思うのです。
「愛の反対は、憎しみではなく無関心」という言葉があります。
本当は理解できるはずなのに、わざと理解しないでいる、そんな「分からない」も、「愛の反対」なのかも知れない――そんなことを、自戒も込めて考えてみる今日この頃です。
それは、「分からない」には種類がある、ということです。
ひとつは「理解する能力が無い」から生じる「分からない」。
もうひとつは「理解する気が無い(理解する気が起きない)」から生じる「分からない」です。
どんな人でも分かるようにと、どんなに取扱説明書を分かりやすく工夫しようと、「分からない」人は「分からない」と言ってきます。
それなのに、こちらが取説をそのまま読み上げ、その通りに操作してもらうと、あっさり「出来て」しまったりするのです。
そんなことが何度かあり、思ったのが、「これは『理解できない』わけではなく、取説を取り出したり、その中から必要な操作を書いたページを探し出したり、そこに書いてある内容を理解するのが『面倒くさい』だけなのだろう」ということでした。
自分で説明書を読み込んで理解するより、他人に訊いてそのままやった方が「簡単」で「面倒くさくない」から、あえて「分からない」ままでいる…
世の中にはたぶん、そういう人々が存在するのです。
きっとこれは、機械の操作や業務の進め方に限らないことだと思われます。
世の中に溢れる様々な“問題”や“課題”――難しくて理解できない、という人のうち、「理解する能力が無い」から分からない人は、一体どれだけいるのでしょう。
きっと中には、理解する能力があっても、理解する気が無いから「分からない」、理解するのが面倒くさいから「分からない」という人間が相当数いるはずです。
人はそもそも、興味を持っていない分野のことは理解したがらないものです。
人生は有限で、処理しなければならない情報・問題は膨大にあります。
そんな中で、特に興味の無いことに頭を割いている余裕は無いのかも知れません。
しかし、そんな「本当は分かるはずなのに」あえて「分からない」ままにしていることが、時に誰かを苦しめたり、誰かに余計な負担を負わせたりしているのではないか…そんな風にも思うのです。
「愛の反対は、憎しみではなく無関心」という言葉があります。
本当は理解できるはずなのに、わざと理解しないでいる、そんな「分からない」も、「愛の反対」なのかも知れない――そんなことを、自戒も込めて考えてみる今日この頃です。
学生時代、自分の成績には、かなりのムラがありました。
理数系はダメダメでしたが、得意な国語は学年1位の常連でした。
そしてその国語に関して言えば、塾などには一切通ったことがなく、特別な「勉強」をした記憶もありません。
それでも国語の成績が異常に良かったのは…自分にとって国語の知識を高めることが、「勉強」ではなく「日常の一部」だったせいかと思われます。
自分は物心ついた時から活字中毒で、小学生の頃から図書館の本を読み尽くす勢いで本を読み漁っていました。
さらには自分で物語を作るのも好きで、そんな物語の糧とすべく、せっせと語彙や知識を吸収しまくっていました。
高校の入学時に伯父にリクエストした入学祝いは「広辞苑」で、高校時代は暇があれば適当に開いたページを「読んで」遊んでいました。
国語の教科書は自分にとっては「教科書」ではなく、詩や短編など様々な文学を集めた「アンソロジー」でした。
授業が始まる前から教科書を読み込み、結局授業では習わずに終わった部分さえしっかり内容を把握していました。
(さらに言えば、自分の代の教科書だけでなく、兄弟の使っていた教科書にまで手を出していたので、他の世代の国語の教科書の内容も知っていたりします…。)
つまり…自分にとって国語を学ぶことは、苦痛な「勉強」ではなく、「楽しみ」や「趣味」だったのです。
「好きこそものの上手なれ」ということわざがあるように、人間誰しも、好きなことに関してはビックリするようなパフォーマンスを発揮するものです。
逆に、苦手意識を持ち「嫌だなぁ」と思っているものに対しては、思うように能力を発揮できないのではないでしょうか。
学校には、各教科を「嫌」で「苦手」なものに変えてしまう「罠」がたくさん存在します。
知識を暗記するばかりで、おもしろみの全く無いテスト対策…
周りの友達の「勉強なんてつまらないよな」という同調圧力…
学年が上がるにつれ増す難易度、教科書から減っていくイラストや図解…
その罠にはまらず、勉強を勉強と思わずに楽しむことができるなら、学力を上げることはそれほど難しくないと思います。
授業や受験対策、テスト勉強などはひとまず置いておいて、まずは各教科で自分が興味を持てそうな「要素」を見つけることです。
日本史の人物の中におかしな名前を見つけて喜ぶことから始めたって良いと思います。
和英辞典を使ってカッコイイ必殺技名を考え出すことから始めたって良いと思います。
大切なのは、まずは興味を持ち、知識を深める「きっかけ」を持つこと。
そして勉強を勉強と思わず、ちょっと変わった趣味のひとつにしてしまうことです。
…ただ、こういう“遊びから始める学力の深め方”は、それなりに長期戦となりますので、なるべく早い段階で始めておいた方が良いです。
あと、遊びから学んだ知識だと、受験と全く関係ない部分を異常に深く掘り下げてしまう場合もあります…。
(それはそれで、受験の役には立たなくても、後で人生の役に立つ場合があるので良いのですが…。)
理数系はダメダメでしたが、得意な国語は学年1位の常連でした。
そしてその国語に関して言えば、塾などには一切通ったことがなく、特別な「勉強」をした記憶もありません。
それでも国語の成績が異常に良かったのは…自分にとって国語の知識を高めることが、「勉強」ではなく「日常の一部」だったせいかと思われます。
自分は物心ついた時から活字中毒で、小学生の頃から図書館の本を読み尽くす勢いで本を読み漁っていました。
さらには自分で物語を作るのも好きで、そんな物語の糧とすべく、せっせと語彙や知識を吸収しまくっていました。
高校の入学時に伯父にリクエストした入学祝いは「広辞苑」で、高校時代は暇があれば適当に開いたページを「読んで」遊んでいました。
国語の教科書は自分にとっては「教科書」ではなく、詩や短編など様々な文学を集めた「アンソロジー」でした。
授業が始まる前から教科書を読み込み、結局授業では習わずに終わった部分さえしっかり内容を把握していました。
(さらに言えば、自分の代の教科書だけでなく、兄弟の使っていた教科書にまで手を出していたので、他の世代の国語の教科書の内容も知っていたりします…。)
つまり…自分にとって国語を学ぶことは、苦痛な「勉強」ではなく、「楽しみ」や「趣味」だったのです。
「好きこそものの上手なれ」ということわざがあるように、人間誰しも、好きなことに関してはビックリするようなパフォーマンスを発揮するものです。
逆に、苦手意識を持ち「嫌だなぁ」と思っているものに対しては、思うように能力を発揮できないのではないでしょうか。
学校には、各教科を「嫌」で「苦手」なものに変えてしまう「罠」がたくさん存在します。
知識を暗記するばかりで、おもしろみの全く無いテスト対策…
周りの友達の「勉強なんてつまらないよな」という同調圧力…
学年が上がるにつれ増す難易度、教科書から減っていくイラストや図解…
その罠にはまらず、勉強を勉強と思わずに楽しむことができるなら、学力を上げることはそれほど難しくないと思います。
授業や受験対策、テスト勉強などはひとまず置いておいて、まずは各教科で自分が興味を持てそうな「要素」を見つけることです。
日本史の人物の中におかしな名前を見つけて喜ぶことから始めたって良いと思います。
和英辞典を使ってカッコイイ必殺技名を考え出すことから始めたって良いと思います。
大切なのは、まずは興味を持ち、知識を深める「きっかけ」を持つこと。
そして勉強を勉強と思わず、ちょっと変わった趣味のひとつにしてしまうことです。
…ただ、こういう“遊びから始める学力の深め方”は、それなりに長期戦となりますので、なるべく早い段階で始めておいた方が良いです。
あと、遊びから学んだ知識だと、受験と全く関係ない部分を異常に深く掘り下げてしまう場合もあります…。
(それはそれで、受験の役には立たなくても、後で人生の役に立つ場合があるので良いのですが…。)
世の中には「少し考えれば分かることなのに」ということを見落としている人々が沢山います。
それを自分は少し前まで「そもそも思考能力が無い(低い)」あるいは「見る目が無い(視点が欠けている)」のだと、単純に考えていました。
しかし、社会人生活も長くなり、最近では考え方が変わってきています。
「少し考えれば分かること」が分からない人々は、もしかしたら「考える能力」や「視点」は持っていても、それが充分に発揮できない状況にあるのではないかと…。
現代の日本人は、多忙です。
情報通信技術の発達により、数年前、数十年前は数日かかっていた仕事が1日…下手すると数時間でできてしまうため、よりスケジュールが過密になっています。
(技術の発達が逆に人間を苦しめるという皮肉なパターンですね…。)
納期も単位が「日」ではなく「時間」になっており、いつもギリギリの状況だったりします(会社にもよるのでしょうけど…)。
そして、実際に職場で、自他ともに経験していることなのですが、仕事が過密で多忙になればなるほど、普段なら起きないようなミス(ヒューマンエラー)が頻発したりします。
それは能力の高低や仕事の熟練度によらず、「こんなベテランが何故こんなミスを?」という事例も少なくありません。
理由として考えられるのは「人間は忙しくなると精神の余裕が失われ、能力やパフォーマンスが下がる」ということです。
自分自身を省みても、頭が疲労している時には、だいぶ判断力が鈍ったり、普段見落とさないものを見落としたりしているな、と感じます。
そもそも「忙しい」とは「心を亡くす」と書きます。
心を喪失してしまっているがゆえに、普段なら見えるはずのものが見えなくなる――忙しさとはそういうもので、現代人はその忙しさにより、常に心を喪失させられているのではないか…そんな風に思うのです。
仕事に限らず、現代ではプライベートでも、日々更新されるネットニュースやSNSや動画などの情報を処理しなくてはならず、何かと「脳」が多忙になりがちです。
世の中に溢れるその情報の量は膨大で、ひょっとしたら「人間」の能力を超えた、過剰な情報を処理させられている可能性もあります。
それゆえに、現代人は「心の余裕」を「亡くして」いるのかも知れません。
現代のこの社会は、もしかしたら、人間が「人間らしく」生きていくには適さない社会なのかも知れない…ふと、そんな風に考えさせられる、今日この頃です。
それを自分は少し前まで「そもそも思考能力が無い(低い)」あるいは「見る目が無い(視点が欠けている)」のだと、単純に考えていました。
しかし、社会人生活も長くなり、最近では考え方が変わってきています。
「少し考えれば分かること」が分からない人々は、もしかしたら「考える能力」や「視点」は持っていても、それが充分に発揮できない状況にあるのではないかと…。
現代の日本人は、多忙です。
情報通信技術の発達により、数年前、数十年前は数日かかっていた仕事が1日…下手すると数時間でできてしまうため、よりスケジュールが過密になっています。
(技術の発達が逆に人間を苦しめるという皮肉なパターンですね…。)
納期も単位が「日」ではなく「時間」になっており、いつもギリギリの状況だったりします(会社にもよるのでしょうけど…)。
そして、実際に職場で、自他ともに経験していることなのですが、仕事が過密で多忙になればなるほど、普段なら起きないようなミス(ヒューマンエラー)が頻発したりします。
それは能力の高低や仕事の熟練度によらず、「こんなベテランが何故こんなミスを?」という事例も少なくありません。
理由として考えられるのは「人間は忙しくなると精神の余裕が失われ、能力やパフォーマンスが下がる」ということです。
自分自身を省みても、頭が疲労している時には、だいぶ判断力が鈍ったり、普段見落とさないものを見落としたりしているな、と感じます。
そもそも「忙しい」とは「心を亡くす」と書きます。
心を喪失してしまっているがゆえに、普段なら見えるはずのものが見えなくなる――忙しさとはそういうもので、現代人はその忙しさにより、常に心を喪失させられているのではないか…そんな風に思うのです。
仕事に限らず、現代ではプライベートでも、日々更新されるネットニュースやSNSや動画などの情報を処理しなくてはならず、何かと「脳」が多忙になりがちです。
世の中に溢れるその情報の量は膨大で、ひょっとしたら「人間」の能力を超えた、過剰な情報を処理させられている可能性もあります。
それゆえに、現代人は「心の余裕」を「亡くして」いるのかも知れません。
現代のこの社会は、もしかしたら、人間が「人間らしく」生きていくには適さない社会なのかも知れない…ふと、そんな風に考えさせられる、今日この頃です。
昔からモヤモヤしていることの1つに「謙虚でいることと、自信を持つことのバランスが難しい」ということがあります。
自分は気づけば何となく「謙虚を美徳」として育っていました。
「自分はスゴいんだ」「自分はこんなに頭が良いんだ」と考えるのは「驕り」で「良くない」ことだと、常に自分を戒め、自分の能力を低く見るようにしてきました。
それは道徳や倫理的な理由からではなく、どちらかと言うと「自分の力に驕れば破滅が待っている」という歴史からの教訓を素直に受け止めていたがゆえのことでした。
しかし、このスタンスにはとても大きな「副作用」や「弊害」がありました。
それは「自分の能力を常に低めに見積もっているがゆえに、自信を持てない」ということ、そして「自分と他人の能力差を正確に把握することができない」ということです。
世の中には、実力を持っていなくても何故か自信満々な人間もいます。
逆に実力はあっても、「自分なんてそんなにスゴくない」「特別なんかじゃない」「驕ってはいけない」と常に自分に言い聞かせているような人間に「自信満々」な態度などとれるはずがありません。
しかし人間というものは、目に見えない「実力」より、態度として表れた「自信」でその人の評価を下してしまったりするもののようです。
特にそれが強く表れるのは就職活動などの自己PRの場なのではないかと思います。
自分は当初、「自己申告の“自己PR”なんて、皆“話半分”に判断するに違いない」と思っていました。
上記の通り、自信の有無と実力の有無は比例しませんし、主観的な自己分析と客観的な人的評価は異なります。
「アピール能力」は営業職なら有益でしょうが、職種によっては特に必要の無い能力ですし、そんなものよりもっと他に「見るべき能力」があるはずだ、と思っていたのです。
しかし、就活を続けるうちに「あれ?世の中って、自分が思っていたよりずっと“見た目”や“イメージ”に引きずられているんじゃ…?」と思い始めました。
自分はこういう性格なので「表に出ているものだけが全てではない」ということには早いうちから気づいていたのですが、たどってきた人生によっては、それに気づけないこともあるのかと…。
常に己を戒め、己に疑問を持って生きる自分には「自信満々に振る舞う」ことは不得意なのですが、謙虚に振る舞い、自信を表に出さないことによって能力を不当に低く評価されるのもだいぶ不本意です。
なので最近は少しずつ、その辺のスタンスを変えてみているのですが…
上手くいっているのかどうかは、実際よく分かりません…。
自分は気づけば何となく「謙虚を美徳」として育っていました。
「自分はスゴいんだ」「自分はこんなに頭が良いんだ」と考えるのは「驕り」で「良くない」ことだと、常に自分を戒め、自分の能力を低く見るようにしてきました。
それは道徳や倫理的な理由からではなく、どちらかと言うと「自分の力に驕れば破滅が待っている」という歴史からの教訓を素直に受け止めていたがゆえのことでした。
しかし、このスタンスにはとても大きな「副作用」や「弊害」がありました。
それは「自分の能力を常に低めに見積もっているがゆえに、自信を持てない」ということ、そして「自分と他人の能力差を正確に把握することができない」ということです。
世の中には、実力を持っていなくても何故か自信満々な人間もいます。
逆に実力はあっても、「自分なんてそんなにスゴくない」「特別なんかじゃない」「驕ってはいけない」と常に自分に言い聞かせているような人間に「自信満々」な態度などとれるはずがありません。
しかし人間というものは、目に見えない「実力」より、態度として表れた「自信」でその人の評価を下してしまったりするもののようです。
特にそれが強く表れるのは就職活動などの自己PRの場なのではないかと思います。
自分は当初、「自己申告の“自己PR”なんて、皆“話半分”に判断するに違いない」と思っていました。
上記の通り、自信の有無と実力の有無は比例しませんし、主観的な自己分析と客観的な人的評価は異なります。
「アピール能力」は営業職なら有益でしょうが、職種によっては特に必要の無い能力ですし、そんなものよりもっと他に「見るべき能力」があるはずだ、と思っていたのです。
しかし、就活を続けるうちに「あれ?世の中って、自分が思っていたよりずっと“見た目”や“イメージ”に引きずられているんじゃ…?」と思い始めました。
自分はこういう性格なので「表に出ているものだけが全てではない」ということには早いうちから気づいていたのですが、たどってきた人生によっては、それに気づけないこともあるのかと…。
常に己を戒め、己に疑問を持って生きる自分には「自信満々に振る舞う」ことは不得意なのですが、謙虚に振る舞い、自信を表に出さないことによって能力を不当に低く評価されるのもだいぶ不本意です。
なので最近は少しずつ、その辺のスタンスを変えてみているのですが…
上手くいっているのかどうかは、実際よく分かりません…。
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(11/08)
(10/26)
(10/19)
(10/13)
(10/05)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
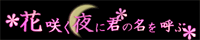
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
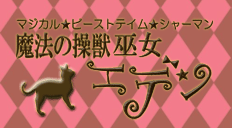
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
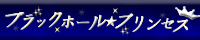
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
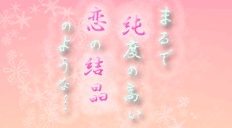
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
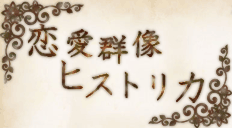
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
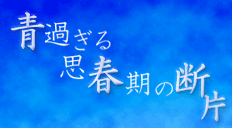
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
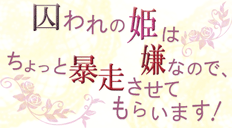
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
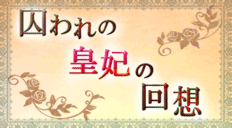
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
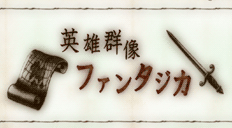
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
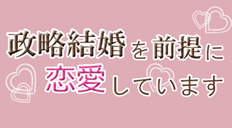
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
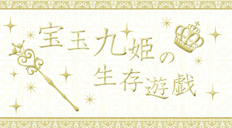
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

