日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
世の中「頭が良いはず」なのに、なぜか「おかしな方向」へ行ってしまう人って、いますよね?
元から「頭が悪い」ならともかく、高学歴だったり高スペックだったりするにも関わらず、「そうはならんやろ」という「やらかし」や「問題発言」で身の破滅を招いてしまうタイプの人が…。
そういう人々を見るたびに「本当の頭の良さって何なんだろう…?」と疑問に思うのですが…
最近、ふと思いついたことがあります。
それは「『自分にとって“不都合”な意見を受け入れられるか否か』が“知性の分かれ目”なのではないか?」ということです。
自分と「真逆」の意見、自分の主張に「反対」する意見を、とことん拒絶し、あまつさえ「攻撃」する人って、いますよね?
自分は昔から、ソレに疑問を抱いていました。
なぜなら自分にとって大切なのは「自分の意見が通るかどうか」ではなく「何が一番“最良”の答えか」だったからです。
だって、多数決で勝利して自分の意見が通ったとして、それが“最悪”の間違いだった場合、賛成していた人はもちろん、反対していた人まで全員道連れにしての「破滅コース」じゃないですか。
自分にとっての優先事項は、常に「自分がこの世界で生き残っていくこと」でした。
そのためには「自分を生き残らせてくれる答え」こそが必要で、たとえそれが「自分の」意見でなくても構わないのです。
たとえばサバイバルな状況下で、サバイバル知識が全く無い「自分」と、サバイバル知識に長けた「他人」がいたとして――そこで「自分の意見が通らないと気が済まない」なんてワガママを言っていられますか?
…思うに「異論を絶対に認められない人」って、人生において、判断ひとつが生死を分けるような「ギリギリの極限状態」に置かれたことがないのではないでしょうか(いや、そもそもそこに置かれたことのある人の方が少なそうですけど…)?
「自分の選択が間違っていたら、そこで人生ゲームオーバー」という切迫感を味わったことのない、「平和」過ぎる意識の持ち主なのではないでしょうか?
人生に危機感を持っている人間は、一つの結論だけで「安心」したりはしません。
それが「間違っていないか」を常に警戒し、反論含め数多くの意見を集めて「比較検討」します。
さらに「比較」する際には「主観的」な感情で判断を下すのでなく、「客観的」な情報で正否を見極めます。
感情的に「好ましい・好ましくない」で判断するのは、平和惚けした人間のすること。
常に緊張感を持って生きている人間に、感情で判断するという選択肢は(趣味の買い物の選択etcでもない限り)そもそも存在しないのです。
…ひょっとすると、日本は平穏な時代が長かったため、危機感の無い人間が多く育ってしまったのかも知れません。
ですが「これから」の時代は、危機感無くフラフラ生きていられるほど安穏とした時代ではないかも知れないのです。
過去記事で、自分は常に「半信半疑」のスタンスで生きている、と書きましたが…
「どんなに信じたい意見でも、最低1%は疑いの余地を持つ」「どんなに否定したい意見でも、最低1%は信じる余地を持つ」――これって「思考の機動力」を保つために必要な考えだと思うのです。
100%肯定または100%否定で思考が固まってしまうと、いざそれが間違っていた時、すぐには動けません。
それともう1つ、自分が心がけていることがあります。
それは「異論を“おもしろい”と思える心を保つ」ことです。
人が自分の意見とは違う「異論」を攻撃しがちなのは、それを「おもしろくない」「憎らしい」と思うからではないでしょうか?
そしてそう思うのは、その異論が自分の意見を「否定」しているように感じるからなのではないでしょうか?
ですが異論は必ずしも、自分の意見を「否定」するものではありません。
それを「弱点の指摘」と捉えるなら、それは「弱点克服のヒント」になります。
それが「思いもしなかった別角度からの意見」であるなら「それを取り入れれば、自分の意見はさらに深みを増す」ということです。
異論は使い方次第で、自分の意見をパワーアップさせるものになるのです。
それを思えば、異論を知るのって「おもしろい」と思いませんか?
…逆に言えば、それを「おもしろい」と思えないのは、その人に異論を上手く取り入れられるだけの「知恵」が無いからなのでしょうね…。
自分は、異論を端から否定するのは「愚か者」だと、子どもの頃から思っていました。
討論番組で他者の意見を遮って自分の意見を押し通そうとする「識者」を「みっともないな」という目で見てきました。
なので、そんな「愚か者」に自分からなりに行く気は無いのです。
まして「愚か者」だと、人生の破滅リスクが上がってしまいますので…。
元から「頭が悪い」ならともかく、高学歴だったり高スペックだったりするにも関わらず、「そうはならんやろ」という「やらかし」や「問題発言」で身の破滅を招いてしまうタイプの人が…。
そういう人々を見るたびに「本当の頭の良さって何なんだろう…?」と疑問に思うのですが…
最近、ふと思いついたことがあります。
それは「『自分にとって“不都合”な意見を受け入れられるか否か』が“知性の分かれ目”なのではないか?」ということです。
自分と「真逆」の意見、自分の主張に「反対」する意見を、とことん拒絶し、あまつさえ「攻撃」する人って、いますよね?
自分は昔から、ソレに疑問を抱いていました。
なぜなら自分にとって大切なのは「自分の意見が通るかどうか」ではなく「何が一番“最良”の答えか」だったからです。
だって、多数決で勝利して自分の意見が通ったとして、それが“最悪”の間違いだった場合、賛成していた人はもちろん、反対していた人まで全員道連れにしての「破滅コース」じゃないですか。
自分にとっての優先事項は、常に「自分がこの世界で生き残っていくこと」でした。
そのためには「自分を生き残らせてくれる答え」こそが必要で、たとえそれが「自分の」意見でなくても構わないのです。
たとえばサバイバルな状況下で、サバイバル知識が全く無い「自分」と、サバイバル知識に長けた「他人」がいたとして――そこで「自分の意見が通らないと気が済まない」なんてワガママを言っていられますか?
…思うに「異論を絶対に認められない人」って、人生において、判断ひとつが生死を分けるような「ギリギリの極限状態」に置かれたことがないのではないでしょうか(いや、そもそもそこに置かれたことのある人の方が少なそうですけど…)?
「自分の選択が間違っていたら、そこで人生ゲームオーバー」という切迫感を味わったことのない、「平和」過ぎる意識の持ち主なのではないでしょうか?
人生に危機感を持っている人間は、一つの結論だけで「安心」したりはしません。
それが「間違っていないか」を常に警戒し、反論含め数多くの意見を集めて「比較検討」します。
さらに「比較」する際には「主観的」な感情で判断を下すのでなく、「客観的」な情報で正否を見極めます。
感情的に「好ましい・好ましくない」で判断するのは、平和惚けした人間のすること。
常に緊張感を持って生きている人間に、感情で判断するという選択肢は(趣味の買い物の選択etcでもない限り)そもそも存在しないのです。
…ひょっとすると、日本は平穏な時代が長かったため、危機感の無い人間が多く育ってしまったのかも知れません。
ですが「これから」の時代は、危機感無くフラフラ生きていられるほど安穏とした時代ではないかも知れないのです。
過去記事で、自分は常に「半信半疑」のスタンスで生きている、と書きましたが…
「どんなに信じたい意見でも、最低1%は疑いの余地を持つ」「どんなに否定したい意見でも、最低1%は信じる余地を持つ」――これって「思考の機動力」を保つために必要な考えだと思うのです。
100%肯定または100%否定で思考が固まってしまうと、いざそれが間違っていた時、すぐには動けません。
それともう1つ、自分が心がけていることがあります。
それは「異論を“おもしろい”と思える心を保つ」ことです。
人が自分の意見とは違う「異論」を攻撃しがちなのは、それを「おもしろくない」「憎らしい」と思うからではないでしょうか?
そしてそう思うのは、その異論が自分の意見を「否定」しているように感じるからなのではないでしょうか?
ですが異論は必ずしも、自分の意見を「否定」するものではありません。
それを「弱点の指摘」と捉えるなら、それは「弱点克服のヒント」になります。
それが「思いもしなかった別角度からの意見」であるなら「それを取り入れれば、自分の意見はさらに深みを増す」ということです。
異論は使い方次第で、自分の意見をパワーアップさせるものになるのです。
それを思えば、異論を知るのって「おもしろい」と思いませんか?
…逆に言えば、それを「おもしろい」と思えないのは、その人に異論を上手く取り入れられるだけの「知恵」が無いからなのでしょうね…。
自分は、異論を端から否定するのは「愚か者」だと、子どもの頃から思っていました。
討論番組で他者の意見を遮って自分の意見を押し通そうとする「識者」を「みっともないな」という目で見てきました。
なので、そんな「愚か者」に自分からなりに行く気は無いのです。
まして「愚か者」だと、人生の破滅リスクが上がってしまいますので…。
PR
ここ最近、夏になると「リチウムイオンバッテリー」の発火事故のニュースを聞きますよね?
でも、リチウムイオンバッテリーが普及し始めた当初、そんな危険性があるなんて言われていましたっけ?
それどころか、スマホや充電可能な小型家電にそれが組み込まれているなんてこと自体、皆さん意識していなかったのではないでしょうか?
同様に、太陽光発電のメガソーラー建設が始まった頃、それが自然破壊や災害に繋がる可能性なんて、誰か言っていましたっけ?
日本中あちこちにそれが出来てしまってから、森林破壊だ、環境破壊だ、豪雨が来れば地滑りだ…なんて騒がれていますよね?
…おそらく、それらが普及し始めた当初も、リスクに気づいていた人は気づいていたでしょうし、情報発信する人はしていたのでしょう。
ですが、それが大々的に報じられることは無く、気に留める人もいなかった…そういうことなのではないでしょうか?
日本人は「新しもの好き」な民族だと言われていますが…
「新しいテクノロジー」と聞くと、皆目の色を変えて持てはやし、リスクやデメリットには目もくれない(考えもしない)…
それどころかネガティブな言説は「水を差すな」とばかりに黙殺する…そんな人が多いのかも知れません。
ですが、物事には何でもメリットとデメリットがあります。
メリットばかりに目が眩んでデメリットを無視すれば、後でその「しっぺ返し」を喰らうのです。
「しっぺ返し」の大きさは、それが普及すれば普及するほど大きくなります。
リチウムイオンバッテリーなんて、もはやに数も把握できない時限爆弾が日本全国(どころか世界中)にバラまかれている状態じゃないですか。
(リチウムイオンバッテリーの中にも、ちゃんと安全性を考えて作られたリスクの少ないものと、そうでないものがあるのでしょうが…。あとは日本の夏の気温上昇が想定外過ぎた…というのもあるのでしょうが…。)
「しっぺ返し」が痛手にならないためには、早い段階でリスクに気づき、それを回避する対策を取ることが必要です。
…ですが「新技術ワッショイ」な人々は、新技術を持ち上げてはしゃぎこそすれ、ネガティブな話題には耳も貸さないんですよね…。
もしかしたらこれは、人生や世の中に対する「危機感」の問題なのかも知れませんが…。
自分は中学に上がるまでの間に「あと三、四歩間違っていたら死んでいた」という目に何回か遭遇しています(一、二歩というほど切羽詰まってはいないものの、下手したら死んでいた状況)。
さらには小一で「ひろしまのピカ」(広島原爆を描いた絵本。トラウマになることで有名)に出逢い「人生一寸先には死があるかも知れない」と学んだため、おそらく人生に対する「危機感」が他人とは違うのでしょう。
(具体的には「選択を誤れば死すら有り得る。判断材料はできる限りかき集めろ」「物事にはデメリットがあると必ず疑え」という心構えですね。フェイク情報も多い現代で、まともな判断材料を集めること自体、至難の業というのはあるのですが…。)
…なので「新しいもの=まだ良いも悪いも分かっていない未知のシロモノ」に対し、ワッショイしかしない人々を不思議に思いさえするのですが…。
あるいは世の人々は「デメリットは国や企業が勝手に何とかしてくれる」と思い込んで“安心”してしまっているのでしょうか?
…ですが、世のニュースを見ていれば、デメリットがバレるまで消費者を欺き、不都合を隠蔽する企業って、普通にあるじゃないですか。
過去の歴史を振り返れば、国ですら信用しきれません。
結局のところ、一人一人の“個人”が危機感を持って、デメリットやリスクを警戒するしか方策は無いのです。
…新技術の欠点や粗が「普及してから」ボロボロ出て来るのは、普及しきってしまえば「目新しさ」は無くなり、目が眩んでいた人々も「目が醒める」からなのかも知れません。
あるいは確率の低いリスクでも、普及して母数が大きくなれば、いずれ必ずどこかで起こる…ということなのかも知れません。
リチウムイオンバッテリーの件は(化学に疎いこともあり)自分もノーマークでしたし、いろいろと反省もあるのですが…
(既にリチウムイオンバッテリー製品をたくさん買ってしまっています…。日本の中でも暑くなりやすい地域なのに…。)
「今」一番気になっているのはAI技術に関することですね。
海外ではAIに感化されて事件を起こした例や、自殺してしまった例が既に出ていますし…
(そもそもAIが人のメンタルや思考力および社会に与える影響は、これから何十年か経過観察してみないと分からないことなのかも知れません…。我々は今まさしく「実験台」にされている状態なのではないかと。後になって「実は無思考廃人を生むものでした」なんてことになったら怖過ぎませんか…?)
AI技術は何もかもが新し過ぎて、取りまとめる業界団体も無ければ規制も間に合っていない状態ですので。
(今はただ開発者の「良心に任せる」というビミョウ過ぎる有様なのではないかと…。一応AI新法で「コンプラは守れ(※超意訳)」みたいなことは書いてありますが、海外の事業者もいる中で、どれだけそれが通用するか…と。)
なお、モバイルバッテリー含め、既に世に出ている製品のリコール情報などは、消費者庁のサイトに結構載っています。
ご心配な方はチェックされると良いのではないかと。
でも、リチウムイオンバッテリーが普及し始めた当初、そんな危険性があるなんて言われていましたっけ?
それどころか、スマホや充電可能な小型家電にそれが組み込まれているなんてこと自体、皆さん意識していなかったのではないでしょうか?
同様に、太陽光発電のメガソーラー建設が始まった頃、それが自然破壊や災害に繋がる可能性なんて、誰か言っていましたっけ?
日本中あちこちにそれが出来てしまってから、森林破壊だ、環境破壊だ、豪雨が来れば地滑りだ…なんて騒がれていますよね?
…おそらく、それらが普及し始めた当初も、リスクに気づいていた人は気づいていたでしょうし、情報発信する人はしていたのでしょう。
ですが、それが大々的に報じられることは無く、気に留める人もいなかった…そういうことなのではないでしょうか?
日本人は「新しもの好き」な民族だと言われていますが…
「新しいテクノロジー」と聞くと、皆目の色を変えて持てはやし、リスクやデメリットには目もくれない(考えもしない)…
それどころかネガティブな言説は「水を差すな」とばかりに黙殺する…そんな人が多いのかも知れません。
ですが、物事には何でもメリットとデメリットがあります。
メリットばかりに目が眩んでデメリットを無視すれば、後でその「しっぺ返し」を喰らうのです。
「しっぺ返し」の大きさは、それが普及すれば普及するほど大きくなります。
リチウムイオンバッテリーなんて、もはやに数も把握できない時限爆弾が日本全国(どころか世界中)にバラまかれている状態じゃないですか。
(リチウムイオンバッテリーの中にも、ちゃんと安全性を考えて作られたリスクの少ないものと、そうでないものがあるのでしょうが…。あとは日本の夏の気温上昇が想定外過ぎた…というのもあるのでしょうが…。)
「しっぺ返し」が痛手にならないためには、早い段階でリスクに気づき、それを回避する対策を取ることが必要です。
…ですが「新技術ワッショイ」な人々は、新技術を持ち上げてはしゃぎこそすれ、ネガティブな話題には耳も貸さないんですよね…。
もしかしたらこれは、人生や世の中に対する「危機感」の問題なのかも知れませんが…。
自分は中学に上がるまでの間に「あと三、四歩間違っていたら死んでいた」という目に何回か遭遇しています(一、二歩というほど切羽詰まってはいないものの、下手したら死んでいた状況)。
さらには小一で「ひろしまのピカ」(広島原爆を描いた絵本。トラウマになることで有名)に出逢い「人生一寸先には死があるかも知れない」と学んだため、おそらく人生に対する「危機感」が他人とは違うのでしょう。
(具体的には「選択を誤れば死すら有り得る。判断材料はできる限りかき集めろ」「物事にはデメリットがあると必ず疑え」という心構えですね。フェイク情報も多い現代で、まともな判断材料を集めること自体、至難の業というのはあるのですが…。)
…なので「新しいもの=まだ良いも悪いも分かっていない未知のシロモノ」に対し、ワッショイしかしない人々を不思議に思いさえするのですが…。
あるいは世の人々は「デメリットは国や企業が勝手に何とかしてくれる」と思い込んで“安心”してしまっているのでしょうか?
…ですが、世のニュースを見ていれば、デメリットがバレるまで消費者を欺き、不都合を隠蔽する企業って、普通にあるじゃないですか。
過去の歴史を振り返れば、国ですら信用しきれません。
結局のところ、一人一人の“個人”が危機感を持って、デメリットやリスクを警戒するしか方策は無いのです。
…新技術の欠点や粗が「普及してから」ボロボロ出て来るのは、普及しきってしまえば「目新しさ」は無くなり、目が眩んでいた人々も「目が醒める」からなのかも知れません。
あるいは確率の低いリスクでも、普及して母数が大きくなれば、いずれ必ずどこかで起こる…ということなのかも知れません。
リチウムイオンバッテリーの件は(化学に疎いこともあり)自分もノーマークでしたし、いろいろと反省もあるのですが…
(既にリチウムイオンバッテリー製品をたくさん買ってしまっています…。日本の中でも暑くなりやすい地域なのに…。)
「今」一番気になっているのはAI技術に関することですね。
海外ではAIに感化されて事件を起こした例や、自殺してしまった例が既に出ていますし…
(そもそもAIが人のメンタルや思考力および社会に与える影響は、これから何十年か経過観察してみないと分からないことなのかも知れません…。我々は今まさしく「実験台」にされている状態なのではないかと。後になって「実は無思考廃人を生むものでした」なんてことになったら怖過ぎませんか…?)
AI技術は何もかもが新し過ぎて、取りまとめる業界団体も無ければ規制も間に合っていない状態ですので。
(今はただ開発者の「良心に任せる」というビミョウ過ぎる有様なのではないかと…。一応AI新法で「コンプラは守れ(※超意訳)」みたいなことは書いてありますが、海外の事業者もいる中で、どれだけそれが通用するか…と。)
なお、モバイルバッテリー含め、既に世に出ている製品のリコール情報などは、消費者庁のサイトに結構載っています。
ご心配な方はチェックされると良いのではないかと。
最近、世の中を見ていて不安になることがあります。
それは「AIを“何でも出来る万能の魔法”のように見ている人が多くないか?」ということです。
たとえばパソコン(初期はマイコンでしたっけ?)やWindowsが世に出た時、当時の人々はそれを「何でも出来る魔法の箱」と思っていたでしょうか?
もし思っていたとしても、やがてはその「限界」に気づいたはずです。
AIはまだ技術的に新し過ぎて、まだその限界も分かっていなければ、メリットやデメリットも充分に議論されていません。
AIにはどんな仕事が向いていて、逆に何が不向きなのか…それさえよく分かっていないのが現状なのではないでしょうか?
なのに世の中は「AI化の波に乗り遅れるな」とばかりに企業を焦らせます。
人手不足、人材不足でDX化、AI化していかざるを得ない、という事情も分かるのですが…
それが本当に「AI化して大丈夫なものなのかどうか」真剣に検討できているでしょうか?
もしAI化に「失敗」すれば、AI化にかかった費用をまるっと損する…どころか、貴重な人材や顧客まで失いかねないことに、ちゃんと気づけているのでしょうか?
たとえば最近の事例で言うと、こども家庭庁が約10億円かけて開発していた“AIによる虐待判定システム”が、6割もの判定ミスを出して「導入見送り」になったことがありました。
大金をかけて開発したAIシステムが、結局実用化できずに終わる…
国でなく民間でこの事態が起きた時、果たして企業運営は無事に済むでしょうか?
あるいは民間の場合は、それが「使えない」ことにも気づかないまま「導入」してしまうことも考えられます。
(大概の場合、AIシステムは「外注」でしょうし、外注先は「良いこと」しか言わないでしょうから…。)
さらにはAI導入により要らなくなった労働力を、早まってリストラしてしまう企業も出て来ることでしょう。
…ですが実際にはAIシステムは「使えない」ものですので、サービスや品質が落ち、顧客離れが進むのです。
自分は(過去記事にも書いた)AmazonロッカーのトラブルでAIチャットを使った時、正直「使えないな」と思いました。
おそらく「よくある質問」のQ&Aコーナーに載っているタイプのトラブルになら対応しているのでしょうが…
滅多にないトラブルにはまるで対応しておらず、結局は「人間の出る」コールセンターと電話する羽目になったからです。
そもそもAI導入者は「AIとは何か?」をちゃんと分かって導入しているのでしょうか?
AIの知能は「学習データ」を元にしています。
学習していないことには答えを出せません(あるいは、いわゆる「ハルシネーション」でデタラメな答えを出してきます)。
「よくあるトラブル」には対処できても「データにないトラブル」に対処できないのは、考えてみれば当たり前の話なのです。
なのにAmazonさんのAIチャットには「そのトラブルは私では対処できかねますのでコールセンターにお繋ぎしましょうか?」という「橋渡し」すらありませんでした。
(ここでまずユーザーの一人である自分は「GAFAの一角なのに、この程度のAI利用しかできないのか…」と心の中で評価を下げたのですが…。もしかしたらAI以前に顧客満足度の意識の問題で開発にお金をかけていないだけ(トラブルなんて滅多に起きないだろうから金かけてられないみたいな?)だったりするのかも知れませんが。)
「埒の明かないAI対応」は、顧客によってはクレームに繋がることでしょう。
コールセンターにクレームを入れるだけならまだしも、今の時代はSNSで悪評を拡散される恐れもあります。
…ですが、そうやって「表に出る」反応なら、ある意味「まだマシ」なのです。
大半の顧客は、失望すれば「物も言わずに」去って行きます。
企業は「文句を言って離れていく顧客」は把握できますが、「何も言わずに去っていく顧客」は把握できません。
いつの間にか業績が下がった時、やっと「何かがおかしい」と気づくだけです。
AI化の失敗に気づき、元の「人の手によるシステム」に戻そうとした時…
今の時代、果たしてリストラしてしまったのと同程度の人材は戻ってくるでしょうか?
今は「人手不足」で「人材の奪い合い」の時代です。
新たに人材を確保しようとするなら、以前よりも高い人件費が必要となる可能性がかなり高いです。
しかも「即戦力」が確保できるかどうかは分からず、また一から人材育成しなければならないかも知れないのです。
…以上のことを考えると「AI化に失敗して倒産する企業」って、今後普通に出て来ると思いませんか?
そうならないためには「焦って時代に合わせようとする」のではなく、「AI化したい事業の性質」と「AIの性質」を改めて見つめ直し「それがAI化に向いているのか否か」をしっかり検討することなのですが…
世の企業経営者の皆さんは、果たして大丈夫なのでしょうか?
AI事業者たちの言う耳触りの良いメリットにばかり踊らされて、冷静な判断ができなくなったりしていないでしょうか?
なお、AIは「学習していないことはできない」だけでなく「誤ったデータを学ばされればミスを犯す」「データの学習の仕方を誤ってもミスをする」ものであること、開発する事業者によりAI精度がピンキリになるであろうこと、海外産のAIに頼る場合は利用料が円相場で変動することなども…皆さん、ちゃんとお気づきですよね?
ネットにあまりにもAI礼賛、AI賛美ばかりが溢れていると、心配になってきてしまうのですが…。
(あと、AIを導入するならフィードバック機能は絶対つけておくべきかと。人間でも「言われないとミスに気づけない」人はいますが、AIだと尚更ですから。)
それは「AIを“何でも出来る万能の魔法”のように見ている人が多くないか?」ということです。
たとえばパソコン(初期はマイコンでしたっけ?)やWindowsが世に出た時、当時の人々はそれを「何でも出来る魔法の箱」と思っていたでしょうか?
もし思っていたとしても、やがてはその「限界」に気づいたはずです。
AIはまだ技術的に新し過ぎて、まだその限界も分かっていなければ、メリットやデメリットも充分に議論されていません。
AIにはどんな仕事が向いていて、逆に何が不向きなのか…それさえよく分かっていないのが現状なのではないでしょうか?
なのに世の中は「AI化の波に乗り遅れるな」とばかりに企業を焦らせます。
人手不足、人材不足でDX化、AI化していかざるを得ない、という事情も分かるのですが…
それが本当に「AI化して大丈夫なものなのかどうか」真剣に検討できているでしょうか?
もしAI化に「失敗」すれば、AI化にかかった費用をまるっと損する…どころか、貴重な人材や顧客まで失いかねないことに、ちゃんと気づけているのでしょうか?
たとえば最近の事例で言うと、こども家庭庁が約10億円かけて開発していた“AIによる虐待判定システム”が、6割もの判定ミスを出して「導入見送り」になったことがありました。
大金をかけて開発したAIシステムが、結局実用化できずに終わる…
国でなく民間でこの事態が起きた時、果たして企業運営は無事に済むでしょうか?
あるいは民間の場合は、それが「使えない」ことにも気づかないまま「導入」してしまうことも考えられます。
(大概の場合、AIシステムは「外注」でしょうし、外注先は「良いこと」しか言わないでしょうから…。)
さらにはAI導入により要らなくなった労働力を、早まってリストラしてしまう企業も出て来ることでしょう。
…ですが実際にはAIシステムは「使えない」ものですので、サービスや品質が落ち、顧客離れが進むのです。
自分は(過去記事にも書いた)AmazonロッカーのトラブルでAIチャットを使った時、正直「使えないな」と思いました。
おそらく「よくある質問」のQ&Aコーナーに載っているタイプのトラブルになら対応しているのでしょうが…
滅多にないトラブルにはまるで対応しておらず、結局は「人間の出る」コールセンターと電話する羽目になったからです。
そもそもAI導入者は「AIとは何か?」をちゃんと分かって導入しているのでしょうか?
AIの知能は「学習データ」を元にしています。
学習していないことには答えを出せません(あるいは、いわゆる「ハルシネーション」でデタラメな答えを出してきます)。
「よくあるトラブル」には対処できても「データにないトラブル」に対処できないのは、考えてみれば当たり前の話なのです。
なのにAmazonさんのAIチャットには「そのトラブルは私では対処できかねますのでコールセンターにお繋ぎしましょうか?」という「橋渡し」すらありませんでした。
(ここでまずユーザーの一人である自分は「GAFAの一角なのに、この程度のAI利用しかできないのか…」と心の中で評価を下げたのですが…。もしかしたらAI以前に顧客満足度の意識の問題で開発にお金をかけていないだけ(トラブルなんて滅多に起きないだろうから金かけてられないみたいな?)だったりするのかも知れませんが。)
「埒の明かないAI対応」は、顧客によってはクレームに繋がることでしょう。
コールセンターにクレームを入れるだけならまだしも、今の時代はSNSで悪評を拡散される恐れもあります。
…ですが、そうやって「表に出る」反応なら、ある意味「まだマシ」なのです。
大半の顧客は、失望すれば「物も言わずに」去って行きます。
企業は「文句を言って離れていく顧客」は把握できますが、「何も言わずに去っていく顧客」は把握できません。
いつの間にか業績が下がった時、やっと「何かがおかしい」と気づくだけです。
AI化の失敗に気づき、元の「人の手によるシステム」に戻そうとした時…
今の時代、果たしてリストラしてしまったのと同程度の人材は戻ってくるでしょうか?
今は「人手不足」で「人材の奪い合い」の時代です。
新たに人材を確保しようとするなら、以前よりも高い人件費が必要となる可能性がかなり高いです。
しかも「即戦力」が確保できるかどうかは分からず、また一から人材育成しなければならないかも知れないのです。
…以上のことを考えると「AI化に失敗して倒産する企業」って、今後普通に出て来ると思いませんか?
そうならないためには「焦って時代に合わせようとする」のではなく、「AI化したい事業の性質」と「AIの性質」を改めて見つめ直し「それがAI化に向いているのか否か」をしっかり検討することなのですが…
世の企業経営者の皆さんは、果たして大丈夫なのでしょうか?
AI事業者たちの言う耳触りの良いメリットにばかり踊らされて、冷静な判断ができなくなったりしていないでしょうか?
なお、AIは「学習していないことはできない」だけでなく「誤ったデータを学ばされればミスを犯す」「データの学習の仕方を誤ってもミスをする」ものであること、開発する事業者によりAI精度がピンキリになるであろうこと、海外産のAIに頼る場合は利用料が円相場で変動することなども…皆さん、ちゃんとお気づきですよね?
ネットにあまりにもAI礼賛、AI賛美ばかりが溢れていると、心配になってきてしまうのですが…。
(あと、AIを導入するならフィードバック機能は絶対つけておくべきかと。人間でも「言われないとミスに気づけない」人はいますが、AIだと尚更ですから。)
個人的に、最近のG○oleさんのAI活用の仕方に失望を覚えています。
なぜなら最近のGo○leさんは「サイトやブログや投稿記事を紹介する」のではなく「そこから拾った情報を要約して提示する」方へ舵を切っているからです。
無料版の方なら一応、勝手に最上部にAI要約は出るものの、元記事へのリンクがあるのでまだマシなのですが(そのリンクもひどく分かりづらいのでちょっとアレなのですが)…
AIモードの方ではリンクも出なくなるという話を聞いています。
(ネット記事を読む限り、ChatGPTのようなAIチャットサービスを目指している印象があるのですが…実際のところどうなんでしょう?正直最初に読んだ時は「自分にしか無い強みを棄てて、わざわざ二番煎じに甘んじようとする意味が分からない」「そこまで思い詰めるほど広告収入が減っているのだろうか」と邪推してしまったのですが…。)
Goo○eさんはソレを「新たな情報検索の形」のように語っていますが…
どうも根本的に、検索者のニーズを「分かっていない」気がしてなりません。
(あるいは検索者本人すら、そのニーズに無自覚なのかも知れませんが。)
だって「検索」って、べつに「情報」だけを求めてするわけではないじゃないですか。
暇な時に、ふらふらウィンドウショッピングをするのを楽しむように、たくさんの情報が並んでいるのをざっと読んで「こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだ」というのを楽しむ時って、ありませんか?
AIによる要約・回答は、検索者から「選ぶ楽しみ」「探す楽しみ」を奪ってしまうのです。
そもそもAI要約・回答が「その人」に合った答えを導き出してくれるとは限りません。
人間の性質や生きる環境は十人十色で、求めている情報も実は細かく違っています。
(IQの高い人ならAIに質問する時点でそのあたりを細かく「条件付け」するでしょうが、「それほどでもない人」はそもそも「万人に通じる答えが存在する」と勘違いしていて、条件設定などしないことでしょう。)
AIはおそらく一番「一般的」な答えを出してくるでしょうが…実はもっとその人に合った「答え」がネット上には他に存在するかも知れないのです。
AIの答えだけで「こんなものか」と諦めてしまう人は、その「答え」に一生気づけません。
検索で出てきたサイトや投稿を直感で選んで読み漁るのって、「時間の無駄」になるリスクもありますが、逆に「思いがけない情報との出逢い」を生んでくれるものでもあります。
「要約」は一見タイパが良いように見えて、「急がば回れ」の「逆」なのです。
(さらに言えば、その「時間の無駄」と「思わぬ掘り出し物」を行ったり来たりするのが面白かったりするのですが…たぶん人生の醍醐味って、そういう所にあるものなんじゃないでしょうか?)
そんなこともあり、自分はAI要約を「お出しされる」たびに「余計なお世話なんじゃい!」と思ってしまいます。
(せめて要約が欲しいかどうか訊いてから出してくれないものでしょうか?そもそも自分はAIの「答え」が合っているかどうか元記事と見比べてファクトチェックするタイプですので、逆に手間なんですよ…。なお、言及記事の少ない事柄については誤答を出すこともある、というのは既に確認済。)
<関連記事:ある猫種を検索してみたら、AIの弱点とその対策にうっすら気づいた。>
そしてそれより何より最悪なのが「AI要約・回答が“人と人との出逢い”を奪ってしまうこと」です。
サイトやブログや記事の紹介なら、検索者が「その知を持った人」と出逢えるのです。
ふと出逢った「鋭い意見」や「独自の視点」にハッとさせられて、その人の過去記事を遡って読んだり、SNSを辿ってみたことってありませんか?
AI要約・回答では、情報は「その場限りで終わり」です。
その「元となった人」に出逢うこともなければ、過去記事に「もっと感動できる言葉」があることも知らないままです。
AIで「元の記事」と切り離された情報は「いもづる式に情報をたどること」を阻害してしまうのです。
自分もそうなので言うのですが…人間って、ただ情報だけを求めているわけではなく、その背後にいる「人間」を求めていたりはしないでしょうか?
その人がその情報を語るに至った「事情」や「物語」を求めていたりはしないでしょうか?
自分は時々X(旧Twitter)や動画サイトで「見知らぬ他人の意見」を読むのが好きです。
時にひどい暴言に胸が痛んだり、無神経な言葉に苛立ったりすることもありますが、それを「要約」で読みたいとは思いません。
なぜなら、AIで加工されていない、その人の「生の言葉」が読みたいからです。
(まぁ、それはあくまで「他人事」に対する意見だから、というのもあるのでしょうが…。あるいは自分が創作活動の糧として、人間のグロテスクな部分をも見たがっているせいかも…。)
「情報検索はAIによる回答だけで良い」と思ってしまっている人は、きっとそういう「人を求める人の気持ち」「人を知りたいと思う人の気持ち」が理解できていないのでしょう。
そして、そういう人が「開発」をしてしまう限り、きっと「人とネットとのつき合い」はどんどん機械的で無味乾燥な「つまらない」ものになってしまうことでしょう。
自分は検索サイトにおけるAI活用の仕方は、むしろ「人と情報(その背後にいる人)とのマッチング」だと思っています。
正直、現時点でも検索サイトの検索性能って、まだまだ不充分だと思いませんか?
ある程度の「あいまい検索」には対応できるようになっても「キーワードも思いつかない」情報って、検索できないじゃないですか。
むしろAIが導入され始めてから「それは求めていない(余計なお世話)」という余分な情報が交ざるようになり、検索性能が劣化している印象すらあります。
情報要約だの何だのを考える前に、まず本分である「検索」を、もっと突き詰めて考えるべきなのではないでしょうか?
そして出来ることならば「検索」が「人から情報を切り離し、人と人との出逢いの機会を失わせるもの」ではなく「人と人とが出逢えるもの」になってくれることを願います。
「人と出逢う」「人を知る」ということは、きっと単に「情報を知る」ことの何十倍、何千倍も価値あるもののはずなので…。
なぜなら最近のGo○leさんは「サイトやブログや投稿記事を紹介する」のではなく「そこから拾った情報を要約して提示する」方へ舵を切っているからです。
無料版の方なら一応、勝手に最上部にAI要約は出るものの、元記事へのリンクがあるのでまだマシなのですが(そのリンクもひどく分かりづらいのでちょっとアレなのですが)…
AIモードの方ではリンクも出なくなるという話を聞いています。
(ネット記事を読む限り、ChatGPTのようなAIチャットサービスを目指している印象があるのですが…実際のところどうなんでしょう?正直最初に読んだ時は「自分にしか無い強みを棄てて、わざわざ二番煎じに甘んじようとする意味が分からない」「そこまで思い詰めるほど広告収入が減っているのだろうか」と邪推してしまったのですが…。)
Goo○eさんはソレを「新たな情報検索の形」のように語っていますが…
どうも根本的に、検索者のニーズを「分かっていない」気がしてなりません。
(あるいは検索者本人すら、そのニーズに無自覚なのかも知れませんが。)
だって「検索」って、べつに「情報」だけを求めてするわけではないじゃないですか。
暇な時に、ふらふらウィンドウショッピングをするのを楽しむように、たくさんの情報が並んでいるのをざっと読んで「こんなのもあるんだ、あんなのもあるんだ」というのを楽しむ時って、ありませんか?
AIによる要約・回答は、検索者から「選ぶ楽しみ」「探す楽しみ」を奪ってしまうのです。
そもそもAI要約・回答が「その人」に合った答えを導き出してくれるとは限りません。
人間の性質や生きる環境は十人十色で、求めている情報も実は細かく違っています。
(IQの高い人ならAIに質問する時点でそのあたりを細かく「条件付け」するでしょうが、「それほどでもない人」はそもそも「万人に通じる答えが存在する」と勘違いしていて、条件設定などしないことでしょう。)
AIはおそらく一番「一般的」な答えを出してくるでしょうが…実はもっとその人に合った「答え」がネット上には他に存在するかも知れないのです。
AIの答えだけで「こんなものか」と諦めてしまう人は、その「答え」に一生気づけません。
検索で出てきたサイトや投稿を直感で選んで読み漁るのって、「時間の無駄」になるリスクもありますが、逆に「思いがけない情報との出逢い」を生んでくれるものでもあります。
「要約」は一見タイパが良いように見えて、「急がば回れ」の「逆」なのです。
(さらに言えば、その「時間の無駄」と「思わぬ掘り出し物」を行ったり来たりするのが面白かったりするのですが…たぶん人生の醍醐味って、そういう所にあるものなんじゃないでしょうか?)
そんなこともあり、自分はAI要約を「お出しされる」たびに「余計なお世話なんじゃい!」と思ってしまいます。
(せめて要約が欲しいかどうか訊いてから出してくれないものでしょうか?そもそも自分はAIの「答え」が合っているかどうか元記事と見比べてファクトチェックするタイプですので、逆に手間なんですよ…。なお、言及記事の少ない事柄については誤答を出すこともある、というのは既に確認済。)
<関連記事:ある猫種を検索してみたら、AIの弱点とその対策にうっすら気づいた。>
そしてそれより何より最悪なのが「AI要約・回答が“人と人との出逢い”を奪ってしまうこと」です。
サイトやブログや記事の紹介なら、検索者が「その知を持った人」と出逢えるのです。
ふと出逢った「鋭い意見」や「独自の視点」にハッとさせられて、その人の過去記事を遡って読んだり、SNSを辿ってみたことってありませんか?
AI要約・回答では、情報は「その場限りで終わり」です。
その「元となった人」に出逢うこともなければ、過去記事に「もっと感動できる言葉」があることも知らないままです。
AIで「元の記事」と切り離された情報は「いもづる式に情報をたどること」を阻害してしまうのです。
自分もそうなので言うのですが…人間って、ただ情報だけを求めているわけではなく、その背後にいる「人間」を求めていたりはしないでしょうか?
その人がその情報を語るに至った「事情」や「物語」を求めていたりはしないでしょうか?
自分は時々X(旧Twitter)や動画サイトで「見知らぬ他人の意見」を読むのが好きです。
時にひどい暴言に胸が痛んだり、無神経な言葉に苛立ったりすることもありますが、それを「要約」で読みたいとは思いません。
なぜなら、AIで加工されていない、その人の「生の言葉」が読みたいからです。
(まぁ、それはあくまで「他人事」に対する意見だから、というのもあるのでしょうが…。あるいは自分が創作活動の糧として、人間のグロテスクな部分をも見たがっているせいかも…。)
「情報検索はAIによる回答だけで良い」と思ってしまっている人は、きっとそういう「人を求める人の気持ち」「人を知りたいと思う人の気持ち」が理解できていないのでしょう。
そして、そういう人が「開発」をしてしまう限り、きっと「人とネットとのつき合い」はどんどん機械的で無味乾燥な「つまらない」ものになってしまうことでしょう。
自分は検索サイトにおけるAI活用の仕方は、むしろ「人と情報(その背後にいる人)とのマッチング」だと思っています。
正直、現時点でも検索サイトの検索性能って、まだまだ不充分だと思いませんか?
ある程度の「あいまい検索」には対応できるようになっても「キーワードも思いつかない」情報って、検索できないじゃないですか。
むしろAIが導入され始めてから「それは求めていない(余計なお世話)」という余分な情報が交ざるようになり、検索性能が劣化している印象すらあります。
情報要約だの何だのを考える前に、まず本分である「検索」を、もっと突き詰めて考えるべきなのではないでしょうか?
そして出来ることならば「検索」が「人から情報を切り離し、人と人との出逢いの機会を失わせるもの」ではなく「人と人とが出逢えるもの」になってくれることを願います。
「人と出逢う」「人を知る」ということは、きっと単に「情報を知る」ことの何十倍、何千倍も価値あるもののはずなので…。
「勝ち馬に乗る」という言葉があります。
いかにも「勝てそう」な、「勢いのあるもの」「優勢なもの」に乗っかって、自分も勝利を得ようとするムーブのことです。
実際、ネットの世界では「今まさに人気のもの」「話題のもの」について言及すれば、それだけで数字が伸びたりしますよね?
なにかと「数値至上主義」な現代、そうやって労せず成果(数値)を得ようとする人が多いのも「時代」なのかも知れません。
でも皆さん、乗ってしまったその「馬」の「本性」を、ちゃんと見極められていますか?
その馬の「行き先」も確かめず、安易に乗っかってしまってはいませんか?
たとえ「ヤバい馬」でも「危なくなったら降りればいい」なんて、簡単に考えてはいませんか?
ですが「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、ネットで発信した情報は、投稿者本人がいくら削除したところで、どこかしらにコピーやスクショされて残ってしまっているものです。
そしてそれは、後々思わぬタイミングで掘り返され、思わぬダメージを生みます。
(問題を起こした有名人がよく過去を掘り返されて「伏線回収」だの何だのと言われていますよね…。)
皆さん、その辺りのことを深く考えずに、ただ「勢いのあるもの」に喰いついてはいませんか?
でも「勢いのあるもの=正しい」というわけではないのが、この世の中です。
自分の知っている一番ヤバいケース(確か初めて知ったのは「映像の世紀」だった気がしますが、番組名をメモしておかなかったため確信はありません)を挙げると…
かつて「ウラン」が発見された際、人々はこの新しく珍しいモノをもてはやし、こぞって「商品」に取り入れていました。
知っての通り、ウランは人体に有害な放射性物質です。
ですが当時はその危険性が人々に知られてはおらず、むしろ「エネルギーを秘めた未知の物質」として魅力的にさえ捉えられていたのです。
ウランを「奇跡のクリーム」として化粧品に取り入れたり、石鹸や軟膏に取り入れたり…
紫外線で照らすと光ることに注目され、ウランを着色料に取り入れた「ウランガラス」が食器に使われたり…
現代人からすればゾッとする、恐ろしい「流行」ですよね。
「流行」や「人気」というものは往々にして、そのものの「本質」や「本性」を知らないまま広まるものなのです。
人間にとって害のあるモノを「人気だから」「今、勢いがあるから」というそれだけで世に広めて、後にその「本質」が発覚したら…
考えるだけでも恐ろしいと思いませんか?
広めた当人は「手のひら返しをしておけば大丈夫」と思っているかも知れませんが…
ネットでの発言は、覚えている人は覚えているものですし、コピーやスクショを取っているものです(そしてふとしたタイミングで「あいつ前に○○って言ってたじゃん」と言ってくるものです)。
(ちなみに自分も、気に入った発言や気になった発言はスクショして保存しておくタイプです。)
何より「勝ち負け」以前の問題で…
乗ったその「勝ち馬」が、まんま「地獄への片道切符」である可能性すらあるのです。
たとえば「フランス革命」も「ナチスによる支配」も、当時の人々の「熱狂」が生んだものです。
ですが、勢いのままに勝ち進んで得られたものは、ギロチンによる恐怖政治と世界大戦でしたよね?
今の時代は「アテンション・エコノミー(目立ったもの勝ちな経済)」と呼ばれています。
誰も彼もが数字を求めて「勢い」に乗りたがる時代です。
だからこそ、そんな「時代」に不安を覚えるのです。
…皆さん、自分の乗ったその馬が、地獄へ通じていないか、ちゃんと考えて乗っていますか?
いかにも「勝てそう」な、「勢いのあるもの」「優勢なもの」に乗っかって、自分も勝利を得ようとするムーブのことです。
実際、ネットの世界では「今まさに人気のもの」「話題のもの」について言及すれば、それだけで数字が伸びたりしますよね?
なにかと「数値至上主義」な現代、そうやって労せず成果(数値)を得ようとする人が多いのも「時代」なのかも知れません。
でも皆さん、乗ってしまったその「馬」の「本性」を、ちゃんと見極められていますか?
その馬の「行き先」も確かめず、安易に乗っかってしまってはいませんか?
たとえ「ヤバい馬」でも「危なくなったら降りればいい」なんて、簡単に考えてはいませんか?
ですが「デジタルタトゥー」という言葉がある通り、ネットで発信した情報は、投稿者本人がいくら削除したところで、どこかしらにコピーやスクショされて残ってしまっているものです。
そしてそれは、後々思わぬタイミングで掘り返され、思わぬダメージを生みます。
(問題を起こした有名人がよく過去を掘り返されて「伏線回収」だの何だのと言われていますよね…。)
皆さん、その辺りのことを深く考えずに、ただ「勢いのあるもの」に喰いついてはいませんか?
でも「勢いのあるもの=正しい」というわけではないのが、この世の中です。
自分の知っている一番ヤバいケース(確か初めて知ったのは「映像の世紀」だった気がしますが、番組名をメモしておかなかったため確信はありません)を挙げると…
かつて「ウラン」が発見された際、人々はこの新しく珍しいモノをもてはやし、こぞって「商品」に取り入れていました。
知っての通り、ウランは人体に有害な放射性物質です。
ですが当時はその危険性が人々に知られてはおらず、むしろ「エネルギーを秘めた未知の物質」として魅力的にさえ捉えられていたのです。
ウランを「奇跡のクリーム」として化粧品に取り入れたり、石鹸や軟膏に取り入れたり…
紫外線で照らすと光ることに注目され、ウランを着色料に取り入れた「ウランガラス」が食器に使われたり…
現代人からすればゾッとする、恐ろしい「流行」ですよね。
「流行」や「人気」というものは往々にして、そのものの「本質」や「本性」を知らないまま広まるものなのです。
人間にとって害のあるモノを「人気だから」「今、勢いがあるから」というそれだけで世に広めて、後にその「本質」が発覚したら…
考えるだけでも恐ろしいと思いませんか?
広めた当人は「手のひら返しをしておけば大丈夫」と思っているかも知れませんが…
ネットでの発言は、覚えている人は覚えているものですし、コピーやスクショを取っているものです(そしてふとしたタイミングで「あいつ前に○○って言ってたじゃん」と言ってくるものです)。
(ちなみに自分も、気に入った発言や気になった発言はスクショして保存しておくタイプです。)
何より「勝ち負け」以前の問題で…
乗ったその「勝ち馬」が、まんま「地獄への片道切符」である可能性すらあるのです。
たとえば「フランス革命」も「ナチスによる支配」も、当時の人々の「熱狂」が生んだものです。
ですが、勢いのままに勝ち進んで得られたものは、ギロチンによる恐怖政治と世界大戦でしたよね?
今の時代は「アテンション・エコノミー(目立ったもの勝ちな経済)」と呼ばれています。
誰も彼もが数字を求めて「勢い」に乗りたがる時代です。
だからこそ、そんな「時代」に不安を覚えるのです。
…皆さん、自分の乗ったその馬が、地獄へ通じていないか、ちゃんと考えて乗っていますか?
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(12/29)
(12/18)
(12/06)
(11/29)
(11/23)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
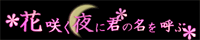
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
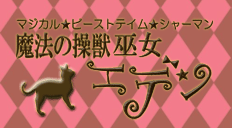
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
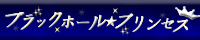
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
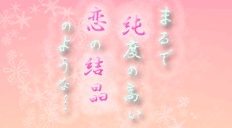
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
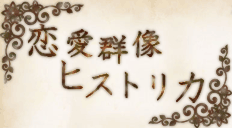
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
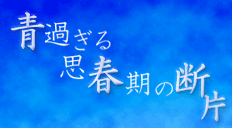
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
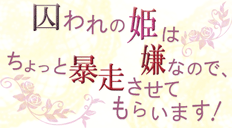
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
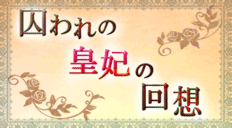
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
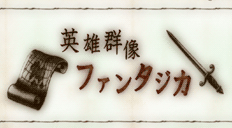
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
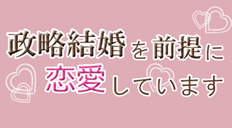
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
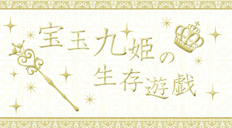
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

