日々ふと思うことを徒然なるままに書き綴る個人的エッセイあるいは回想録。
つい先ごろ、X(旧Twitter)で「X上の画像を自他問わずAI編集できる機能」が実装され、物議を醸していますが…
これ、実はXユーザーだけの問題ではないんですよね。
それどころか、全世界・全人類がAIフェイクの被害者となり得る、あまりにも無責任な機能実装なのですが…
これ、気づかずにやっているとしたら経営者としての想像力が無さ過ぎますし、分かった上でやっているとしたら企業としてのタチが悪過ぎるのですが…
皆さん、ひょっとして、まだこのことには気づいていないのでしょうか?
これ、実はXユーザーだけの問題ではないんですよね。
それどころか、全世界・全人類がAIフェイクの被害者となり得る、あまりにも無責任な機能実装なのですが…
これ、気づかずにやっているとしたら経営者としての想像力が無さ過ぎますし、分かった上でやっているとしたら企業としてのタチが悪過ぎるのですが…
皆さん、ひょっとして、まだこのことには気づいていないのでしょうか?
- 本人がXユーザーでなくとも、Xユーザーに画像UPされてしまえば「終わり」
こういった「悪用されかねない機能」が実装された場合、よく言われるのが「嫌ならそのSNSを出て行けばいいじゃないか」ですが…
今回の機能実装の場合、Xを退会したからと言ってリスクがなくなるわけではありません。
なぜなら、本人がXユーザーでなかったとしても、Xの現役ユーザーに無断・無許可で画像投稿されてしまえば「終わり」だからです。
たとえば時々「有名人がネットに勝手にプライベート写真を載せられた」という炎上事案、ありますよね?
勝手に盗撮された上、それをX上でAIフェイク加工されてしまうとしたら…あまりにもあんまり過ぎやしませんか?
(そもそも有名人なら、ニュースメディアの記事で顔写真が載っている可能性も高いですし…。)
もちろん被害者は有名人に限りません。
ママ友に勝手に子どもの写真を投稿された…という事例も聞いた(読んだ)ことがありますし…
たまたまそこに写り込んでしまっただけの一般人だって、被害者になり得るのです。
それに、展示会などで撮った他者のアート作品、本の表紙や、お気に入りの小物etc…
X上に投稿されたあらゆるモノが、AIフェイクのリスクに晒されます。
それも、当事者のあずかり知らぬところで、いつの間にかフェイク画像を作られかねないのです。
その他にも…Xにはよく、アニメの感想がその場面のスクショ画像と共に投稿されていたりします。
そもそもそのスクショ画像投稿自体が無断・無許可で著作権的にアウトな可能性大なのですが…
これまでは「SNSで盛り上がってくれる分には構わない」ということで、著作権者に「黙認」されてきたところがあるのではないでしょうか?
実写作品やアニメのスクショを使った「大喜利」や、画像つき「ネットミーム」などもそんな感じで「本来ならアウトだけど目をつぶってもらえていた」部分があるのではないでしょうか?
…ですが、そんな版権画像がAIで改変可能だとなったら、どうでしょう?
「もうスクショ画像はUPするな」あるいは「Xに投稿するのだけはやめてくれ」という感じで、規制が厳しくなってしまう可能性もあると思いませんか?
- 法令違反の責任はユーザーに丸投げな企業姿勢
言うまでもない話なのですが、生成AIを間に挟もうと何だろうと、著作権侵害は著作権侵害で、肖像権侵害は肖像権侵害です。
…が、昨今はその種の法令違反の責任を、ユーザー側だけに負わせようとするAI事業者も多いのです。
法律についての知識も無ければ、プラットフォームの利用規定やガイドラインもロクに読み込まない…そんな利用者は、数多いと思われます。
(利用規定やガイドラインって、大概細かい文字がビッッッシリで、読むのが嫌になるものばかりですからね…。いつの間にか改訂されていて、その変更内容を追えていないパターンもありますし…。)
そういう利用者がプラットフォームに新たな機能を見つけたら「これ、使っても良いんだ」「これで何でもやって良いんだ」という誤解をしかねません。
…ですが、例えばそれで著作権侵害が起きたとしても、それは「利用者の責任」「我々は一切責任を負いません」というのが、企業側の姿勢です。
(Xは来年1月に利用規定を改定しますが、そこにそういう姿勢が明示される(ユーザーが責任を負うことがより明確に反映される)予定のようです。)
Xについてもそうですが、動画生成AI「Sora」を有するオープンAI社も著作権侵害に対してはそんな姿勢なんですよね…。
オープンAIはそもそも、ユーザーの法令違反どころか、著作権保護さえ著作権者に丸投げしようとして批判を浴びた過去があります。
Sora2がリリースされた際、著作権がオプトアウト方式という「著作権者が拒否の申し立てをしない限り、著作物をAIで自由に使われてしまう」というシステムが問題となりました。
恐ろしいことにコレ、Sora2の利用者だけの話ではないのです。
全世界の著作物が、拒否申請しない限り「勝手にAI生成動画に使われてしまう」という話だったのです。
(中にはSora2の存在自体「気づいていない」著作権者もいるでしょうに…。)
実際、Sora2ではポケ○ンやドラゴンボー○などの日本のコンテンツも勝手に生成され、各所から批判が出ました。
(そんなこともあり、現在はオプトイン方式に変更されたとか…。)
海外のAI事業者はそんな感じで「これで批判が出ないとでも思ってたのか?」くらいなシステムや機能を平気で出して来ることが多々あります。
日本に住んでいる我々は「企業が出してくれているからには使って良いものなのだろう」「サービスとして世に出ているものなのだから合法で安全なのだろう」と勝手に思い込んでしまっている所があるのではないでしょうか?
ですが海外の企業は日本の企業とは考え方がまるで違います。
「使って良いのだろう」と勝手に思い込んで安易に使うと痛い目を見ます。
(オンラインカジノなども、そんな感じで「使って良いと思っていた」「違法だとは知らなかった」で逮捕されてしまった例も多いと聞きますし…。)
なので、ちゃんと知識を学んで自分で自分を守らなければなりません。
つまりは、法令違反しないための著作権法の学習なども、ユーザーの側が負わなければならないということなのです。
(これが「タダより高いものはない」なんでしょうね…。だから、そこら辺の意識がしっかりしていて「三方よし」な精神を守ってくれる日本企業がAIで覇権を獲ってくれないかと思ってしまうのです…。まぁ最近は国内企業だからと言って安心しきれない部分もありますが…。)
- 性善説前提のシステムなんて、もう無理なのでは?
上の項目を読んでもお分かりかと思いますが…
事業者は「我々は機能をリリースしただけ。悪用されても、悪用する人間が悪いだけ」というスタンスです。
まるで悪用する人間など「ほとんどいない」とでも言いたげな姿勢ですが…
過去の事例を見れば、SNSの悪用事例なんて、AIが浸透する前から既に山ほどあるんですよね…。
大災害が起きた際に災害に関するフェイクニュースが流れたり、被災者を装って助けを求める投稿があったり…
X上でもかなりありましたし、問題にもなりましたので、運営が把握していないとは思えないのですが…
それでも事業者は「悪用されたらとんでもないことになる機能」を平気で世に出すのでしょうか?
今の世の中を見ていると「性善説」…すなわち「人は元々善だから、悪いことなんてしない」を前提としたシステムなんて、もう無理があるように見えます。
…というよりそもそもコレは、性善説を隠れ蓑にした企業側の責任放棄なのではないでしょうか?
自分は一応、大学で法律を学んできた人間ですので「権利と義務は表裏一体」という考えを持っています。
企業として利益を得ておきながら、そのサービスによって生み出される実害は「我関せず」というのは、許されるものなのでしょうか?
サービスを提供するなら、そのサービスが「世にもたらすもの」について、ある程度の責任や義務を負うのは「当たり前」なのではないでしょうか?
…むしろ世の人々は、もっとそこの部分(責任を丸投げされている件)を怒って良いと思うのですが…。
ちなみに、この手の議論でよく言われるのが「包丁だって良いことにも悪いことにも使える」ですが…
日本では6cmを超える長さの刃物って、銃刀法違反でそうそう持ち歩けないんですよね。
猟銃なども免許や保管方法が厳しく法令で決められています。
そういう「危ないモノが危ない目的に使われないように」というルールって、ちゃんと考えられて整備されているのです(それでも防げない事件はありますが…)。
…ですが、AIはまだ技術的に新し過ぎて法律も規制も間に合っていません。
今のAI事業者たちのやり口って、そういう「ルールが間に合っていない」ことを逆手に取った「暴走」なんですよね…。
こんな事業者ばかりが覇権を争い合っているAI業界って、本当に何だか嫌になるんですが…。
- AI改変機能がある限り「X上の画像はとりあえず全て疑ってかかる」が原則になる
上でも書いたSora2では、あまりにもリアルなフェイク動画が作れてしまうことも問題となっています。
一応ロゴは出るのですが、ずっと出続けるわけでも、そこまで目立つわけでもなく、加工で消されてしまっている例すらあります。
そもそもSora自体を知らない人にとっては、そのロゴだけでAIだと気づくこともできないため、いろいろと問題なのです。
そんなこともあって、近頃はAIでのフェイク動画/画像に嫌悪感や拒否感を持つ人も増えている印象があります。
…それはそうですよね。
本物だと思って信じていたら「実は存在しなかった」って…普通に「騙された」と、ネガティブ感情を抱く案件じゃないですか。
個人的なことを言わせてもらえば、自分は「リアルに存在する猫」を愛でたいのであって、どんなに可愛く利口な猫でも「存在しない猫」を愛でさせられたくはないのです。
存在しない猫を一瞬でも「わ~、可愛いネコチャン♪」などと思ってしまった日には、その感情の行き場がなくなり、どうにもならないモヤモヤばかりが残ってしまうのです。
(最初から存在しないと分かりきっている「あきらかCGな猫」や「アニメやイラストな猫」は当然、話が別です。)
…で、話を戻してXの件ですが…
Xの件の新機能は、そんなAI画像を、お手軽に作れてUPできてしまう機能です。
(しかも、自分の画像だけでなく、他人の画像も使えてしまう点がタチが悪すぎるのです。)
つまりは今後、X上には相当数のAIフェイク画像が溢れてしまう可能性がある、ということです。
AIフェイクは悪用だろうと悪用ではなかろうと、見る人を混乱させる可能性が高いシロモノです。
うっかりそれを「本物」だと信じてしまうと、痛い目に遭いかねないのです。
(AIで「盛りに盛った」人物画像や商品画像を「リアル」と勘違いした後、本物を見てガッカリ…というパターンは出てくるでしょうし…。上でも書いたように「勝手にUPされた有名人の画像」も加工できてしまうとなると、既に問題となっているような「有名人を使った詐欺広告」も簡単に作れてしまうわけです。)
今後、X上に上がっている画像はとりあえず、一旦全て疑ってかからなければならないのかも知れません。
…これも事業者がユーザーに押しつけている「責任」なのかも知れませんね。
正直、こんな企業姿勢という時点で、見限る理由が山ほどあるのですが…
そろそろ本気でX離れを考えてみる時期なのでしょうか…?
PR
このまま行くと、AIの進化は確実に止まる――自分がそう危惧しているのには、理由があります。
それは、多くのAI事業者が利用者を「囲い込む」ことに夢中になり、AIの「外」に人を送り出していないからです。
…と、ここまで言っても、多くの人々は「それで何故AIの進化が止まるのか」ピンと来ないことでしょう。
下手をするとAIを運営する「事業者」ですら、そこへの想像が働いていないのかも知れません。
…だって、そこの想像力が真っ当に働くなら、こんなあからさまな「自滅行動(消極的な自殺行為)」を取っているはずがありませんので…。
それは、多くのAI事業者が利用者を「囲い込む」ことに夢中になり、AIの「外」に人を送り出していないからです。
…と、ここまで言っても、多くの人々は「それで何故AIの進化が止まるのか」ピンと来ないことでしょう。
下手をするとAIを運営する「事業者」ですら、そこへの想像が働いていないのかも知れません。
…だって、そこの想像力が真っ当に働くなら、こんなあからさまな「自滅行動(消極的な自殺行為)」を取っているはずがありませんので…。
- どんなにAI精度が進化しても、学ぶべき情報が無ければ意味が無い
どうにも皆さん「AI」と言うと「半導体」ですとか「データセンター」ですとか「AIモデル」ですとか、ハード面やシステム面の進化や精度ばかり気にしているようですが…
そもそもAIって「情報」を「深層学習」することによって進化しているものですよね?
AIそのものの精度をどれほど上げたところで、学ぶべき「情報」が存在しないなら、まるで意味が無いはずなのですが…
なぜか昨今のAI事業者たちは、その情報源を「減滅させる」方向に動いています。
皆さんもご存知の通り、昨今の大手AI事業者は「ネット上の情報」を学習させることでAIの開発コストを抑えているのですが…
そうやって出来上がったAIは、情報源から得た情報を「要約」して出しはするものの、情報源へのリンクを出さなかったり、出しても目立たせなかったりして、利用者をAIの「外」へ出さないように「囲い込んで」います。
(なお、AI事業者は情報源への正当な対価を支払っていないことでも度々問題(訴訟)になっています。某検索サイトGのAIモードがEUから競争法違反の疑いで調査されていたり…。)
実際、国内での某検索サイトG経由のサイト訪問は、ここ2年で33%も減少しています。
実はこれ、AI学習の「情報源の崩壊」の一歩手前な状況なのですが…
このまま行くと数年後にはAIの学習すべき情報が枯渇するか、あったとしても相当に質の低いものばかりになり、AIの存在意義自体が危ぶまれることになりかねないのですが…
皆さん、本気でこの状況の意味するものに気づいていないのでしょうか???
- サイトやブログは訪問者あってのもの
日本には質の高い情報を提供してくれるサイトやブログがたくさんあります。
それは決して「大手」のマスコミや企業のものばかりでなく、中小企業や個人のものでさえ、きめ細やかな「お役立ち情報」を出してくれています。
実際自分も、冠婚葬祭の折、ブライダル事業者や葬儀社のサイトにどれだけ助けてもらったか知れません。
でも、この種の「お役立ち情報」…べつに「ボランティア」で提供されているわけではないのです。
もちろん「世の役に立とう」という意識はあるでしょうが、その最大の目的は「その情報によって人を呼ぶこと」。
サイトやブログに人を集めることが目的なのです。
たとえ受注につながらない遠い地方からの閲覧だとしても、訪問者数が増えれば評価が上がり、検索上位表示される可能性が上がります。
そうやって利用者と情報提供者のWin-Winの相互利益関係で回っていたのが、今までのネットの世界だったのです。
ですがAIの登場は、この関係性を崩します。
皆が皆AI回答やAI要約だけで満足して、サイトやブログに行かなくなってしまったら…
わざわざ時間と手間をかけてネットに情報提供しても、何の意味もなくなってしまいますよね?
ビジネス系サイトのみならず、個人の趣味のサイトも同様です。
HPやブログ、動画サイトなどで様々な趣味のノウハウを紹介してくれている方は多いですが…
どれもこれも「見てくれる人がいるから続けていられる」のではないでしょうか?
苦労して記事や動画をまとめてUPしても、見てくれる人もなく、反応も無い…そんな状況が続けば、心が折れてやめてしまう人も多く出て来るのではないでしょうか?
(さらには自分のUPした「人のためになる情報」をAIに「横取り」されて、得られるはずだった「反応」も「報い」も全て持って行かれていると知ってしまったら、絶望以外の何ものでもありませんよね?)
AIがユーザーを囲い込んでネットへの流入を阻めば阻むほど、ネットは不活性化し、有益な情報がどんどん消えていきます。
いわばAI事業者がやっていることは「立派なダムを作って水を貯めたけれど、水源を枯らそうとしている」行為なわけですが…
…本当に何故、こんな自滅行動に走っているのでしょう?
そもそもAIユーザーの何割かは「ネットで集客するためのコンテンツをAIで作りたい」という人々でしょうが…
AIで優れたコンテンツを作れたところで、そのコンテンツへの集客自体をAIによって阻まれてしまうなら、何の意味もないですよね?
むしろ、ただ無駄にAIに時間(あるいは利用料も)を取られただけになってしまいますよね?
広告主に「AIモードができてもサイトへのトラフィックは減りませんから大丈夫ですよ」的なことを言っておきながら、実際ガッツリ流入を減らしている某検索サイトといい、どうしてAI事業者って、そういうことをするんでしょうね?- 真っ当な事業者は「持続可能性」を求める
もしかしたらAI事業者は「AIに必要な情報は既に得た。あとは用済みだ」とでも言うつもりなのかも知れませんが…
それだとAI開発当時のネット情報を永遠に擦り続けるばかりで、時代に合わせたバージョンアップもできません。
(世の常識やマナーは時代によって変化していくものです。新しい情報が得られなければ、AI回答は古い情報のままで「いつの時代の話?」ということになってしまいます。)
あるいはAI事業者は「どれだけ水源を荒らそうと、どこからか水は湧き出るものさ」と楽天的な考えでいるのかも知れませんが…
その「水」が「以前と同じ質」とは限りません。
むしろ「AI生成コンテンツ」ばかり増えて「既にAIが知っている情報」をAIが「再学習」するという、新たなフェーズの「AI狂牛病(モデル自食症:Model Autophagy Disorder)」が発生するだけかも知れません。
今ならまだ、確実に質が高いと分かっている情報源を、確実に守ることができるのに…
わざわざそれを潰して、質がどうかも分からない、湧き出るかも分からない「次」に期待するなんて、あまりにも非合理的です。
…この非合理的な企業姿勢を見てふと思ったのが「もしかして、海外に寿命の長い企業が少ないのは、そういうことだったのか?」ということでした。
たとえば日本の企業は、山から木を伐採した分、また新たな苗木を植えて森を育てたりしますよね?
木を伐るだけ伐ってそこで「おしまい」ではなく、この先もずっとそれを続けられるよう、持続可能なサイクルを作っているのです。
海外のビジネス事情には詳しくありませんが、そういう考えを持っている企業って、海外では少ないのでしょうか?
目先の利益を取るだけ取って、数年後の自分たちの首を自分で締めて破滅しても「時代の流れが悪かった」で終わりなのでしょうか?
その数年後の破滅を回避するために「今」できることがあるのに…
そこに想像を働かせ行動しようという意識を、まるで持っていないのでしょうか?
- AIとネット文化が「共存」する道は普通にある
AIの進化を止めず、ネット文化の衰退も防ぐ…その方法は、普通に存在します。
言うまでもないことですが…AIがむしろ積極的に、ネットの各サイト・ブログへの人の流出を推し進めれば良いのです。
いわば、これまでの検索サイトの「上位互換」になれば良いわけですが…
これが出来ていないのって、AI事業者が「そんなことをしたらAIの利用時間が減るじゃないか!」「AIに人が戻って来なくなったらどうする!?」と過剰に身構えてしまっているからなのでしょうか?
…それでAIの進化が止まって使い物にならなくなったら本末転倒なのですが…
人ってそこまでして、他者に利益を持たせたがらないものなんですかね??
自分だけが利益を独占して、結果それで首が回らなくなっても良いのでしょうか??
むしろ、AIとネットの各サイト・ブログとの間にWin-Winな相互利益関係が生まれれば、どちらも共に寿命を延ばしていけるはずなのですが…。
AI事業者が閉ざそうとしているものは、もしかしたらAIの未来のみならず、人類そのものの未来なのかも知れませんよね…。
ちなみに、AI事業者によるコンテンツの無断学習&利用問題については、最近ニュース記事で見たKDDIとGoogle Cloudの戦略提携の話が、個人的に気になっています。
予め許諾を得たコンテンツを生成AIへ提供し、それをユーザーが使えば収益が分配される仕組みを想定しているようですが…。
記事の内容だけでは、その仕組みで「どこまで」のコンテンツ提供者をカバーできるのかは分かりませんでしたが…。
「AI生成物」と「そうでないもの」を見分けるために、AI生成物には特定の「印(マーク)」を付けるべき…
今さらここで言わずとも、既に有識者によって散々言われてきたことなのですが…
なぜそれが必要なのか、少し考えれば分かりますよね?
…そうしないと、フェイクをうっかり信じてしまう人が多発して、世の中が大混乱するからです。
生成AIの精度が向上すれば、もはやAI生成画像(動画)と「そうでないもの(オリジナル)」を区別するのは不可能とさえ言われていますが…
それ、普通に困りますよね?
日常で当たり前に目にする画像や動画を、いちいち「これは本物、これは実在しないフェイク」と判断していかなければならないって…
普通に「生活が困難になる」レベルじゃないですか。
しかもフェイクは「熊が出た」「政治家がこんな発言をした」という、生命の危機に関するものや、政治判断を左右するものにまで及んでいます。
(あるいは「この動物は人が平気で触れるほど安全な生き物」という誤解を生んでしまう「間接的に人の命を脅かす」動画など。)
昨今「本物と見分けがつかないフィッシングサイト」や「より巧妙な迷惑メール」が急増しているのも、生成AIの精度向上と無関係とは思えません。
(ロマンス詐欺や「なりすまし」にもAIのディープフェイクが使われたりしていますし…。)
AIで造られたものが「本物と区別できない状態」は、社会の混乱や犯罪を招くのです。
さらに言えば、大人でも混乱するこの状況…
まだ現実とフィクションの区別もつかない幼い子どもには、なおさら「悪影響」を及ぼすリスクがあります。
(実際、スペインの大学では動物動画のフェイクが子どもに及ぼす影響の研究が行われています。)
…これ、一定以上の知能がある方なら、誰でも気づくことかと思うのですが(さらに言えば、既に世の中がこの状態で、気づかない人がいるとも思えないのですが)…
何故AI事業者は、未だにAI生成物に「そうと分かる印」を入れないのでしょう?
「たとえ入れたところで、その印を加工で消されてしまえばそれまでだ」という考えもあるかと思いますが…
その「加工して消さなければ使えない」という「一手間」が加わるだけでも、悪戯や犯罪の何%かは低減させられるはずなのです。
(犯罪予防のポイントの1つは、相手に「面倒くさい」と思わせることですので。「生成AIに頼めば、その印も一瞬で消されてしまう」という懸念もありますが、AI事業者なら「どんなプロンプトを与えられても消せない印」をAIに仕込むことも可能なのでは?)
実を言うと、最近出た某O社の生成動画アプリ「Sora(2)」では、生成した動画にロゴが埋め込まれるようになりました。
最初にネットニュースの記事でこれを読んだ時は個人的に「やっとか…」と思い、多少はAI事業者を「見直す」気になったのですが…………
このロゴの出方、思ったのと違っていました。
てっきり画面のどこかに「ずっと」ロゴが出ているものだとばかり思っていたのですが…
このロゴ、一定時間で消えてしまう上、半透明なので動画によっては目立ちません。
最初から出ているわけでもありませんし、サムネイルにもロゴが載っていないことがあります。
…そもそも出ているロゴが「Sora」というアプリの名前だけなんですよ…。
自分も実際にリリースされるまでは「アプリの名が入っていれば大丈夫だろう」と思っていたのですが、認識が低過ぎました…。
YouTubeなどのコメント欄を読んで初めて気づいたことなのですが…
「アプリの名」で「AIか否か」を区別できるのは「そのアプリを認知している人だけ」なのです。
AIにそれなりの興味を持って情報収集している人間なら「Sora?ああ、あのAI動画が作れるやつか」となるでしょうが…
そうでもない一般の人々にとって、その名はまだそれほど認知度の高いものではないのです。
なので、ロゴを入れるとしたら「AI Movie ○○」「AI Picture ○○」のように、アプリ名とともに「AIであることが分かる文言」を入れるべきだったのでしょう。
(ついでに言うと、どうせ一定時間でロゴが変化するなら、ロゴの表示場所が何秒かごとに変わる(そしてずっとどこかしらに出続けている)とかだと、加工で印を消すのが面倒くさくなって良いのでは?)
…ただ、まぁ……入れるようになっただけでもだいぶ「マシ」ではあるので、そこは大いに評価したい所ですが…
他の「何もしていない」AI事業者は、フェイクが世の中を害するこの状況を、どう思っているのでしょう?
「印を入れる」の他にも「AIならではの特徴づけをする」など、対策の立てようはいくらでもあるはずです。
なのに、利益を得るだけ得ておいて、社会に生まれる損失は見て見ぬフリをする…それって、許されることなのでしょうか?
「悪用する側が悪い」という理屈はあるとしても、事業者がその悪用に何の「予防策」も打たない理由にはならないじゃないですか。
この問題を思うたびに「あれ?PL法ってアメリカ発祥じゃなかったんだっけ?アメリカって『それを作った者にはそれなりの責任がある』っていう考えの国じゃなかったんだっけ?」と不思議に思うのですが…
(現在AI事業者の有名どころは、大体アメリカの企業なんですよね…。)
…まぁ、アメリカも最近いろいろ変わってきていますからね…。
利益は巻き上げられるだけ巻き上げておいて、まき散らされる混乱は「知らんぷり」っていうのが、最近のスタンスなんですかね…??
さらに不思議なのは、この事態に対して一般企業および一般の人々がほとんど声を上げていないことなのですが…
(AI生成の詐欺メールや偽サイト、フェイク情報によるデマで迷惑している企業さんも相当数いらっしゃるでしょうに…。)
皆さん、この事態を放置しているAI事業者に対して、何も思うところは無いのでしょうか?
自分は正直、不信感を持っていますし「社会的責任に対する意識が低いのでは?」と思っています。
…あるいは低いのは、「自社サービスが世の中に与える影響」に対する「想像力」の方なのかも知れませんが…
どちらにせよ、こんな姿勢の事業者にAI業界の覇権を取ってもらいたくはありません。
ユーザーには利用するAIを選択する自由があります。
あるいは「選択する余地も無い」ほど無責任なAI事業者しかいなかったとしても…
そこに対して声を上げ、改善を求める(改善されない限りは利用しない)自由があります。
そしてそれは、未来に対する「選択」でもあるのです。
フェイク含むAIの「悪用」に対し何の対策も取らない事業者と、ちゃんと取り組む事業者…
「どちらを選ぶかで、人類の未来は変わってくる」と言っても過言ではないのです。
皆さん、無料だとか利便性だとか、そんな部分ばかりでAIを選んでいるかも知れませんが…
ぶっちゃけ、そんなものより「もっと重要なもの」があるのです。
目先の安さや便利さと引き換えに、平穏に暮らせるはずだった未来を永遠に喪う(AI犯罪だらけの未来を生んでしまう)とか…割に合わないにもほどがあるじゃないですか。
今さらここで言わずとも、既に有識者によって散々言われてきたことなのですが…
なぜそれが必要なのか、少し考えれば分かりますよね?
…そうしないと、フェイクをうっかり信じてしまう人が多発して、世の中が大混乱するからです。
生成AIの精度が向上すれば、もはやAI生成画像(動画)と「そうでないもの(オリジナル)」を区別するのは不可能とさえ言われていますが…
それ、普通に困りますよね?
日常で当たり前に目にする画像や動画を、いちいち「これは本物、これは実在しないフェイク」と判断していかなければならないって…
普通に「生活が困難になる」レベルじゃないですか。
しかもフェイクは「熊が出た」「政治家がこんな発言をした」という、生命の危機に関するものや、政治判断を左右するものにまで及んでいます。
(あるいは「この動物は人が平気で触れるほど安全な生き物」という誤解を生んでしまう「間接的に人の命を脅かす」動画など。)
昨今「本物と見分けがつかないフィッシングサイト」や「より巧妙な迷惑メール」が急増しているのも、生成AIの精度向上と無関係とは思えません。
(ロマンス詐欺や「なりすまし」にもAIのディープフェイクが使われたりしていますし…。)
AIで造られたものが「本物と区別できない状態」は、社会の混乱や犯罪を招くのです。
さらに言えば、大人でも混乱するこの状況…
まだ現実とフィクションの区別もつかない幼い子どもには、なおさら「悪影響」を及ぼすリスクがあります。
(実際、スペインの大学では動物動画のフェイクが子どもに及ぼす影響の研究が行われています。)
…これ、一定以上の知能がある方なら、誰でも気づくことかと思うのですが(さらに言えば、既に世の中がこの状態で、気づかない人がいるとも思えないのですが)…
何故AI事業者は、未だにAI生成物に「そうと分かる印」を入れないのでしょう?
「たとえ入れたところで、その印を加工で消されてしまえばそれまでだ」という考えもあるかと思いますが…
その「加工して消さなければ使えない」という「一手間」が加わるだけでも、悪戯や犯罪の何%かは低減させられるはずなのです。
(犯罪予防のポイントの1つは、相手に「面倒くさい」と思わせることですので。「生成AIに頼めば、その印も一瞬で消されてしまう」という懸念もありますが、AI事業者なら「どんなプロンプトを与えられても消せない印」をAIに仕込むことも可能なのでは?)
実を言うと、最近出た某O社の生成動画アプリ「Sora(2)」では、生成した動画にロゴが埋め込まれるようになりました。
最初にネットニュースの記事でこれを読んだ時は個人的に「やっとか…」と思い、多少はAI事業者を「見直す」気になったのですが…………
| 正直、AI事業者は安全問題やプライバシー問題や著作権問題等々、何かと後手に回っていて「何かあって余所から文句を言われないと動かない」イメージがあります。 なので、個人的には信頼性など微塵も感じたことはありません。 そこら辺の意識が「ちゃんとした」安心安全な国内企業が出て来て覇権を取ってくれないものかと、常日頃から思っているくらいです。 …そもそも海外産のAIに依存すること自体、いろいろリスクがありますし…。 |
このロゴの出方、思ったのと違っていました。
てっきり画面のどこかに「ずっと」ロゴが出ているものだとばかり思っていたのですが…
このロゴ、一定時間で消えてしまう上、半透明なので動画によっては目立ちません。
最初から出ているわけでもありませんし、サムネイルにもロゴが載っていないことがあります。
…そもそも出ているロゴが「Sora」というアプリの名前だけなんですよ…。
自分も実際にリリースされるまでは「アプリの名が入っていれば大丈夫だろう」と思っていたのですが、認識が低過ぎました…。
YouTubeなどのコメント欄を読んで初めて気づいたことなのですが…
「アプリの名」で「AIか否か」を区別できるのは「そのアプリを認知している人だけ」なのです。
AIにそれなりの興味を持って情報収集している人間なら「Sora?ああ、あのAI動画が作れるやつか」となるでしょうが…
そうでもない一般の人々にとって、その名はまだそれほど認知度の高いものではないのです。
なので、ロゴを入れるとしたら「AI Movie ○○」「AI Picture ○○」のように、アプリ名とともに「AIであることが分かる文言」を入れるべきだったのでしょう。
(ついでに言うと、どうせ一定時間でロゴが変化するなら、ロゴの表示場所が何秒かごとに変わる(そしてずっとどこかしらに出続けている)とかだと、加工で印を消すのが面倒くさくなって良いのでは?)
…ただ、まぁ……入れるようになっただけでもだいぶ「マシ」ではあるので、そこは大いに評価したい所ですが…
他の「何もしていない」AI事業者は、フェイクが世の中を害するこの状況を、どう思っているのでしょう?
「印を入れる」の他にも「AIならではの特徴づけをする」など、対策の立てようはいくらでもあるはずです。
なのに、利益を得るだけ得ておいて、社会に生まれる損失は見て見ぬフリをする…それって、許されることなのでしょうか?
「悪用する側が悪い」という理屈はあるとしても、事業者がその悪用に何の「予防策」も打たない理由にはならないじゃないですか。
この問題を思うたびに「あれ?PL法ってアメリカ発祥じゃなかったんだっけ?アメリカって『それを作った者にはそれなりの責任がある』っていう考えの国じゃなかったんだっけ?」と不思議に思うのですが…
(現在AI事業者の有名どころは、大体アメリカの企業なんですよね…。)
…まぁ、アメリカも最近いろいろ変わってきていますからね…。
利益は巻き上げられるだけ巻き上げておいて、まき散らされる混乱は「知らんぷり」っていうのが、最近のスタンスなんですかね…??
さらに不思議なのは、この事態に対して一般企業および一般の人々がほとんど声を上げていないことなのですが…
(AI生成の詐欺メールや偽サイト、フェイク情報によるデマで迷惑している企業さんも相当数いらっしゃるでしょうに…。)
皆さん、この事態を放置しているAI事業者に対して、何も思うところは無いのでしょうか?
自分は正直、不信感を持っていますし「社会的責任に対する意識が低いのでは?」と思っています。
…あるいは低いのは、「自社サービスが世の中に与える影響」に対する「想像力」の方なのかも知れませんが…
どちらにせよ、こんな姿勢の事業者にAI業界の覇権を取ってもらいたくはありません。
ユーザーには利用するAIを選択する自由があります。
あるいは「選択する余地も無い」ほど無責任なAI事業者しかいなかったとしても…
そこに対して声を上げ、改善を求める(改善されない限りは利用しない)自由があります。
そしてそれは、未来に対する「選択」でもあるのです。
フェイク含むAIの「悪用」に対し何の対策も取らない事業者と、ちゃんと取り組む事業者…
「どちらを選ぶかで、人類の未来は変わってくる」と言っても過言ではないのです。
皆さん、無料だとか利便性だとか、そんな部分ばかりでAIを選んでいるかも知れませんが…
ぶっちゃけ、そんなものより「もっと重要なもの」があるのです。
目先の安さや便利さと引き換えに、平穏に暮らせるはずだった未来を永遠に喪う(AI犯罪だらけの未来を生んでしまう)とか…割に合わないにもほどがあるじゃないですか。
文字だけのメディアは「感情」が伝わらない・分からない(なので誤解を生む)…これって、よく言われることですよね?
だからメールに絵文字があったり、L○NEにスタンプがあったりして、感情を「補完」するのでしょうけど…
そういう「補完」の一切無い文章って「感情が分からない」どころか「ネタなのかガチなのか?」すら区別できない時がありませんか?
特にX(旧Twitter)などの短い文章だと、内容も端的過ぎて「え?これ、ネタで言ってるだけだよね?本気 でそう思ってるわけじゃないよね?」というものが多々あります。
ネタで「おかしなこと」を言っている分には、おもしろがるなり、「ネタとしてはサムいな…」とビミョウな気持ちになるなりすればいい話なのですが…
ガチだとしたら「笑えない」…そんな投稿が、最近はよく目につく気がします…。
最近は「読書離れ」「活字離れ」が深刻ですが…
「本」というのは、単に「知識」を得るためのものではなく「他者の気持ちや視点を学ぶ機会」でもあるんですよね…。
それを失った人々の「精神的視野」が狭くなり、短絡的な物の見方しかできなくなっている…というのは、普通にあり得そうな話です。
さらに言うと、その肝心な「本」を含む「コンテンツ」も、どんどん単純化・エンタメ至上主義化し、いわゆる「考えさせ系」が減っているような気がします。
そんな現代事情を考えれば、本当に「ガチでおかしなことを言っている」人が増えても、不思議ではないのかも知れません。
…「ガチでおかしなことを言っている人」の何が怖いかって…普通に社会を悪化させそうな所なんですよね…。
「自分さえ良ければ他人がどうなっても構わない」という、極度の「自己中心的」思考…
「バレなければ犯罪を犯しても良い」とすら思っている「反社会的」思考…
「自分の言動がどんな結果をもたらすのか」まるで考えない「無責任」思考…
そんな人々が人類の「多数派」になってしまったら、普通に社会秩序が崩壊しますよね??
そもそも「おかしい」のが、それを「心の中だけに収めておく」こともせず、「堂々と公言」しているところなのです。
現代ではもはや「悪いことは隠れてやる」すら通用していないのか…と、世の人々の正気を疑ってしまうのですが…。
(そもそも「悪いことを悪いことと認識する能力」すら失われているのか…。それはそれで恐ろし過ぎるのですが…。)
ひょっとしたら「こんな悪いことを考えてるのは自分一人だけじゃないはずだ。お前らだって考えたことあるだろう」みたいな感じで「仲間集め」をしたいのかも知れませんが…
そんな感じで「悪い仲間」がどんどん増えていったら、やっぱり社会秩序崩壊じゃないですか。
イメージで言うと、どこぞの終末世界のように、文明の崩壊した荒野で悪者たちが「ヒャッハー!」する世界になってしまうじゃないですか。
そんな世界で、どれだけの人間が生き残っていけると思うのでしょう???
今はネットの中で「他人を足蹴にしてでも成り上がってやんぜ」とイキっている人たちだって、本当の崩壊社会に放り込まれたら、もっと悪くて暴力的な輩に一瞬でプチッと潰されて終わりじゃないですか??
自分は平穏な世界で幸せに暮らしていきたい人間ですので、わざわざ「悪い思考」「自分がカモにされるための思考」を世に拡散させたいとは思わないのですが…
…ひょっとして、そんなこと(自分の吐いた毒が、巡り巡って自分自身を蝕む)にすら気づいていないアレな人々が、今の時代は多いのでしょうか?
「これをガチで言っているのだとしたら、今の時代の人間って、どうなってしまっているのだろう?」――そんな不安に押し潰されそうになっているのは、きっと自分だけではないのでしょう。
昨今ネットでの「炎上」や「叩き」が過激化しがちなのは、おそらくはそんな「不安」や「恐怖」の裏返しなのではないでしょうか?
「この失言をガチで言っているのだとしたら、恐ろし過ぎる。今のうちに潰しておかなければ、我々の未来が脅かされる」――そんな神経過敏な不安感が、「やらかした人」への「叩き」をエスカレートさせてしまうのではないでしょうか?
…ただ、忘れてはいけないのは「その人の“真意”がどうなのかは、結局“他人”には分からない」ということです。
ほんの「ネタ」でつぶやかれたものを「ガチ」に受け取り過ぎて「炎上」するのは、双方ともに不幸なことです。
(…まぁ場合によっては、「それをネタにする時点で不謹慎」というケースもあったりするわけですが…。)
さらに言えば、ネットで発言しているのは、あくまで「ネットで発言できるだけの神経の持ち主」「ネットで発言できるだけの時間的余裕のある人」だけです。
それが人類の「全て」なわけではありません。
むしろ沈黙する多数派 の逆のラウド・マイノリティー…「声がデカいだけの少数派」の可能性が高いのです。
(実際、芸能人の冤罪ねつ造事件の「元」を辿ったら、フェイク情報を流していたのはたった3人のユーザーだった…なんて事案もありましたよね。)
なので、ネットで「おかしな発言をしている人」がやたら目につくからと言って、そこまで過敏に怯える必要は無い…
…と、言いたいところなのですが…
問題は、そんな「おかしな発言」に悪い意味で影響されてしまう人間もいる、ということなんですよね…。
昨今「陰謀論を信じる人」が増えている、という社会問題がありますが…
客観的に見れば「どう考えてもおかしいだろう」ということを、なぜかネットの動画や記事だけで信じ込んでしまう人が、現実に増えているのです。
それを考えると、ネットの中に漂う「おかしな発言」を、ただ放置するのもどうか、というのはあります…。
…ただ「おかしなことを言う奴は喋るな」というのだと「言論の自由」の侵害や、人間の尊厳の問題にも関わってきてしまいます。
「おかしなことを言う人」がなぜ「おかしなことを言う」のかと言うと、そこには大概の場合「認知の歪み」があります。
大人になるまでに学んでおくべきだった「ものの考え方」や「ものの見方」を習得できていないので、変な方向に物事を考えてしまうのです。
なので、必要なのは「今まで見て来た狭い世界の殻をブチ破るための新しい視点」に気づいてもらうこと。
その人たちの知らない「別の視点」「別の考え方」を、様々な形で提示していくことなのではないかと…。
…もっとも「おかしなことを言う人」は精神的視野が凝り固まっていて、別の視点など「受け入れる気すら無い」ことも多いかと思われます。
なので、まずはその「別の視点」「新しい視点」に興味を持ってもらうことから始めなければいけないのですが…
…まず、ここからして難し過ぎて「そんなこと出来る人いるの?」ってレベルですよね…。
それでも「頭ごなしに相手を否定する」だけでは「意見を受け入れてもらう」どころではないので、何とかそういう方向でやっていくしかないわけですが…。
だからメールに絵文字があったり、L○NEにスタンプがあったりして、感情を「補完」するのでしょうけど…
そういう「補完」の一切無い文章って「感情が分からない」どころか「ネタなのかガチなのか?」すら区別できない時がありませんか?
特にX(旧Twitter)などの短い文章だと、内容も端的過ぎて「え?これ、ネタで言ってるだけだよね?
ネタで「おかしなこと」を言っている分には、おもしろがるなり、「ネタとしてはサムいな…」とビミョウな気持ちになるなりすればいい話なのですが…
ガチだとしたら「笑えない」…そんな投稿が、最近はよく目につく気がします…。
最近は「読書離れ」「活字離れ」が深刻ですが…
「本」というのは、単に「知識」を得るためのものではなく「他者の気持ちや視点を学ぶ機会」でもあるんですよね…。
それを失った人々の「精神的視野」が狭くなり、短絡的な物の見方しかできなくなっている…というのは、普通にあり得そうな話です。
さらに言うと、その肝心な「本」を含む「コンテンツ」も、どんどん単純化・エンタメ至上主義化し、いわゆる「考えさせ系」が減っているような気がします。
そんな現代事情を考えれば、本当に「ガチでおかしなことを言っている」人が増えても、不思議ではないのかも知れません。
…「ガチでおかしなことを言っている人」の何が怖いかって…普通に社会を悪化させそうな所なんですよね…。
「自分さえ良ければ他人がどうなっても構わない」という、極度の「自己中心的」思考…
「バレなければ犯罪を犯しても良い」とすら思っている「反社会的」思考…
「自分の言動がどんな結果をもたらすのか」まるで考えない「無責任」思考…
そんな人々が人類の「多数派」になってしまったら、普通に社会秩序が崩壊しますよね??
そもそも「おかしい」のが、それを「心の中だけに収めておく」こともせず、「堂々と公言」しているところなのです。
現代ではもはや「悪いことは隠れてやる」すら通用していないのか…と、世の人々の正気を疑ってしまうのですが…。
(そもそも「悪いことを悪いことと認識する能力」すら失われているのか…。それはそれで恐ろし過ぎるのですが…。)
ひょっとしたら「こんな悪いことを考えてるのは自分一人だけじゃないはずだ。お前らだって考えたことあるだろう」みたいな感じで「仲間集め」をしたいのかも知れませんが…
そんな感じで「悪い仲間」がどんどん増えていったら、やっぱり社会秩序崩壊じゃないですか。
イメージで言うと、どこぞの終末世界のように、文明の崩壊した荒野で悪者たちが「ヒャッハー!」する世界になってしまうじゃないですか。
そんな世界で、どれだけの人間が生き残っていけると思うのでしょう???
今はネットの中で「他人を足蹴にしてでも成り上がってやんぜ」とイキっている人たちだって、本当の崩壊社会に放り込まれたら、もっと悪くて暴力的な輩に一瞬でプチッと潰されて終わりじゃないですか??
自分は平穏な世界で幸せに暮らしていきたい人間ですので、わざわざ「悪い思考」「自分がカモにされるための思考」を世に拡散させたいとは思わないのですが…
…ひょっとして、そんなこと(自分の吐いた毒が、巡り巡って自分自身を蝕む)にすら気づいていないアレな人々が、今の時代は多いのでしょうか?
「これをガチで言っているのだとしたら、今の時代の人間って、どうなってしまっているのだろう?」――そんな不安に押し潰されそうになっているのは、きっと自分だけではないのでしょう。
昨今ネットでの「炎上」や「叩き」が過激化しがちなのは、おそらくはそんな「不安」や「恐怖」の裏返しなのではないでしょうか?
「この失言をガチで言っているのだとしたら、恐ろし過ぎる。今のうちに潰しておかなければ、我々の未来が脅かされる」――そんな神経過敏な不安感が、「やらかした人」への「叩き」をエスカレートさせてしまうのではないでしょうか?
…ただ、忘れてはいけないのは「その人の“真意”がどうなのかは、結局“他人”には分からない」ということです。
ほんの「ネタ」でつぶやかれたものを「ガチ」に受け取り過ぎて「炎上」するのは、双方ともに不幸なことです。
(…まぁ場合によっては、「それをネタにする時点で不謹慎」というケースもあったりするわけですが…。)
さらに言えば、ネットで発言しているのは、あくまで「ネットで発言できるだけの神経の持ち主」「ネットで発言できるだけの時間的余裕のある人」だけです。
それが人類の「全て」なわけではありません。
むしろ
(実際、芸能人の冤罪ねつ造事件の「元」を辿ったら、フェイク情報を流していたのはたった3人のユーザーだった…なんて事案もありましたよね。)
なので、ネットで「おかしな発言をしている人」がやたら目につくからと言って、そこまで過敏に怯える必要は無い…
…と、言いたいところなのですが…
問題は、そんな「おかしな発言」に悪い意味で影響されてしまう人間もいる、ということなんですよね…。
昨今「陰謀論を信じる人」が増えている、という社会問題がありますが…
客観的に見れば「どう考えてもおかしいだろう」ということを、なぜかネットの動画や記事だけで信じ込んでしまう人が、現実に増えているのです。
それを考えると、ネットの中に漂う「おかしな発言」を、ただ放置するのもどうか、というのはあります…。
…ただ「おかしなことを言う奴は喋るな」というのだと「言論の自由」の侵害や、人間の尊厳の問題にも関わってきてしまいます。
「おかしなことを言う人」がなぜ「おかしなことを言う」のかと言うと、そこには大概の場合「認知の歪み」があります。
大人になるまでに学んでおくべきだった「ものの考え方」や「ものの見方」を習得できていないので、変な方向に物事を考えてしまうのです。
なので、必要なのは「今まで見て来た狭い世界の殻をブチ破るための新しい視点」に気づいてもらうこと。
その人たちの知らない「別の視点」「別の考え方」を、様々な形で提示していくことなのではないかと…。
…もっとも「おかしなことを言う人」は精神的視野が凝り固まっていて、別の視点など「受け入れる気すら無い」ことも多いかと思われます。
なので、まずはその「別の視点」「新しい視点」に興味を持ってもらうことから始めなければいけないのですが…
…まず、ここからして難し過ぎて「そんなこと出来る人いるの?」ってレベルですよね…。
それでも「頭ごなしに相手を否定する」だけでは「意見を受け入れてもらう」どころではないので、何とかそういう方向でやっていくしかないわけですが…。
生成AIをめぐる問題で最近気になっているのが「生成AIで二次創作画を作ることの何が悪いの?ファンアートと同じじゃないの?」という論調です。
最初にこの意見を見かけた時「この違いが分からない人がいるんだ!?」と逆に衝撃を受けたのですが…
この2つの何が違うのか…分かっている方には、あまりにも「当たり前のこと」でしょうから、今さら説明することも憚られるのですが…
それって、ズバリ「情状酌量の余地」ですよね?
そもそも勘違いされている方が多いようですが…
「二次創作」というのは元々「著作権者の温情により見逃されているグレーゾーン」。
べつに「やってもOK!」と許されているホワイトゾーンでも何でもないのです。
古参の二次創作クリエイターさんたちはよく「二次創作者はなるべく日蔭者であれ」「権利者とは距離を取れ(間違っても凸するな)」などと言いますが…
それは「著作権者の堪忍袋の緒を切ってしまうと大変なことになる」と知っているからなのです。
…で、話を戻して生成AI画とファンアートの違いですが…
例えば皆さん「幼稚園児がクレヨンで一生懸命描いたプリキュアの絵」を「版権モノだからダメ!」なんて、冷たいことを言えますか?
…それ、普通に鬼じゃないですか。
ファンアートが黙認されている理由のひとつは「ファンが愛情を持って一生懸命描いてくれたものだから」なのです。
幼稚園児でなく大人だったとしても…
手間と時間をかけて描き上げられたファンアートは、時に作者でさえ敬意を覚えてしまうものなのではないでしょうか?
一方で「こんな絵を描いて」という命令文ひとつで(まぁプロンプトは1文とは限りませんが)ちょろっと出来上がってしまう生成AI画…
著作権者の心証が同じだと思いますか?
現代の一部のネット民は、何かと「感情論を排除」して「合法か違法か」だけで物事を見ようとしますが…
著作権法は「親告罪」――すなわち、著作権者が相手を訴えるか否かが、そもそもの罪の分かれ目なのです。
二次創作やSNSでのちょっとした「お遊び」が許されている背景には「これくらいなら、まぁいいだろう」「話題になって盛り上がってくれる分には有難い」という、著作権者の暗黙の「お目こぼし」があります。
一方で、作品の権利を侵害しかねないものや、作品の品格を落としかねないものは、普通に訴えられるリスク「大」なのです。
生成AI画のマズい所は、版権モノのオリジナル画と「区別がつかないレベル」の画像を生成できてしまうことにあります。
オリジナルそっくりのタッチで「原作にはあり得ないシーン」を描き出すこともできますし…
何も知らない視聴者が見たら「これって公式の画像(動画)?」という誤解もされかねません。
実際「権利者」は生成AIに対してかなりの危機感を抱いていますし、AI事業者を相手どった訴訟も国内外問わず頻発しています。
個人の生成AI利用者で言うと、2025年1月の「エヴァンゲリヲン」の「アスカ」の(性的な)AI生成ポスター販売や、6月のゴジラ海賊版DVD販売(生成AIでモノクロ映画をカラー化したとみられる)など、国内での逮捕者も出始めています。
全ての生成AI利用者がそうだとは思いませんが…
生成AI利用者の中には、明らかに「やって良いことと悪いことの境界線」が見えていない人がいます。
自分もX(旧Twitter)上で見かけたことがありますが…
当時放映中のアニメ(お子様も観る全年齢対象)キャラクターの卑猥な生成AI画像を、作品名・キャラ名(さらには生成AI画であること)を堂々と表記してUPしているもの等…
何重もの意味でアウトです(そもそもSNSの誰でも見られる場所に卑猥な画像をUPしているだけで相当なアウト行為…)。
「ファンが作品愛ゆえに描いたもの」なら許してくれる著作権者でも、「ファンかどうかも分からない人間がインプレッション稼ぎのためにチョロッと生成したもの(しかも卑猥)」に怒りや苛立ちを覚えないわけないじゃないですか。
思うに「AI生成画とファンアートの違いが分からない」という意見の中には「生成AIを使って版権モノでボロ稼ぎしたい→そのためには生成AI画を規制したがる風潮が邪魔だ→人の手による二次創作が許されているなら生成AIも許可しろ」という「さもしい本音」があるのではないでしょうか?
…ですが実際には、そうした一部の生成AI利用者の「暴走」が、かえって生成AIの「規制」を招くことになるのではないでしょうか?
そもそも二次創作界隈って元々「稼ごう」「儲けよう」という世界ではないんですよね…。
儲けは「元が取れれば万々歳」くらいな感じで「とにかく、この作品への愛を表現したい」というのが活動の源のはずなのです。
「稼ごう」「儲けよう」が目的になってしまったら、それは「商売」になってしまい「版権モノで許可無くビジネスしている」ことになってしまうのです。
「稼ぐ」「儲ける」が「お金」でなく「インプレッション」や「表示回数」「再生回数」でも同じこと。
(プラットフォームによっては、それで収益が出るものもあるわけですから。)
生成AI画像(動画)に「この作品への愛を自分の手で表現したい」という、一番肝心な「動機」はあるのでしょうか?
作品への愛が分かれば、たとえ絵が拙くとも、褒めてくれる同志はいますし、ファンになってくれる人もいます。
(実際自分も、一次・二次創作物問わず重視するのは、画力よりもネタの面白さです。)
むしろ「拙くても、一生懸命に愛を表現している」ところにアツさを感じて感動するのですが…
「生成AI画とファンアートの違いが分からない」という人は、そういう「人が情熱を傾けることの価値」が分からないのでしょうか?
どうにも昨今、「合理性」「コスパ」ばかりが重視されて「人の心」を見失ってしまっている人が増えていないでしょうか?
…と言うより、どうにも最近「手抜き」や「怠惰」や「雑な仕事」を「合理的」「コスパ」と言い訳している人が多くないですか?
どんなに「現代的な言い訳」で繕おうと、その裏にある「手抜き感」に、人は本能で気づくものなのではないでしょうか?
根性論や精神論を推すわけではありませんが…
「労を惜しんで結果や名声だけ得ようという人」を「全力で自作品への愛を表現してくれるファン」と同等に扱う気になれる人って、いるのでしょうか?
…これが分からない人は、人間として大切な何かを、既に見失ってしまっているのかも知れませんね。
人間が「人の心」を忘れて「人の労に価値を置かない」「人を大切にしない」社会…
それって、人間が幸せになれる社会なのでしょうか?
最初にこの意見を見かけた時「この違いが分からない人がいるんだ!?」と逆に衝撃を受けたのですが…
この2つの何が違うのか…分かっている方には、あまりにも「当たり前のこと」でしょうから、今さら説明することも憚られるのですが…
それって、ズバリ「情状酌量の余地」ですよね?
そもそも勘違いされている方が多いようですが…
「二次創作」というのは元々「著作権者の温情により見逃されているグレーゾーン」。
べつに「やってもOK!」と許されているホワイトゾーンでも何でもないのです。
古参の二次創作クリエイターさんたちはよく「二次創作者はなるべく日蔭者であれ」「権利者とは距離を取れ(間違っても凸するな)」などと言いますが…
それは「著作権者の堪忍袋の緒を切ってしまうと大変なことになる」と知っているからなのです。
…で、話を戻して生成AI画とファンアートの違いですが…
例えば皆さん「幼稚園児がクレヨンで一生懸命描いたプリキュアの絵」を「版権モノだからダメ!」なんて、冷たいことを言えますか?
…それ、普通に鬼じゃないですか。
ファンアートが黙認されている理由のひとつは「ファンが愛情を持って一生懸命描いてくれたものだから」なのです。
幼稚園児でなく大人だったとしても…
手間と時間をかけて描き上げられたファンアートは、時に作者でさえ敬意を覚えてしまうものなのではないでしょうか?
一方で「こんな絵を描いて」という命令文ひとつで(まぁプロンプトは1文とは限りませんが)ちょろっと出来上がってしまう生成AI画…
著作権者の心証が同じだと思いますか?
現代の一部のネット民は、何かと「感情論を排除」して「合法か違法か」だけで物事を見ようとしますが…
著作権法は「親告罪」――すなわち、著作権者が相手を訴えるか否かが、そもそもの罪の分かれ目なのです。
二次創作やSNSでのちょっとした「お遊び」が許されている背景には「これくらいなら、まぁいいだろう」「話題になって盛り上がってくれる分には有難い」という、著作権者の暗黙の「お目こぼし」があります。
一方で、作品の権利を侵害しかねないものや、作品の品格を落としかねないものは、普通に訴えられるリスク「大」なのです。
生成AI画のマズい所は、版権モノのオリジナル画と「区別がつかないレベル」の画像を生成できてしまうことにあります。
オリジナルそっくりのタッチで「原作にはあり得ないシーン」を描き出すこともできますし…
何も知らない視聴者が見たら「これって公式の画像(動画)?」という誤解もされかねません。
| 動画サイトのコメント欄など見ていると、生成AI動画に気づいていない人って、結構いるんですよ…。 一瞬とは言え、動画生成AIのロゴが出ているにも関わらず(個人的には、見づらい・分かりづらいロゴの出し方をしているAI事業者もだいぶ「思慮が足りない」とは思っていますが…(出すようになっただけ、まだマシではありますが))…。 |
実際「権利者」は生成AIに対してかなりの危機感を抱いていますし、AI事業者を相手どった訴訟も国内外問わず頻発しています。
訴訟だけでなく、10月末には日本漫画家協会とアニメ・出版業界団体による「生成AI時代の創作と権利のあり方に関する共同声明」というものも出されています。) |
個人の生成AI利用者で言うと、2025年1月の「エヴァンゲリヲン」の「アスカ」の(性的な)AI生成ポスター販売や、6月のゴジラ海賊版DVD販売(生成AIでモノクロ映画をカラー化したとみられる)など、国内での逮捕者も出始めています。
全ての生成AI利用者がそうだとは思いませんが…
生成AI利用者の中には、明らかに「やって良いことと悪いことの境界線」が見えていない人がいます。
| …と言うより、悪いことと分かった上で「匿名だし、捕まったりしないだろう」と高をくくって「やらかしている」気もしますが(実際に逮捕者は出ているのに…ニュースとか見ないんでしょうか?)…。 |
自分もX(旧Twitter)上で見かけたことがありますが…
当時放映中のアニメ(お子様も観る全年齢対象)キャラクターの卑猥な生成AI画像を、作品名・キャラ名(さらには生成AI画であること)を堂々と表記してUPしているもの等…
何重もの意味でアウトです(そもそもSNSの誰でも見られる場所に卑猥な画像をUPしているだけで相当なアウト行為…)。
「ファンが作品愛ゆえに描いたもの」なら許してくれる著作権者でも、「ファンかどうかも分からない人間がインプレッション稼ぎのためにチョロッと生成したもの(しかも卑猥)」に怒りや苛立ちを覚えないわけないじゃないですか。
思うに「AI生成画とファンアートの違いが分からない」という意見の中には「生成AIを使って版権モノでボロ稼ぎしたい→そのためには生成AI画を規制したがる風潮が邪魔だ→人の手による二次創作が許されているなら生成AIも許可しろ」という「さもしい本音」があるのではないでしょうか?
…ですが実際には、そうした一部の生成AI利用者の「暴走」が、かえって生成AIの「規制」を招くことになるのではないでしょうか?
| 一部の利用者が生成AIで著作権を侵したり、モラルに反したAI生成を行うたびに、「そういうことをしていない利用者」まで含めた「生成AI全体のイメージ」が暴落します(現代人は「分けて考えることをせず、属性で物事を決めつけたがる」人が多いので)。 なので「真っ当にAI利用をしている人」も、この問題を「他人事扱い」すべきではないのです。 |
そもそも二次創作界隈って元々「稼ごう」「儲けよう」という世界ではないんですよね…。
儲けは「元が取れれば万々歳」くらいな感じで「とにかく、この作品への愛を表現したい」というのが活動の源のはずなのです。
「稼ごう」「儲けよう」が目的になってしまったら、それは「商売」になってしまい「版権モノで許可無くビジネスしている」ことになってしまうのです。
「稼ぐ」「儲ける」が「お金」でなく「インプレッション」や「表示回数」「再生回数」でも同じこと。
(プラットフォームによっては、それで収益が出るものもあるわけですから。)
生成AI画像(動画)に「この作品への愛を自分の手で表現したい」という、一番肝心な「動機」はあるのでしょうか?
作品への愛が分かれば、たとえ絵が拙くとも、褒めてくれる同志はいますし、ファンになってくれる人もいます。
(実際自分も、一次・二次創作物問わず重視するのは、画力よりもネタの面白さです。)
むしろ「拙くても、一生懸命に愛を表現している」ところにアツさを感じて感動するのですが…
「生成AI画とファンアートの違いが分からない」という人は、そういう「人が情熱を傾けることの価値」が分からないのでしょうか?
どうにも昨今、「合理性」「コスパ」ばかりが重視されて「人の心」を見失ってしまっている人が増えていないでしょうか?
…と言うより、どうにも最近「手抜き」や「怠惰」や「雑な仕事」を「合理的」「コスパ」と言い訳している人が多くないですか?
どんなに「現代的な言い訳」で繕おうと、その裏にある「手抜き感」に、人は本能で気づくものなのではないでしょうか?
根性論や精神論を推すわけではありませんが…
「労を惜しんで結果や名声だけ得ようという人」を「全力で自作品への愛を表現してくれるファン」と同等に扱う気になれる人って、いるのでしょうか?
…これが分からない人は、人間として大切な何かを、既に見失ってしまっているのかも知れませんね。
人間が「人の心」を忘れて「人の労に価値を置かない」「人を大切にしない」社会…
それって、人間が幸せになれる社会なのでしょうか?
ブログ内検索
カテゴリー
管理人プロフィール
- 【HN(ハンドル・ネーム)】
- 津籠睦月(つごもりむつき)
- 【職業】
- 社会人(毎日PCを使う仕事。残業も休日出勤も普通にあります。)
- 【趣味】
- 小説・HP制作、読書、猫と遊ぶこと。
- 【好きな小説ジャンル】
- ファンタジー、冒険、恋愛、青春、推理、濃い人間ドラマの展開するモノ。
- 【備考】
- 漢検2級(準1以上は未受験)。国語の最高偏差値80(高2時点)。
ブログ更新&チェックについて。
このブログは管理人に時間の余裕がある時にちょこっとずつ更新していく予定ですので、更新やチェックの頻度はおそらく数週間に1回~下手をすると1ヶ月以上の間が空いてしまう可能性も…。
もし更新が滞ったても「あぁ、仕事が忙し過ぎて時間が無いんだな」と気長にお待ちいただければ幸いです。
最新記事
(12/29)
(12/18)
(12/06)
(11/29)
(11/23)
WEBサイト及びオリジナル小説
カスタマイズ系
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ

和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
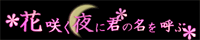
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
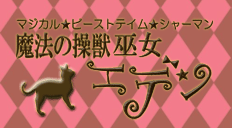
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
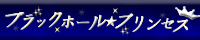
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」

乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)

恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
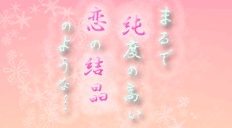
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
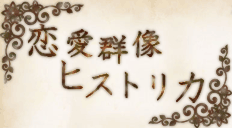
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
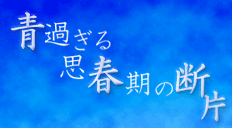
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
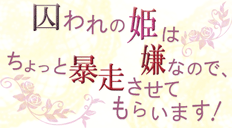
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
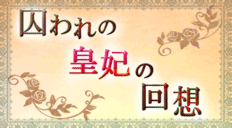
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
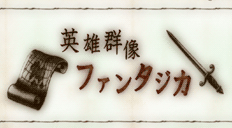
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
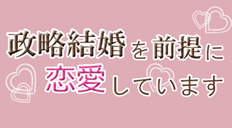
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
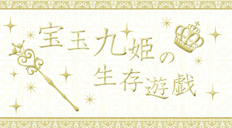
ファンタジー小説サイト
「言ノ葉ノ森」TOPページ
和風ファンタジー小説「花咲く夜に君の名を呼ぶ」
魔法少女風ファンタジー小説「魔法の操獣巫女エデン」
異世界召喚ファンタジー小説「ブラックホール・プリンセス」
児童文学風ファンタジー小説「夢の降る島」
乙女ゲーム風ファンタジー小説「選帝のアリス」
(pixiv投稿小説)
恋愛SSオムニバス「まるで純度の高い恋の結晶のような…」
歴史恋愛短編オムニバス「恋愛群像ヒストリカ」
青春SSオムニバス「青過ぎる思春期の断片」
自作RPG転生小説「囚われの姫は嫌なので、ちょっと暴走させてもらいます!」
恋愛ファンタジー小説「囚われの皇妃の回想」
ファンタジーSSオムニバス「英雄群像ファンタジカ」
恋愛SSオムニバス「政略結婚を前提に恋愛しています」
ファンタジー長編オムニバス「宝玉九姫の生存遊戯」
カウンター
相互RSS
P R

